ハバネロの育て方

ハバネロの育てる環境について
植物の成長で最も重要なのは日光です。日当たりのいいところで育てるようにしましょう。最低でも5時間程度は日が当たるところが望ましいです。日の当たる時間が少ないと、植物が自身の成長を維持させるために枝や茎が間延びして伸びてしまいます。こうなると、
病気にかかりやすく、暑さや寒さにも弱くなるので気をつけましょう。ただし、鉢植えで栽培する場合は、夏場は原産地より高温になるため、鉢の中の温度が高温になり、花を咲かせても落ちてしまう可能性があるので、午後から日陰になるところに置くようにしましょう。
庭に植える場合はその心配は必要ないので、なるべく日が当たる所を選んでください。熱帯性の植物のため、日本では一年草として扱いますが、室内栽培で育て方を間違えなければ越冬させることも可能です。越冬させるためには、最低でも3~5℃程度の気温が必要です。
寒くなる前に室内に入れ、越冬中は細かな葉を刈り取り、最低限の水だけで乾燥状態にします。低い温度で冬越させる場合は日光が少なくても大丈夫ですが、置く場所の気温が高い場合はそれなりの日当たりが必要となります。翌年、気温が上がってきたら、少し大きな鉢に植え替えるといいでしょう。
しかし、ハバネロはナス科の植物であり連作を嫌うため、前年と比べて収穫量が減ったり、実が全体的に小さくなることが多く、越冬の手間のわりに見返りは少ないといえます。前年同様の収穫を望むなら、新しく種をまくか苗を購入した方がいいでしょう。
ハバネロの種付けや水やり、肥料について
熱帯地域の植物であるため、夜間の温度が20℃以上になる頃が発芽しやすいです。このことから、地域にもよりますが、通常5~7月頃に種をまきます。1本の木から大量の果実が収穫できるので、種をまきすぎないように注意しください。気温が低い時期に種をまくと発芽するのに時間がかかり、
途中で発芽しなくなることもあります。また、遅すぎると発芽してから花が咲いて、実をつけるための時間がなく途中で枯れてしまうことがあるため、遅くとも7月までには種をまくようにしましょう。種をまいたら、種が隠れる程度に土をかけます。
発芽には土が常に湿っている状態が一番です。多すぎると発芽せずカビが生えることもあり、途中で完全に水が切れると発芽しかけていたものが枯れてしまうので、気をつけましょう。発芽までは、種まき後3週間程度かかりますが、気温が高い6~7月にまくと1週間程度で発芽してきます。
発芽して以降は、午前中に鉢の底から流れ出るくらいたっぷりと水を与えて、夕方には水が切れているという状態を維持するようにしましょう。水分が多いと間延びする原因となります。鉢皿に溜まった水は捨ててください。本葉が5~6枚程度になるまで育ったら、
緑色が濃く、茎がしっかりした苗以外は間引いておきます。肥料は、緩効性肥料か液体肥料を商品に表記されている分量にそって、3~4週間に1度与えれば十分ですが、もともと強い植物なので、それほど気をつかう必要はありません。
ハバネロの増やし方や害虫について
果実は非常に刺激が強いが、葉や茎には刺激がないのでアブラムシ、カタツムリ、ヨトウムシの被害を受けることが多々あります。カタツムリやナメクジは成熟した果実も食べるため注意が必要です。枯葉が鉢の中に入っていると害虫が付きやすくなるので、
こまめに掃除するようにしてください。また葉や茎をよく観察し、害虫がついていないか定期的に調べておきましょう。害虫が発生してしまった場合、市販のスプレー式の園芸用殺虫剤を散布するのが最も一般的ですが、害虫が大きくなってしまうと効果が見られないこともあります。
その時は、見つけ次第捕まえて駆除するようにしましょう。葉に病気が出てきた場合、数枚程度ならば症状が出ている葉を除去して様子を見ます。被害が大きい場合は、害虫の場合と同様に市販の薬剤で対処しましょう。翌年も栽培するならば、霜が降りて株が枯れてしまう前に実を収穫し、種を取ります。
種をとる際には、大きく熟した果実を選ぶようにしましょう。小さい果実の場合だと、種に含まれる養分が十分でないことがあり、発芽の確率が低くなることがあります。大きくて完熟した果実を収穫したら縦に割り、種を取り出して、涼しい所で乾燥させます。
近くで別のトウガラシを栽培している場合、交雑して品種が変わってしまうことがあるので注意してください。乾燥させた種は、気温が低い時期であれば机の引き出しなどで保管できますが、夏を越えて保管する場合は、密閉できる容器に入れて冷蔵庫などに入れておきましょう。
ハバネロの歴史
ハバネロはトウガラシの一種で、原産地はアマゾンかその周辺の地域だといわれており、そこからユカタン半島に伝わったと考えられています。ペルーやメキシコの遺跡の発掘調査によって、ハバネロを含むトウガラシ属が利用され始めたのは紀元前8000年ごろのことで、
他の地域で栽培化されるよりも早く利用されていたことが分かっています。トウガラシが使われ始めたころは、集落の近辺に生えていた野生の品種を利用していましたが、改良や栽培化が進み、メキシコでは紀元前1500年には栽培化が完了したと考えられています。
原産地の南米ではトウガラシ属の10種類が利用されていますが、そのうち5種類は基本的に原産地で栽培化され、また現在でも生息地を移動せず、ほぼ野生状態で利用されている品種もあります。世界一辛いトウガラシとして激辛スナック菓子に使用されたことで、
急激に知名度を上げましたが、2007年2月にブート・ジョロキアが世界一辛いトウガラシとしてギネスブックに認定されるなど、現在ではハバネロよりも辛いトウガラシが存在する事が分かっています。近年さらに研究が進み、テキサス州の研究者が、
ユカタン半島の辛いハバネロとボリビアの辛くないトウガラシを掛け合わせ、風味はハバネロそのものだが、辛くないハバネロを作ることに成功しています。ユカタン半島では現在、年に1500トンが生産されており、その他の産地としてブラジル、コスタリカ、ベリーズ、アメリカなどがあります。
ハバネロの特徴
ハバネロの特徴はなんといってもその辛さで、一説には一味唐辛子の20倍もあるとも言われています。刺激が非常に強く、付着したハバネロの汁を放置していると、皮膚が火傷したようになってしまう場合もあります。そのため、眼の周辺や鼻、皮膚の弱い部分に汁が付着した場合は、
すぐに洗い流す必要があります。辛さに注目されがちですが、ただ辛いだけではなく柑橘系のフルーティーな香りもあるため、肉料理やカレーなどに使用することによって、料理の味を向上させることができます。辛い料理が好きな方はスープに入れたり、煮込み料理にも入れるのもいいでしょう。
しかし、日本食のような淡白な風味の料理に使用してしまうと、ハバネロの風味で台無しになってしまうので注意が必要です。実の形は一般的なトウガラシのような長細い円すい形ではなく、先が尖ったいびつなトマトのような形をしています。熟す前の実は緑色ですが、
熟すと様々な色に変化します。最も一般的なのはオレンジ色ですが、白やピンク、ブラウンといった色になる場合もあります。ハバネロに含まれるカプサイシンの発汗作用にはダイエットに効果や、免疫力を高め風邪などの予防に期待できるとして、
健康食としても注目されています。最近は栽培セットが販売されていたり、ホームセンター等で苗や種が売られており、用意に手に入れることができます。野菜としてはかなり容易に栽培できる部類なので、初心者が挑戦しても失敗せず育てることが可能です。
野菜の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:ビート(テーブルビート)の育て方
-

-
ブライダルベールの育て方
ブライダルベールは吊り下げるタイプの観葉植物が流行した昭和50年代に日本に登場しました。英語での名称は「タヒチアンブライ...
-

-
グロリオサの育て方
グロリオサはアフリカ、熱帯アジアが生息地で5種が分布するつる性植物です。グロリオサの名前はギリシア語の栄光ある、名誉ある...
-

-
リクニス・ビスカリアの育て方
リクニス・ビスカリアの歴史はそれほど解明されていません。実際語源はどこから来ているのかははっきりしていませんが、属名のリ...
-

-
マグノリアの育て方
マグノリアはアジアとアメリカなどが原産で生息地のモクレン属の植物です。中国では玉蘭、白蘭などと呼ばれており、品格のある高...
-

-
植物の育て方で考えるべき要素や種類の選択について
植物の栽培を考える上で考えるべき事は、栽培する植物に合わせた環境を作るという事に尽きると言えます。特に重視したいのは肥料...
-

-
レダマ(スパニッシュブルーム)の育て方
レダマ(スパニッシュブルーム)は、マメ科の低木になります。主に、南ヨーロッパとカナリア諸島が原産地になります。世界各地の...
-

-
モミジバアサガオの育て方
モミジバアサガオは和名をモミジヒルガオといい、日本で古くから親しまれてきたアサガオの仲間です。日本へ伝来したのは今から1...
-

-
初心者でも栽培しやすいえんどう豆の育て方について説明します。
えんどう豆の栽培は、マメ科なので前回マメを育てた場所での栽培は避けた方が無難です。しかし、えんどう豆は日当たりが良く水は...
-

-
フリージアの育て方
フリージアは南アフリカ原産のアヤメ科の植物です。ケープ地方に10種類あまりが分布していますが、現在よく栽培されているもの...
-

-
シノグロッサムの育て方
シノグロッサムはワスレナグサの仲間でムラサキ科に属する植物です。秋まき一年草で中国南部原産ですが、ワスレナグサ自体はヨー...




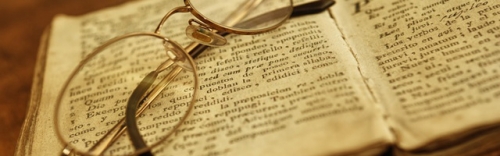





ハバネロはトウガラシの一種で、原産地はアマゾンかその周辺の地域だといわれており、そこからユカタン半島に伝わったと考えられています。ペルーやメキシコの遺跡の発掘調査によって、ハバネロを含むトウガラシ属が利用され始めたのは紀元前8000年ごろのことで、他の地域で栽培化されるよりも早く利用されていたことが分かっています。