アザミの仲間の育て方

アザミの仲間の育てる環境について
栽培環境としては、暖かい日差しのある日向で 、風通しの良い環境での栽培がベストです。 庭に植えて楽しむことも多い花ですが、地面や環境が、とても乾燥をするような場所は向いていません。種類も豊富なアザミの仲間ですから、基本的に生息地も様々です。
割と高めの山に育つ種類や、崩壊地に育つような種類であれば、ロックガーデンを築いてみるのもよいでしょう。季節の草花が、ちょこんと顔を出すようなロックガーデンは、広めの庭がある家庭では粋なスペースにもなります。それほど広い庭ではなくても、バランスよく岩を組んでみるのもいいものです。
そこまでは無理であっても、高山植物用である用土を搬入したゾーンに。植え替えをしてみるのも良い方法です。森林の中に生える種類もありますから、その場合は森林の環境に知覚してあげます。たくさんの木を植えるわけではなく、 森林の中を歩くと、木々の合間から光が木漏れ日となって降り注ぐものです。
そんなイメージで、ある程度の遮光を心がけます。日差しの協力になる真夏のシーズンは、40%から50%遮光を行います。これにより過剰な日差しを防いで、日焼けしてしまうのも防止することになります。
アザミの仲間は本当に様々なす類がありますから、大型の種類も存在します。サイズが大きめの種類になってくると、鉢を使っての栽培は大変になってきます。そのため、大型の場合は鉢植えにはしないで、庭に植えて成長を楽しみましょう。
種付けや水やり、肥料について
アザミの仲間の植え付けや植え替えですが、鉢植えでの管理であれば、適切な時期としては、2月から3月あたりでし ょう。直接庭の土に植えているケースであれば、植え替えなどは特に行うことはありません。水やりですが、家庭での管理においては、土の表面をチェックしてミス槍をするようにします。
自生している場合は、自然の流れで雨水などで水分補給を行っていますが、鉢植えなど家庭での栽培であれば、人間が気にかけてあげる必要があります。アザミの仲間類は、土の表面が白く乾いてきたら、水を十分にあげましょう。
栽培する環境としても、乾燥が激しすぎるのは向いていないため、鉢植えでの栽培は、適度な水分補給が重要なポイントとなります。しかし庭に植えている場合は、話が少し違ってきます。家庭の庭であっても、外で育っている花になります。よほど雨が降らないで、
乾燥もひどいということがな ければ、庭に植えている場合は水やりはしなくても大丈夫です。湿地性に育つ種類のキセルアザミみたいな種類も存在しますから、こういった場合は、乾燥を防止する対策をしてあげましょう。浅い状態でいいので、腰水をすることで、
外部の乾燥から守ることができます。肥料ですが、植物のサイズに合わせた、適切な量を様子を見ながら与えてあげましょう。ノアザミであれば、りん酸やチッソ、カリウムなど配合の緩効性肥料を、株が成長しているあいだは与えます。地植えしているケースでは、特に与えなくても平気です。
仲間の増やし方や害虫について
アザミを増やしていくときにきになるのが、病気や害虫の存在です。特にメインとなって登場しやすい害虫というのはない ものの、アブラムシが発生することはあります。野菜や花類にも寄生しやすい害虫で、病気を運んできてしまう困りものでもあります。
アブラムシ類への対策で知って起きて損がないのは、光を反射して眩しいものを苦手とする、ということです。光り物が苦手な油虫除けには、忌避資材を使用した対処もあります。ホームセンターなどで売っている、シルバーポリフィルムなんかを、周囲に貼っておくというのも、ひとつの手段になります。
スプレーヨプの容器に牛乳を入れて、存在を確認したらスプレーする、といった方法もあります。天気の良い日に行うのがコツで、牛乳が渇いた時に効果は実感できるタイプです。病気という面から見ると、こちらも特にはありません。
たまにですが、うどんこ病が発生する ケースもあります。もしもうどんこ病を発見したら、窒素肥料が多すぎる可能性がありますから、肥料は少なめにすることです。もうひとつ気をつけたいのが、通気性の悪さです。できるだけ、風通しの良い環境を整えてあげましょう。
増やす方法は、タネをまくか、株分けするといった方法があります。最も良いのは、タネでの増やし方です。時期的には、2月から3月くらいに、タネをまくとよいです。スムーズに株が成長をすれば、つぎの年にはキレイな花を咲かせて目を楽しませてくれます。
アザミの仲間の歴史
アザミの仲間の種類は多く、科属はキク科アザミ属です。生息地で言うと、日本に多く見られるのは、日本が原産国であるためです。栽培されているものもあれば、自生している花もあります。ドイツあざみはよく目にするタイプの種類ですが、このネーミングでは、
ドイツが原産なのかと勘違いしがちです。ドイツと付いていますが、日本が原産国になります。ドイツあざみは世間一般で通っている呼び方になります。はなあざみという別名も持っていて、楽音寺あざみや寺岡あざみといった、色の鮮やかさも特徴的な種類になります。
ドイツあざみの育て方としては、中性の土壌で陽のひかりによく当ててあげることを心がけることです。アザミ属は北半球において は、250種の種類があると言われています。原産国である日本においては、種類は100種類を超えています。
花の種類の分布されている地域は、広いこともありますが、種類によってはとても狭い地域にのみ育つ種類もあります。種間雑種などが見られる地域もあります。標準的な和名を、それだけでアザミとする種はないです。日本生まれの花ではありますが、スコットランドの国花でもあります。
北西ヨーロッパのグレートブリテン、そして北アイルランド連合王国などの4つのカントリーのうちの一つです。色彩も割とはっきりしており、遠目には可愛らしい花に見えるものの、近づいてみると、トゲがあることに気がつきます。そのため、さわると痛い種類も多いです。
アザミの仲間の特徴
アザミの仲間の特徴として、色の鮮やかさもあります。魅力的なはっきりした色合いも多い花ですが、トゲを持つタイプも多いのも特徴的と言えるでしょう。日本人にも馴染みある、最もたくさん育てられているタイプは、ノアザミになります。
山でも割と高めの山に咲いていたり、海岸沿いに咲いていることもあります。山道で見かける花でもありますし、とても日当たりの良い草原にも、イキイキとしたカラーで咲いています。日本で輝きを発揮している花でもありますが、台湾や中国東部んどにも分布している花です。
アザミの仲間たちの特徴として、花が咲いている期間が長めというのもあります。春頃に花を見たと思ったら、秋ころまで花を楽しむことができます。分布する地域は非常に広いもので、広い 地域に様々な変わった種類や亜種を見ることができます。
ほかの種類のアザミの花との交雑により、新たな雑種が誕生しているケースもあります。花の形状としては、直径3cm程のサイズです。開花をしている時には、根元にある葉っぱは、既に枯れています。世界中にアザミの仲間の種類はあって、数も300種類あると言われています。
日本国内においては、その数の1/3ほどの種類が集中して咲いています。日本列島の特産であることが、大部分を占めています。森林や湿地帯、崩壊地や亜高山帯、亜熱帯の海岸など、とてもいろんな場所に生えている花です。種類の識別が若干困難であることも、アザミの仲間の特徴です。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:アスコセントラムの育て方
タイトル:アジュガの育て方
-

-
クリサンセマム・ムルチコーレの育て方
クリサンセマム・ムルチコーレの生息地は、ヨーロッパ西部と北アフリカなどの地中海沿岸です。アルジェリア原産の耐寒性または、...
-

-
ヒトツバタゴの育て方
20万年前の近畿地方の地層から、泥炭化されたヒトツバタゴがみつかっています。しかし、現在の日本でヒトツバタゴが自生するの...
-

-
トリカブトの育て方
トリカブトは日本では”鳥兜”または”鳥冠”の由来名を持っています。この植物の花の形が舞楽で被る帽子の鳥冠に似ている事から...
-

-
レーマンニアの育て方
観賞用として栽培されているエラータは葉っぱの形が楕円のような形をしていて、5月ぐらいか暑いシーズンになると、花茎が長い花...
-

-
黄花セツブンソウの育て方
キバナセツブンソウはキンポウゲ科セツブンソウ属ということで、名前の通り黄色い花が咲きます。この植物はエランシスとも呼ばれ...
-

-
セルリア・フロリダの育て方
”セルリア・フロリダ”は南アフリカケープ地方が原産の植物になります。日本にはオーストラリアから切り花として入ってきた植物...
-

-
タチアオイ(立葵)の育て方
タチアオイは立葵と漢字で書かれて、名前の通り立ってるように高く伸びて育つ植物です。育て方は比較的簡単な植物になります。し...
-

-
クロバナロウバイの育て方
クロバナロウバイは北アメリカ南東部原産の低木で、原産地全域の山林や人里周辺を生息地としています。漢字では黒花蝋梅と書き表...
-

-
カラミンサの育て方
カラミンサはシソ科のハーブで白やピンク、淡い紫色の小さな花をたくさんつけることで人気となっている宿根植物で葉の部分はハー...
-

-
アルテルナンテラの育て方
植物の特徴として、まずはヒユ科であることがあげられます。草丈は10センチぐらいから20センチぐらいの大きさです。木のよう...




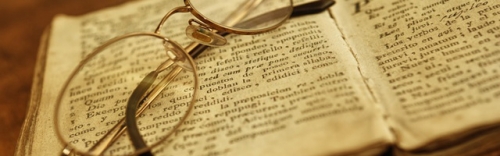





アザミの仲間の種類は多く、科属はキク科アザミ属です。生息地で言うと、日本に多く見られるのは、日本が原産国であるためです。栽培されているものもあれば、自生している花もあります。