ツキヌキニンドウの育て方

育てる環境について
ツキヌキニンドウの育て方のポイントとして剪定や誘引は重要とされます。この植物はツル性の植物であること、耐寒性や耐暑性が高い事、そして丈夫であり、葉は常緑性もしくは半常緑性であることなどからも、そのままにしておくとどんどん伸びてしまいます。
剪定は、適度にカットをしてあげるなどして風通しを良くさせたり、花つきを良くさせるなどの効果に繋がりますし、見栄えもよくなります。誘引はツルを伸ばす方向を考えて植物に指示を与えるものであり、これ等をきちんと行って管理をしていく事が大切です。
また、育てる環境となる植え付けを行う場所を考えて植え付けないと庭の中が煩雑になりかねません。尚、ツキヌキニンドウは土質についてはそれほど選ぶ必要はないのですが、水はけが良い土壌を選んでおくことは大切で、水はけが良い場所を選ぶ事で乾燥を防止出来ますし、根腐れなどが起きずに済みます。
また、日当たりも重要な要素の一つですが、午前中に太陽の光が当たり、午後からは日陰になるような場所を選ぶと良いとしています。尚、栽培する地域にもよりますが、寒冷地などでは冬場は葉は落葉となりますが、暖地においては葉はそのまま残るため、
冬場の乾いた風、冷たい風などに出来る限り当たらない場所を選ぶ事は大切で、これにより葉を傷めずに済みますし、常に綺麗な葉を見る事も可能になります。尚、用土としては水はけが良い物を選ぶ事がポイントであり、赤玉土の小粒を5、鹿沼土の小粒を2、腐葉土を3の割合で配合して用土を作り利用します。
種付けや水やり、肥料について
ツキヌキニンドウなどの常緑性のスイカズラの仲間と言うのは、3月から4月頃に植え付けや植え替えを行うのが良く、腐植質に富んだ土壌を好みますので、根鉢の2倍の深さと幅を持つ穴を掘り、掘り上げた土に腐葉土を1/3ほど合わせてよく混ぜ合わせてから植え付けを行います。
尚、鉢植えの場合でも、2年に1度の割合で根を1/3程度の長さに整理をしてあげてから、一回り大きな鉢に植え替えを行って上げると良いです。こうする事で、根がどんどん伸びて行くため、栄養を根から吸い上げて生育を高めることが出来ます。肥料については、生育期となる5月から7月頃と、
開花期となる6月から9月頃にそれぞれ月一度の割合で緩効性化成肥料を施してあげます。また、新芽が伸びる前、花の咲き終わった後などには、株元に化性肥料、油かすと骨粉を同量混ぜたものなどを適量置肥としてばらまいてあげると良いです。水やりについては、
庭植えの場合は特別必要はないのですが、それでも極端に乾燥してしまう真夏の高温期には、夕方に水やりを行うと良いです。尚、朝に水を与えてしまうと日中の高温度により根が蒸してしまうので注意が必要で、夕方がベストと言ます。
また、鉢植えの場合は庭植えとは異なり定期的な水やりは必要で、枝が伸びる春から秋までの期間は十分に水を与えてあげます。尚、ツルが伸びやすい性質となりますので、支柱やフェンスなどを利用して、ツルを絡ませるように管理をしてあげることも大切です。
増やし方や害虫について
ツキヌキニンドウはツル性の植物であり、丈夫な常緑性の植物であることからも、ツルは良く伸びます。誘引と言って、ツルを誘うようにして挙げる事も、この植物の栽培における管理の1つであり、フェンスに絡ませるように誘引を行ってあげたり、アーチ仕立て、ポール仕立てなどにします。
尚、この植物は自分から支柱などに絡まる力は弱いとされており、その都度ツルを誘引させてあげるのが育て方のポイントの一つでもあるのです。株の増やし方としては挿し木で増やす事が出来ます。7月から8月に挿し木用の枝を剪定しますが、その年に伸びた枝の中でも、
やや充実して堅くなったものを選び、挿し木を挿す用土は、鹿沼土の小粒や赤玉土の小粒などの挿し木用の用土に挿しておきます。誘引と同時に剪定も手入れとして必要となる作業です。剪定は、伸び出たつるを切り詰める程度で良いのですが、ツルが伸びすぎてしまい、
樹形を整えたい時、いろいろと仕立てたい時などは、形や大きさなどに応じて、ツルを切り戻してあげる必要が有ります。尚、剪定作業は芽が出る前に行うのが良く、2月から3月の上旬頃が適期となります。花芽は切り戻した部分から発生する、
新しい枝の先端に出てくるので、切り戻しを失敗したからと言って花が咲かないと言う事は無く、日照および温度が在る事で開花となります。尚、ツキヌキニンドウは丈夫な植物であり、かかりやすい病気や発生し易い害虫は殆ど見られないと言われています。
ツキヌキニンドウの歴史
ツキヌキニンドウはアメリカ原産のツル性の植物で、5月頃から10月頃までの春時期から秋口にかけて、細長く先端部分が開いた、漏斗型の花を、枝先に10輪ほどつけてます。花色としては赤色の品種が一般的ですが、オレンジ色、クリーム色、黄色、赤紫色と言った
花色を持つ品種、花が咲いた後には大豆ほどの大きさを持つ、真っ赤な実を付ける品種などの園芸品種が存在しています。葉については、互生と呼ばれる、茎を挟むように一節に2枚の葉が付く状態で出て来るのですが、花に近い先端の場所には2枚の葉がくっついて出て来る合着となり、
茎が葉の中心から突き抜けているように見える事からも、「突抜(ツキヌキ)」と言ったの名前を持ち、和名として「ツキヌキニンドウ(突抜忍冬)」という名前の由来が在ります。尚、他にもロニセラを初め、ロニケラ、ハニーサックル、スイカズラと言った別名が在り、
この植物はスカズラ科のスイカズラ属に分類されています。生育については旺盛であり、ツル科の植物と言う事からも、ぐんぐんと枝を伸ばして行き、つる長さとしては6mから7mにも伸びるものが在ると言います。北アメリカ東部から南部にかけてが主な生息地と言われており、
常緑性であることからも葉を常に持つこと、開花期が長い事、甘い香りを持つこと、そして初心者でも栽培がし易いなどの特徴を持っており、1株を植えるだけで庭を明るくすることが出来るなど、丈夫な植物であることからも人気が高いといされています。
ツキヌキニンドウの特徴
ツキヌキニンドウは、半常緑から常緑性となるツル科の植物で、スイカズラ科スイカズラ属に分類されています。北アメリカの東部および南部などが主な生息地であり、アメリカ原産の花木です。この植物の葉と言うのは、対生して生える枝先の葉の部分が基部で合着しているため、
これを見ると茎が葉を突き抜けているように見えるのが特徴であり、この特徴からも、「ツキヌキ」、冬でも落葉しないスイカズラであることからも、「忍冬(にんどう)」とも呼ばれるようになったと言います。この植物の葉は、茎の下の方は互生となり対生して生えており、
それが上部の葉となると合着と言った2つの葉がくっついて丸い形のようになっているのが最大の特徴です。また、合着している葉の上には、オレンジ色や黄色、赤紫色、クリーム色、赤色などの花を咲かせるのも特徴と言えます。尚、ツキヌキニンドウが代表的とも言われているスイカズラの仲間と言うのは、
北アメリカの東部から南部にかけての北半球に幅広く分布しており、その数は約180種だと言われています。また、ロニセラ、ロニケラ、ハニーサックル、スイカズラなど色々な呼び名で呼ばれていますが、ロニセラ、ロニケラは学名、ハニーサックルは英名、スイカズラは属名でもあるのです。
尚、この植物は耐暑性や耐寒性がとても強く丈夫であり、この特徴からも初心者でも育てやすいと言われています。また、6メートルから7メートルなどの大きさになる事からも園芸品種の中でも人気が高いツル性の植物です。
-

-
ペトレアの育て方
ペトレア属はクマツヅラ科の植物で、一口にペトレアといっても様々な種類があります。およそ30種類ほどあり、その中でも日本で...
-

-
パキスタキスの育て方
キツネノマゴ科に分類される低木です。樹高は0.5mから1m程度ですが、放置すると2mほどになることもあります。熱帯性なの...
-

-
ダイアンサスの育て方
ダイアンサスは、世界中に生息地が広がる常緑性植物です。品種によって、ヨーロッパ・アジア・北アメリカ・南アフリカなどが原産...
-

-
ゲッキツ(Murraya paniculata)の育て方
奄美大島以南、沖縄から東南アジアにかけてが生息地で、ゲッキツ(月橘)の名は、花が特に月夜に橘のようによく香るからと言われ...
-

-
ネリネの育て方
ネリネという名前の由来はギリシア神話の海の女神であるネレイデスにちなんだものです。花びらに金粉やラメをちりばめたようなき...
-

-
ドクゼリの育て方
ガーデニングなどの植物を育てるということは、本来自然にある自生の植物を自分の所有する庭に囲い込み、好みに合わせた箱庭を作...
-

-
オブッサの育て方
このオブッサとは丸いという意味だそうですが、葉も丸みを帯びていて、独特な柔らかさのある丸い葉なので、穏やかさも演出してく...
-

-
グレコマの育て方
グレコマの科名は、シソ科 / 属名は、カキドオシ属(グレコマ属)となります。和名は、カキドオシ(垣通し)、その他の名前:...
-

-
ラッカセイの育て方
ラッカセイは、マメ科になります。和名は、ラッカセイ(落花生)、その他の名前は、ピーナッツと呼ばれています。ラッカセイは植...
-

-
キャッツテールの育て方
キャッツテールの原産地はインドで、ベニヒモノキにも似ています。しかし匍匐性の小型種であり、亜熱帯地方や亜熱帯を生息地とし...




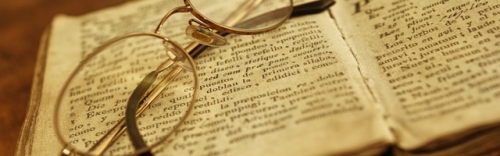





ツキヌキニンドウはアメリカ原産のツル性の植物で、5月頃から10月頃までの春時期から秋口にかけて、細長く先端部分が開いた、漏斗型の花を、枝先に10輪ほどつけてます。