アローディアの育て方

育てる環境について
マダガスカル島の南部が生息地の植物のため、気候は乾燥地帯で雨季はありますが殆ど雨が降らないような場所で自生しています。マダガスカル島の気温は1年間を通しても10度以下になることはまずありません。その為、気温が低い環境で育つ力がないといっても良いので、寒い温度で育つのとても難しいです。
その為、日本で育てる環境と庭などに植えて育てることはまず不可能です。夏は日本でも十分なほど気温が高くなるため問題ありませんが、秋から冬にかけて10度以上を保つのはとても難しいからです。また、冬は水を断つ必要があるため、雨や雪があたる環境では育つことができません。
寒さや水のやりすぎといった環境の変化によって、すぐに根腐れといったことが起こることが多いからです。日本で育てる場合は、冬の温度対策をしっかりする必要があります。最低でも10度以下にしないことが大切ですので、秋の落葉後に無事に冬を越せないと春に芽や葉が出てこずそのまま枯れてしまうことが多いです。できればビニールハウスや温室といった環境を整えておくことがとても大切です。
ビニールハウスや温室が用意できず、家の中で育てる場合はアローディアを育てておく部屋だけは部屋の温度に注意して、10度以下にしないように気をつけます。ビニールハウスや温室などを用意したあとは、室内の温度はできれば15度以上を保てる環境を整えられることが一番良いです。後は日光をたっぷり浴びられるように日陰などがない場所で育てるのが良いです。
種付けや水やり、肥料について
マダガスカル島南部はとても乾燥した地帯であり、雨季でもあまり雨の降らない地域になります。そのため、日本での栽培方法はそれに近い環境にするのが望ましいです。まず育て方として水をあげる場合ですが、春ごろになると芽や葉が出始めるので、徐々に水をあげる回数を増やしていきます。
いきなり大量の水をあげるのではなく、徐々に水の量や回数を増やしていくのが望ましいです。やがて成長期になる夏になるので、夏の時期になったらたっぷりと水をあげることが大切です。アローディアの成長は雨季の夏にしか大きく育ちません。日の当たる場所に置いて、毎日水をあげても問題なくぐんぐん育ちます。
やがて秋ごろにかけて気温が下がり始めたら、また水をあげる量や回数を減らしていきます。やがて葉が落ち始めるので、そのタイミングに水をあげることをやめます。断水期間となり、春の季節まで一切水をあげることはしません。冬に水をあげてしまうと根ぐされをおこず場合があるので注意が必要です。
次に肥料ですが、冬は温度だけ注意し肥料も水もまったく与える必要はありません。春になったら追肥をするのが良いです。夏は成長期なので肥料を与えるとぐんぐんと育ち、種類としては液体の肥料が良いです。与えるとすぐに効果が表れる緩効性肥料などはみずに薄めて与えると効果的です。
徐々に肥料の効果が表れるものとしては有機質肥料なども土に良く混ぜて与えるのも良いです。ただし、とても成長が早く育つ植物のため、夏に与えすぎると与えた分だけ成長するので与えすぎには注意が必要です。
増やし方や害虫について
アローディアの増やし方ですが、挿し木をすることで増やすことができます。挿し木を行う時期は成長期の夏にするのが良いです。成長している幹から剪定した挿し木を、栄養のある土の入った鉢に挿します。挿し木をする場合の切断した枝面が乾燥するまえに挿し木をするのが良いです。やがて根がでて通常のアローディアと同じように成長していきます。
日本での場合春などのまだ成長期に入る前での剪定による挿し木は、そのまま挿し木が成長せずに枯れてしまうことが多いので、時期としては成長期の夏にするのが良いです。しっかり根が出てきたのを確認したら夏の間は水をたっぷりあげ日に当てればぐんぐん成長します。
種からの場合は、まず植えるまえの種はガーゼなどで包んで皮を摂るように水でしっかり洗います。自然界の場合は鳥などが種を食べて、皮がとれた状態で糞として出され発芽するため、皮を洗って取る必要があります。次に栄養豊富な土の入った鉢に種をまきます。この時種の上に土をかけることはせず、土の上に種を置くだけです。
後は、風などで飛ばされないように鉢の上に割り箸をおいた後、ガラス板などをおいて日の当たる場所に置いておきます。水やりは春は霧吹きで数回程度。夏は霧吹きで多めに。秋と冬は断水と言う形で育ちます。害虫ですが強い植物なので殆ど問題ありませんが、夏の成長期にはカイガラムシには注意が必要です。カイガラムシ専用の殺虫剤などで対策するのが良いです。
アローディアの歴史
アローディアと呼ばれる植物は、マダガスカル原産の植物です。刺のある多肉植物になりますが、歴史はとても古く江戸時代にさかのぼります。年代でいうと1644年から1649年頃の徳川家光が将軍として江戸を納めていた時代、ポルトガルから持ち込まれたものが最初とされています。
その時の多肉植物として持ち込まれたのはウチワサボテンが最初でしたが、そこから徐々に色んな種類の多肉植物が持ち込まれるようになりました。持ち込まれた目的として、サボテンと同様にアローディアも観賞用としての用途が殆どとなります。ただし、サボテンと違ってアローディアはマダガスカル島の南部に自生しており、
乾燥した日の当たる場所で育つため高さが10メートルから15メートルもの高さに育つものが多いです。これほどの高さに成長したアローディアをみるためには、日本では植物園などでみることができます。一般家庭でも育てることは可能ですが、さすがに10メートル以上まで育てるのは温度や飼育環境を整えるのが大変なのでなかなか難しいです。
多肉植物に分類される植物は、生育型も大きく変化してきた植物です。今では大きくわけて3種類あり夏型種と春秋型種と冬型種になります。これらは生育する期間ごとにわけられており、アローディアは夏型種に分類されます。ただし、多肉植物の生育方に対する分け方は、人為的なものになるため自然に自生しているものを指し示すものではないです。
アローディアの特徴
一番の特徴としてはやはり、幹全体に覆うように生える鋭い刺になります。また、背が高く成長するのも特徴にあり、マダガスカル島で自然に自生知る場合は15メートルもの高さに成長します。その為、高いや丈のあるというラテン語からアローディアと名がつけられました。和名はその見た目から亜竜木という名前が有名になっています。
幹にはびっしりと触る場所がないほど刺が生えており、その刺の隙間の幹から直接卵型の葉が生えてくるのも特徴の1つです。幹はとても硬く、マダガスカル島では刺や葉を取り除いて幹の部分建築素材に使用されることもあります。また、秋になると葉が落ちて春になるとまた葉を茂らせる特徴があります。
自生しているマダガスカルでは乾期に葉が落ちて雨季になると葉を茂らせるサイクルで成長していきます。葉が繁っている夏の間だけ成長を続け、葉が落ちた後の秋から冬にかけてはただの刺の生えている棒のような状態となり、成長も止まります。マダガスカル島で自生している場合は、その環境にあった成長方法になっているため何もしなくても強く成長しますが、
日本など四季がある場合の成長は温度管理がとても重要になる植物です。幹全体に広がるとがった刺は、思った以上に鋭く少し洋服が触れただけでもすぐに引っかかるため、大きな鉢などで育ってている場合、そのまま服に引っかかり倒れてしまうという事も多くあるため、アローディアの側を通る時は注意することが大切です。
-

-
アイビーの育て方について
観葉植物にも色々な種類が有りますが、その中でもアイビーは非常に丈夫な上に育てやすいので初心者や、観葉植物の育て方が分から...
-

-
ゆりの育て方
ゆりは日本国であれば古代の時期から存在していました。有名な古事記には神武天皇がゆりを摘んでいた娘に一目惚れして妻にしたと...
-

-
メギの育て方
メギはメギ科メギ属の仲間に入るもので、垣根によく利用される背の低い植物です。メギ属はアルカロイドという成分を含んだ種類が...
-

-
サボテンの育て方のコツとは
生活の中に緑があるのは目に優しいですし、空気を綺麗にしてくれるので健康にも良いものなのです。空気清浄機のように電気代がか...
-

-
ライラックの育て方
ライラックの特徴としてあるのはモクセイ科ハシドイ属の花となります。北海道で見られる事が多いことでもわかるように耐寒性があ...
-

-
クロガネモチの育て方
クロガネモチの原産地は、日本の本州中部から沖縄、朝鮮半島南部、台湾、中国中南部、ベトナムなどです。もともと日本に自生して...
-

-
イチジクの育て方
イチジクのもともとの生息地はアラビア半島南部、メソポタミアと呼ばれたあたりです。文明発祥とともに身近な食物として6000...
-

-
ユリ(百合)の育て方
ユリに関しては、北半球のアジアを中心に広く分布しているとされています。亜熱帯から温帯、亜寒帯にかけても分布されている花に...
-

-
モモ(桃)の育て方
桃はよく庭などに園芸用やガーデニングとして植えられていたりしますし、商業用としても栽培されている植物ですので、とても馴染...
-

-
ブバルディアの育て方
ブバルディアは、学名「Bouvardia hybrida Bouvardia」、アカネ科ブバルディア属の半耐寒性の低木、...




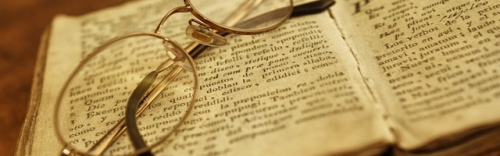





アローディアと呼ばれる植物は、マダガスカル原産の植物です。刺のある多肉植物になりますが、歴史はとても古く江戸時代にさかのぼります。年代でいうと1644年から1649年頃の徳川家光が将軍として江戸を納めていた時代、ポルトガルから持ち込まれたものが最初とされています。和名はその見た目から亜竜木という名前が有名になっています。