クチナシの育て方

クチナシの育て方
植えつけは4月から6月、または9月に行ないます。暑い時期や寒い時期は避けて暖かい時期に植え付けるようにしてください。また、クチナシは、あまり大きくなった株は根付きにくく、若い苗のほうが根付きやすい性質があります。
なので若い苗木から植えてあげるほうが生育がよいといえます。庭に植える場合、クチナシの土は水はけのよいものにしてあげることが大事です。植え方にも特徴があり、植え付けるときは水はけを第一に考えてあまり深く掘らず、山だかにして土を盛って植え付けるようにするのがポイントです。
また腐植質に富んだ、極端に乾燥しない土壌であれば、土質は選びません。鉢植えにする場合は、赤玉土(小粒)7で腐葉土3の割合で混ぜたものを使用します。粘土質の土ではうまく育たないため、腐葉土などを混ぜた水持ちがよく、軽い土にするのがおすすめです。
植えつけたら水をたっぷりとあげ、乾かさないように株元には敷きわらや腐葉土などを置いてあげてください。また鉢植えでは、根が大きく成長するので根づまりが起こりやすいです。そのため、4月から5月にかけて一回り大きな鉢へと植えかえることが必要です。
そのときにも古い土は3分の1ほど落とし、長い根は切り詰めます。水やりは乾燥に弱いので表面が乾いたらたっぷりとあげてください。夏場の場合はとくに水切れを起こしやすく、とくに注意が必要となります。
肥料は2月と8月に1回ずつ化成肥料と油かすを等量混ぜたものを株元に施します。鉢植えは、2ヶ月に1回くらい粒状の油かすを株元にあげますが、鉢植えの場合は冬にあげる必要はありません。
また樹形を考えての剪定はあまり必要がなく、成長するにともなって自然に整っていくので基本的にいりません。徒長枝が出た場合においては、枝の基部から切り除きます。
クチナシの日当たりと置き場所の管理
クチナシは、寒さに弱く南東南部以西の温暖な地域での栽培に適している植物です。関東北部から北陸から東北南部でも、冬に霜や寒風の対策をすれば、庭植えでも栽培可能となっています。
そのため寒さ対策が必要になり、寒い地域では冬は凍らない室内に取り込みます。また暖地であったとしても、乾燥した寒風が当たらない場所に移動させる工夫が必要です。もちろん冬にも日当たりといったことも必要になりますが、夏は反対に日陰に移動させてあげることが大事となる場合があります。
クチナシは寒さにも弱いのですが、乾燥にもとても弱い性質を持っています。夏場の直射日光が一日中当たるといった場所では、株元が乾き弱ってしまいます。そういった場所での栽培は向きません。
鉢植えの場合は移動できますが、地植えの場合は簡単ではありません。そういったことを考えて、夏場に一日中直射日光が当たらない場所、たとえば半日陰といった場所に地植えしてください。水やりも土が乾いていると感じたら、夏場は朝、夕としっかりとあげて管理してください。
クチナシの増やし方と病害虫
クチナシの増やし方は、主に挿し木と種まきで種付けして増やすことが可能です。一般的に成功率が高く、増やしやすいのがさし木とされています。クチナシの挿し木のやり方は、まず固くなった枝を5月から7月に10cmから15cmの長さで切り取ります。
このとき先端の葉を2、3枚残してあとは取り除きます。切り口を斜めに切り落としたら30分から1時間くらい水揚げしておきます。そのまま植えてもよいのですが、発根の成功率を高めるのにも「ルートン」という植物成長調整剤を付けてから土にさします。
このとき、薄く切り口につけるのがポイントです。そして土に斜めになるようにさします。土は赤玉土や鹿沼土でもいいですが、ホームセンターなどで売られているさし木専用の培養土を使うと簡単で便利です。
その後に、水をしっかりと与えて日陰で管理します。9月頃には根がでるのでその時は鉢あげしてください。種で育てる場合は、果実から種子をとり出し、春か秋にまきます。約40日ほどで発芽するので水をやるなどをして枯れないように管理してください。
種の場合は花をつけるのに2年ほどかかります。八重咲き品種では果実ができないため、種の場合は一重咲きとなるようです。育成するにあたって気になるのが病害虫です。オオスカシバの幼虫というのが葉をよく食べます。被害が大きくなるようでしたら、殺虫剤などの駆除が必要になります。
オオスカシバは、青虫のような見た目をしており、おしりにツノのようなものが生えています。ほかにも新芽などにアブラムシが付くことがあり、また甘い香りがすることからアリなども寄ってきやすいなどがあります。
またクチナシの木に限らず、枝にはカイガラムシが付くこともあるので、見つけたら竹べらやハブラシなどを使ってこそぎ落としてください。病気でいえば、褐色円星病、さび病、裏黒点円星病、すす病などがあり、風通しが悪いことでかかってしまう病気なので剪定などして対策をとってください。
クチナシの歴史
クチナシの原産地は日本、中国、台湾、インドシナ、ヒマラヤとされており、暖地の山中に自生し、広く分布しています。主な生息地は、主に暖帯や亜熱帯地域とされているなど暖かい気候を好みます。クチナシの名前の由来は多くあり、果実が熟しても裂けたりはじけたりしないので、口が無い「口無」など、とてもおもしろいです。
別名をGardenia(ガーデニア)として、日本ではクチナシ、漢字では「梔子」と書きます。また「くちなし」の名前から「朽ち無し」は朽ちることがないという意味で、縁起物として結婚祝い、結婚記念日、開店や開業祝いに贈るひともいます。
18世紀にヨーロッパに入ると、かぐわしい芳香がうけて、恋人に贈るようになったともいわれ、世界中で利用されとても人気です。クチナシの仲間には約250種があり、主に旧世界の熱帯に分布していますが、日本では静岡県以西の地域で栽培されており、八重咲き品種が多いです。
日本での歴史も古く、天平時代から布や土木製品を黄色く染めるのに使われてきたそうです。また昔から日本でも森林や山などによくあるものとして親しみのある花としています。
クチナシの特徴
クチナシは、初夏に涼しげな白い花を咲かせる甘い香りが特徴の花木です。春のジンチョウゲ、秋のキンモクセイとともに、香りを楽しむ花木としても有名です。主な色は白色ですが、このクチナシの白さに勝る花がいないとされるほど、白さに定評がありとても魅力があります。
花びらは厚みがあり美しいのですが、すぐに黄色くなってしまうのが残念とされるところです。ですが、黄色くなっても甘い香りは続くなどの特徴があり、たくさんの魅力を持った花として愛されています。
本来は6枚の花びらの一重咲きなのですが、バラのように咲く八重咲きもポプュラーなものとして多くのひとに知られています。クチナシにも多くの品種が存在し、ヤエクチナシ、コクチナシ、オオヤエクチナシ、マルバクチナシなど様々なものがあります。
ほかにも、花や実を活用することができるものとしてよく知られています。花びらは主に食用として使われることが多く、茹でてサラダや酢ものにしたり、生の花びらを紅茶に浮かべるなどした楽しみ方ができます。
実は主に食品の着色料や布地の黄色染料に使います。たとえば、たくわんや栗きんとんの黄色い色はクチナシの実の色だといわれています。そのほかにも、漢方薬にも使われるなど幅広い使い道があります。
八重咲きは雄しべが花弁に変化しているため、結実しません。なので、実を付けさせたいのなら一重品種がよいです。クチナシは、見た目にも美しい純白の花や魅きつけられる甘い香り、花や実の利便性などたくさんの魅力にあふれた花です。こういったものを毎年咲くものとして、庭木として楽しむのもおすすめです。
花の育て方など庭木の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も参考になります♪
タイトル:アジサイの育て方
タイトル:ハギの育て方
タイトル:キンモクセイの育て方
-

-
タツタソウの育て方
タツタソウ(竜田草)は別名イトマキグサや、イトマキソウ(糸巻草)と呼ばれているメギ科タツタソウ属の植物です。花色は藤紫色...
-

-
スズメノエンドウの育て方
生息地は日本となっていますが、マメ科のソラマメ属に分類しています。後援などに雑草のようにその姿が見られ、古くから周りの草...
-

-
ハナトラノオの育て方
ハナトラノオは北アメリカ東部を原産地とする植物であり40センチから1メートル程度の大きさに育つ多年草の草花です。かわいら...
-

-
人参の育て方
原産地はアフガニスタンで、ヒンズークシーという山のふもとで栽培されたのが始まりだといわれています。古代ギリシャでは薬用と...
-

-
シラサギカヤツリの育て方
シラサギカヤツリはカヤツリグサ科の多年草です。シラサギの名前からもわかるように、花を咲かせた姿が白鷺が舞っているようにも...
-

-
シラネアオイの育て方
シラネアオイの原産地は、日本で日本固有の壱属一種の多年草の植物ですが、分類上の位置が二転三転してきた植物でもあります。昔...
-

-
セイロンベンケイの育て方
セイロンベンケイというのは、ベンケイソウ科リュウキュウベンケイ属の植物で別名トウロウソウと呼ばれることがあります。ベンケ...
-

-
クサノオウの育て方
クサノオウは古くから日本に生息している山野草です。聞き慣れない植物ですが、黄色い花を咲かせるヤマブキソウに似ています。ク...
-

-
ネズミモチ(プリベット)の育て方
ネズミモチ(鼠黐・Ligustrum japonicum)は、モクセイ科イボタノキ属の樹木です。 生長すると樹高が4~7...
-

-
レーマンニアの育て方
観賞用として栽培されているエラータは葉っぱの形が楕円のような形をしていて、5月ぐらいか暑いシーズンになると、花茎が長い花...




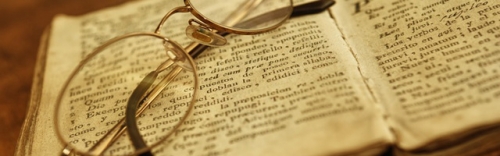





クチナシの原産地は日本、中国、台湾、インドシナ、ヒマラヤとされており、暖地の山中に自生し、広く分布しています。主な生息地は、主に暖帯や亜熱帯地域とされているなど暖かい気候を好みます。クチナシの名前の由来は多くあり、果実が熟しても裂けたりはじけたりしないので、口が無い「口無」など、とてもおもしろいです。