カナメモチの育て方

カナメモチの育て方
カナメモチは日当たりの良い場所に植えてあげるのが向いています。明るい日陰でも良いのですが、注意しなければいけないのは日照時間が十分に得られるかということです。新葉の赤い色はある程度日光にあたらないと色づきません。また日陰ですと枝がまばらにしか伸びず、生垣にした場合は見栄えもあまり良くありませんので避けたほうが良いでしょう。
北海道などでは寒すぎて育たない可能性が高いですので、育てるのに適しているのは東北南部から西にかけての地域です。植え付けは3月から4月もしくは9月中旬頃から10月にかけてが良いです。カナメモチの根は粗い上に細かい根があまり出ません。そのため、一度植えつけてしまうと次に植え替えしようとするのが難しいので植える場所には注意しましょう。
土は乾燥ぎみなところは向いていませんので、腐葉土や堆肥をしっかりと混ぜて土作りをしてから植えつけるようにします。土質はあまり選びませんが、どちらかというと粘土質なタイプの土のほうがよく育ちます。
水やりに関しては庭植えにした場合は夏の高温の時を除いて特に水を与える必要はなく、雨が降った時にあたる程度で大丈夫です。肥料は2月から3月に油粕や化成肥料などを株元に置いておくと良いです。ただし肥料で窒素分が多いと新葉の色に影響するので注意します。
栽培する上でのポイントを知ろう
カナメモチは生垣などにすることが多いので、刈り込みをしてあげる必要があります。刈り込みをしないと枝が茂り過ぎて大変なことになります。刈り込みは初夏と秋頃がベストタイミングです。初夏になると春はまだ赤かった葉も緑色に変化しています。時期的には5月下旬から6月中旬頃になります。
秋は9月中旬頃に刈り込みを行なうことで10月半ばには新芽が出てくるので冬の間も春ほどではないにしても赤い葉を楽しむことができるようになります。ただしこれは非常にタイミングが難しくて少し遅れると葉が丈夫になる前に寒い冬が来てしまい、せっかく出た新芽が枯れてしまうことがありますので注意しなければいけません。
刈り込みをする時は太い枝を思い切りカットしてしまうと枝枯れを起こしてしまうので、基本の刈り込み以外にもひんぱんに軽い刈り込みはしておいたほうがいいです。もし刈り込み時に折れてしまった枝や枯れた枝を見つけた場合は垣根に穴が開いてしまうことになります。
まずはその枯れてしまっている枝をカットし、その上下にある枝の内側にある枝を先端から3分の1切ります。そして枯れ枝側に伸びている枝のみをそのまま残して、枯れ枝の上下にある枝をヒモなどで結んでおきます。しばらくすると枝が成長して穴がちゃんと埋まります。
刈り込みをする時にはある程度好みの形に整えることができますので挑戦してみるのも楽しいです。病気は根頭がん種という細菌による病気に注意が必要です。これは株元にコブができて栄養がとられ、生育が阻害されるのでひどい場合には枯れてしまうというものです。また害虫にはアブラムシやハマキムシ、テッポウムシなどが発生する恐れがありますので薬剤で退治してしまいましょう。
種付けして増やせるのか?
カナメモチは基本的には挿し木で増やしていきます。7月から8月頃が良い時期で、当年伸びた若い枝を15cmほどにカットして赤玉土や鹿沼土に挿しこんでおきます。その時、葉は先端から2、3枚だけ残してあとの下のほうの葉は全て取り除いてしまいます。土に挿す前に30分から40分ほど水揚げして切り口に植物成長調整剤をまぶしておくとより良いです。
水をたっぷりと与えたら日陰で管理しておきます。9月頃になれば発根しますから鉢上げしてあげると良いでしょう。花が咲いた後にできる実には種もできますが、ほとんどの場合、花粉が未成熟なので実があまりならないことも多いです。ですからこぼれ落ちてしまった種でどんどん増えていってしまうということはあまり心配しなくても大丈夫です。
しかし枝はよく茂るのですからそこは枝枯れしてしまわないようにきちんと管理しなくてはいけません。現在広く利用されているのはレッドロビンという品種のもので、これはよく生垣にも使われているので見たことがある方もいるでしょう。カナメモチと近縁種のオオカナメモチをかけあわせたのがフレイゼリ種といい、この種もカナメモチとして出回っています。
園芸品種としてはロブスタやバーミングハム、レッドロビンなどが知られています。レッドロビンは一般的なカナメモチに比べると葉が大きめで枝の茂り方も少し粗いのですが、オオカナメモチの丈夫さを引き継いでいて枝もよく伸びますし、新葉の赤色はとても濃いので見ごたえがあります。オオカナメモチは25年ほど前にニュージーランドで作出されたものです。一般的なカナメモチの赤色は茶色がかった赤色をしていますので、見て比べてみるとすぐにわかります。
カナメモチの歴史
カナメモチの原産は日本や中国などで、国内の生息地は伊豆半島より西側、四国や九州など比較的暖かい地域に分布しています。カナメモチという名前がつけられた由来はこの木で扇の要を作ったからだといわれています。芽の赤いモチノキという意味があるアカメモチが訛ってカナメモチになったという伝説があります。
しかし実際にはモチノキはモチノキ科ですし、カナメモチはバラ科なので全く別のものです。日本に自生しているということでかなり歴史は古く、古事記には多知曾婆、枕草子にはたちそばの木という言葉が記録されていて、これは立っているソバノキという意味があります。つまり蕎麦の木のことです。
カナメモチの木はその花が白く密になって咲くところが蕎麦の花ととても似ているという点からそう呼ばれていたのではないかと考えられます。また属名はフォテイニアといいますが、これはギリシア語の輝くという意味があるフォテイノスという言葉が由来となっているといいます。
カナメモチの木の葉は光沢があって革質、そして厚めで長い楕円形をしているのが特徴だからです。比較的育てやすいのがこのカナメモチで、生垣などによく使われているのを見かけます。
カナメモチの特徴
カナメモチは樹高が4mから5mほど、5月から6月頃に開花を迎え、白くて小さな花がまとまった状態で咲きます。初夏と秋頃に剪定をすることで赤い美しい新葉をより長く楽しむことができるようになります。赤くなるのは新葉だけで、この赤色はアントシアニンの色です。
これは新葉にしか起きないもので、葉が開いてくると赤色だった葉は緑色へと変わってしまいます。新葉が赤くなるのは新芽の頃はまだ弱く、強い陽射しにあたってしまうと傷んでしまうのでそうならないようにアントシアニンがサングラスのような役目をして強い陽射しから新芽を守っているといわれています。新葉の中でも特に赤いものはベニカナメと呼ばれています。
新葉の色が赤すぎると感じられることも少なくないベニカナメは伝統的な庭造りの中では浮いてしまいがちで西日本ではあまり普及しませんでしたが、関東へ持ち込まれるようになってからは庭に植える樹木としてはとても人気が出て普及しました。開花の後は小さくて丸い果実がなり、秋頃になって赤く熟します。カナメモチは冬の耐寒性はあまりありませんので、冬の寒さに対しては何かしらの対策をしてあげたほうが良いです。
庭木の育て方や色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も参考になります♪
タイトル:イヌツゲの育て方
タイトル:モチノキの育て方
-

-
カラタチバナの育て方
カラタチバナの原産地は日本、台湾、中国です。日本では本州、四国、九州、沖縄などを主な生息地としています。日本では江戸時代...
-

-
フクジュソウの育て方
雪に覆われたり、冬の間は殺風景な庭に、どんな花よりも早く顔を出して春の訪れを知らせてくれる、それがフクジュソウです。フク...
-

-
ペンステモンの育て方
ペンステモンが文献に初めて登場したのは1748年のことでした。その文献を書いたのはジョン・ミッチェル氏でした。その当時の...
-

-
ヒイラギナンテンの育て方
ヒイラギナンテンの原産地は中国や台湾で、東アジアや東南アジアを主な生息地としています。北アメリカや中央アメリカに自生する...
-

-
木立ち性シネラリアの育て方
木立ち性シネラリア(木立ち性セネシオ)は、キク科のペリカリス属(セネシオ属)の一年草です。シネラリアという語呂がよくない...
-

-
白菜の育て方
白菜は、アブラナ科の野菜で、生息地は他のアブラナ科の野菜類と同様に、ヨーロッパの北東部からトルコ にかけての地域でだと考...
-

-
ビヨウヤナギの育て方
ビヨウヤナギの生息地は中国ですが、仲間であるヒペリカム・オトギリソウ属には日本原産種もあります。薬草として用いられるオト...
-

-
ブルーファンフラワーの育て方
ブルーファンフラワーはクサトベラ科スカエボラ属で、別名はファンフラワーやスカエボラ、和名は末広草といいます。末広草と名付...
-

-
トリトニアの育て方
トリトニアはアヤメ科トリトニア属の多年草になり、南アフリカ原産の植物です。トリトニアには40種から50種ほどのさまざまな...
-

-
ビタミンCの豊富な夏野菜ピーマンの育て方
次々と実を付け霜の降りる頃まで長く楽しめるピーマンの育て方を紹介します。ピーマンは放置しててもそれなりに収穫できるのです...




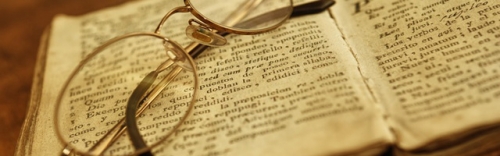





カナメモチの原産は日本や中国などで、国内の生息地は伊豆半島より西側、四国や九州など比較的暖かい地域に分布しています。カナメモチという名前がつけられた由来はこの木で扇の要を作ったからだといわれています。芽の赤いモチノキという意味があるアカメモチが訛ってカナメモチになったという伝説があります。