フイリゲットウ(Alpinia sanderae)の育て方

フイリゲットウの育て方を覚えよう
フイリゲットウは5月下旬頃から7月頃の間に植え付けするようにします。この頃になれば気温も十分に上がっていますので根付くまでも比較的安心です。土は水はけが良く、かつ水持ちが良いものを使うのがベストです。
肥料は用土に粒状のものを適量混ぜ込んでおきます。また春から秋頃までの生育期には2、3か月に1度同じく粒状の肥料を与えておきます。また2週間に1度くらいでいいのですが、液体肥料も与えるようにします。これは水をあげる代わりにします。
基本的な水やりは土の表面が乾いたらたっぷりと与えるようにしますが、この時のポイントとして株全体に水がかかるように与えるようにすると元気に育ってくれます。真夏の高温期は乾きやすいですから水切れしないように気をつけてあげることが大切です。
室内で置く場合はエアコンの風があたらないような場所に置くことも重要です。エアコンの風は乾燥していますので良くありません。エアコンを使っている時期はこまめに霧吹きを使って葉水を与えるようにするといいです。時々で良いのですが、株全体に水をかけてあげることで葉の表面がきれいになります。
室内置きですと特に葉の表面にいつのまにかホコリがついてしまっていることが多いので、たまに見てとってあげるようにするといいでしょう。葉のほこり対策には専用の葉面洗浄剤も販売されてますので、それを使ってきれいにしてあげるのもいいです。高さは3mほどにまで育ちます。
フイリゲットウの栽培の上での注意
とにかく寒さ対策と直射光線を避けることが非常に重要です。また一度花がついた茎は少しずつ枯れてくるようになるので枯れた葉も目立つようになってきます。この場合は株元から枝をカットしてしまうことで新しい芽が出てくるのでまた花を咲かせるようになります。
株が少し大きくなり過ぎてしまったと感じた場合は植え替えをしてあげましょう。植え替えの時には鉢根を崩さないようにして一回り大きな鉢に植えてあげるのが良いです。もし新しい鉢に入れても大きすぎると感じた場合は株分けをしておくといいでしょう。
また害虫はハダニ以外ではカイガラムシがつきやすいので、時々ついていないかチェックしておくといいです。カイガラムシは季節問わず発生します。植物の汁を吸ってひどい時には枯らしてしまいますので見つけ次第すぐに退治します。
大人になったカイガラムシには薬剤はあまり効かないことが多いので、そういう場合は少し手間はかかりますが、幹などからこそげ落としてしまいます。カイガラムシの排泄物は成育不良の原因になりやすいですし、すす病にもかかりやすくなってしまいます。
すす病は植物の葉などの表面がすすがついてしまったように黒い粉のようなもので覆われてしまう病気です。これは黒いカビのようなものです。もし、すす病になってしまっている場合はえさとなる害虫をまず駆除することが大切です。
種付けで増やせるのか?
フイリゲットウは基本的には株分けをして増やしていきます。時期は植え替えをする時に行いますので5月下旬から7月頃にかけてになります。まずは鉢から株を取り出し、軽く土を落としてしまいます。そしてよく切れるカッターナイフなどを使って株を3つほどにわけます。
これはその株の大きさによって分け方を決めるのが良いでしょう。もし根詰まりを起こしてしまっているようならばスコップなどを使って根鉢を切り分けるときれいにできます。根鉢の下を3分の1ほどカットしてしまいます。
そして根をほぐして古い土を軽く落とし、下のほうの葉が落ちてしまっているような枝は株元で切っておきます。新しく用意した観葉植物用の培養土などを鉢に入れてそこに株分けした株を植えます。水はけを良くするためには大きめの赤玉土を入れておくと改善されます。
またどうしても種から育ててみたいという方は開花後に花茎をカットせずに残しておき、実をつけさせるといいでしょう。この実の中に種ができます。通常は放っておくと実が熟して底のほうがパカッと割れ、自然と種が落ちて新しく芽が出てきます。
ただ全ての実を残しておくとたくさん増えてしまう可能性も出てくるので、必要な分以外は開花後に花茎をカットしておくのが良いです。ただし基本的にフイリゲットウは花が咲きにくいので、種付けされること自体が非常に難しいと考えておいたほうがいいです。
フイリゲットウの花言葉は爽やかな愛というものです。フイリゲットウは夏の時期に涼しげな姿を見せてくれますから、そこからこの爽やかなという花言葉が生まれたようです。ちなみに他のゲットウなどの花言葉はどうなのかといいますと、実はこちらも爽やかな愛となっています。フイリゲットウはその葉の美しさから切花としてもよく使われます。他の花と組み合わせてもいいですし、一輪挿しに入れて飾っても見栄えします。
フイリゲットウの歴史
ニューギニアが原産や生息地です。フイリゲットウとはフイリとは斑入りという意味ですが、ゲットウという名前がついていてもゲットウの種とは違います。ショウガ科でゲットウ属です。別名はアルピニアといいます。アルピニアという名前はイタリアの植物学者であるP・アルピーニ氏が由来となっています。
シロフイリゲットウは昭和20年代に奄美大島で発見されており、濃緑の葉に白色の斜め線の模様が等間隔に入るというものです。根茎には芳香があります。沖縄や九州南部では庭木として植えられています。学名はアルピニア・サンデラエといいますが、このsanderaeはイギリスの園芸業者であるF・サンダー氏にちなんでいます。
似たような仲間にキフゲットウというのがあります。キフゲットウは寒さにも比較的強いですし、白い花を咲かせた後に赤い実をつけます。しかしフイリゲットウは寒さにはどちらかというと弱いですし、緑色の花をつけますのでそこですでに違いがあります。
普通のゲットウは昔から精油が搾取され、防虫剤や防カビ剤、抗菌剤などにも使われています。同じゲットウという名前がついていてもフイリゲットウの場合は精油を使うということはありません。
フイリゲットウの特徴
フイリゲットウは常緑多年草で、ニューギニアが原産です。葉脈に沿って乳白色の斑が入っているのが特徴で、キフゲットウと共に観葉植物としてとても人気があります。ゲットウに斑が入った植物だと勘違いをされやすいのですが、全く別物です。
ゲットウはマイナス3度ほどまで耐えることができますが、フイリゲットウは寒さには弱く、10度ほどなければ越冬することはできません。冬場に外に出しっぱなしにしておくと暖地以外では枯れてしまいます。
しかし室内で育てていても風通しが悪いとハダニが発生しやすくなりますので、そこは注意が必要です。ハダニの防止のためにはこまめに表裏に葉水をしておいたり、窓を開けるなどして風通しを良くしておくのが良いです。やや明るめの光を好みますから、鉢植えを室内のレースのカーテン越しの窓辺、遮光してある戸外などに置いておくといいです。
冬場は夜になると窓際がとくに温度が低くなって冷え込みますのでフイリゲットウをそのまま置いておくと、気がついた時には寒さで枯れているということも有り得ますから夜になったら室内の中央付近に移動させるなどして寒さ対策をしてあげるといいです。
観葉植物の育て方や色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も参考になります♪
タイトル:モンステラの育て方
タイトル:ポトスの育て方
タイトル:ムクゲの育て方
-

-
アナカンプセロス、アボニアの育て方
種類としてはスベリヒユ科になります。多肉植物で、多年草となります。高さとしては3センチから10センチぐらいですから土から...
-

-
一重咲きストック(アラセイトウ)の育て方
一重咲きストック、アラセイトウはアブラナ科の植物です。原産地は南ヨーロッパで、草丈は20センチから80センチくらいです。...
-

-
エマルギナダ(ヒムネまたはベニゴウカン)の育て方
この花についてはマメ科、カリアンドラ属となっています。和名においてネムが入っていますが、基本的にはネムは全く関係ありませ...
-

-
ウォーターマッシュルームの育て方
ウォーターマッシュルームは本来ウチワゼニクサという名前になります。生息地は湿地や河川などの水の多い場所で育つ特徴がありま...
-

-
コンボルブルスの育て方
コンボルブルスは地中海の沿岸を中心とした地域で200種くらいが自生しているとされていて、品種によって一年草や多年草、低木...
-

-
いろんなものを栽培する喜び。
趣味としてのガーデニングについては本当に多くの人が注目している分野です。長年仕事をしてきて、退職の時期を迎えると、多くの...
-

-
根茎性ベゴニアの育て方
ベゴニアはシュウカイドウ科シュウカイドウ属の植物です。ベゴニアには他種を交配して作られた様々な品種がありますが、それらを...
-

-
タイムの育て方について
タイムはインド、北アフリカ、アジアを原産とするシソ科のハーブで、たくさんの品種があります。主に料理用に使われるコモンタイ...
-

-
睡蓮(スイレン)の育て方
睡蓮の魅力と言えば、なんと言ってもその美しい花、そして風情のある水面に浮く沢山の葉にあります。元々は東南アジアなどの熱帯...
-

-
シャガの育て方
シャガは中国から古代に渡ってきた植物ですが、学名を日本語訳すると日本の虹と言い、とてもロマンチックな名前です。原産国の中...




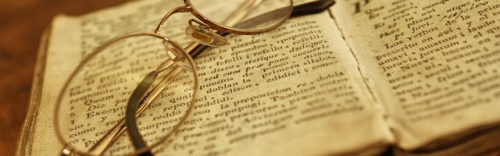





ニューギニアが原産や生息地です。フイリゲットウとはフイリとは斑入りという意味ですが、ゲットウという名前がついていてもゲットウの種とは違います。ショウガ科でゲットウ属です。別名はアルピニアといいます。アルピニアという名前はイタリアの植物学者であるP・アルピーニ氏が由来となっています。