キノコ類の育て方

育てる環境について
きのこ類における生息地としては、日差しの強いところなどにはあまり見ることはできません。山の中の木などにくっつきながら成長していきます。ですから非常に暗い、ジメジメしたところで育つことになります。木に関しては、立っている木に付くこともありますが、それ以外には倒れて腐っている木につくこともあります。
その他土の中から土の中から直接生えてくるようなタイプもあります。アジアから、朝鮮、中国、日本が原産になっているので、この地域の全般において森などがあれば見かけることが出来るかもしれません。育て方の環境としては木が重要になってきます。栽培の時においては必ず原木を用意すると言われます。これは切ってきた木で十分です。
最適な木としてはクヌキ、コナラ類がよく、適する原木としてミズナラ、アベマキ、カシ類、クリなどが良いとされています。それらの木を原木として用意できるところが良い所とされます。木の大きさに関しては特にこだわりませんが、ある程度は気にする必要があるようです。あまり大きすぎる場合には栽培することができなくなることがあります。
きちんと栽培をしようと考えるのであれば整えておく必要があります。農家のように本格的に行わないとしても、最低限これくらいの準備はしておいたほうがいいとすることがあります。自宅において環境を作るときにはホームセンター等で原木を用意した上で行うようにします。比較的簡単に作ることはできます。
種付けや水やり、肥料について
きのこ類については、菌の接種をする必要があります。何時頃に行うかですが、秋の11月頃から5月上旬ごろまでに原木に菌を植え付けるようにします。どのように接種を行っていくかですが、きりで穴を空けます。原木の状態などによって穴の数などは異なります。また穴の直径などもそれぞれ変えるようにします。
木材といいますと角材のように感じる人もいますが、通常の原木は円柱形になっています。その円柱に対して等間隔できりを用いて穴を開けます。この穴の中に種駒を入れていきます。これは金槌などを使うといいでしょう。穴をふさぐようにしていきます。この種駒に菌がついていて、将来的にはここからきのこが生えてくることになります。
水やりなどは必要なのでしょうか。きのこといいますと自然の状態においては雨が降ったり自然の状態があったりすることがあります。育てようとするときには雨が必要なので、雨の当たる場所に並べるようにすることが必要になります。湿度を保つようにすることが必要で、きのこの菌を活着させる必要があります。
この過程においては植菌の初期管理になります。特に肥料に関しては必要ないですが、水分が少ないと感じられる場合においては適度に水分を与えるようにします。じょうろなどで与えるよりも霧吹きなどで優しく与えるようにした方がいいかもしれません。水分があれば湿度もそれなりに保持することが出来るようになります。できるだけ一定に保ちます。
増やし方や害虫について
原木を伏込する作業が必要になります。排水がよく、風通し、雨通しの良い場所を選ぶようにします。日差しに関しては適度に当てる程度です。朝日が当たる分には問題ありませんが、西日が当たるようなところは避けるようにします。場所として適さないところとしては軒下などがあります。きのこだからとジメジメしたところを選びそうになりますが、
あまりジメジメしすぎているところは良い所ではありません。増やそうとする場合においても逆効果になることがあります。菌がきちんとついた場合においてはその後は発生するのを待つだけになります。繁殖する期間としては1年から1年半になりますから、それをめどに管理を行います。木に関しては大きなタイプであれば5年から6年近く採取することが出来るようになります。
害虫が発生した時にはどのように対応するかがあります。菌床などに発生しやすいものとしてはハエなどがあります。これらについては特定のハエを除去することが出来る薬などを利用することがあります。網などを利用してつかないようにすることができれば良さそうですが、そうすると日差しであったり水分がしっかりつかなくなることがあります。
しかし、薬を使うのに抵抗を持つこともあるでしょう。薬に関しては化学的な材料を使ったものもあれば自然な材料を用いることも出来るようになっているので、その時に応じて利用するようにします。多い場合は化学的なものの利用が必要です。
キノコ類の歴史
栄養のある食品としては自然の食べ物があります。野菜類などは栄養があるとされます。生で食べることが出来るものもあれば加熱をしないと食べられないものもあるので十分注意しなければいけません。野菜類とは少し区別されるかもしれませんが、八百屋さんなどで比較的見ることが出来るものとしてキノコ類があります。
こちらは植物の中でも菌類と言われるタイプで区別されることがあります。その中でも最も馴染みのあるのがシイタケかもしれません。多くの料理に使うことができ栽培もされています。原産としてはアジアから日本において広く分布していたとされています。日本においても古くから採取されて食べられていた記録があります。
しかし栽培に関しては難しかったようで、自生しているものを採取することとして食べることになります。これは現在においてはマツタケにも言えることでしょう。マツタケに関しては今でもまだ栽培をすることができず自生するものしか流通していません。ですから非常に高くなっています。
栽培に成功することができたキノコ関係については一気に流通するときの価格が下がっていますから、庶民にとっては買いやすく、そして食べやすい食品になっています。菌を培養することによって栽培をすることが出来るのでしょうが、同じ環境を作り出したりするのに苦労している状態です。栽培をするにおいては一定の歴史があり、技術を持っている会社などによって今は行われています。
キノコ類の特徴
きのこ類の特徴として、シイタケに関してはハラタケ目、キシメジ科、ハラタケ科と呼ばれる種類に属します。それぞれのキノコについては何らかの種類に属するようになっています。ただキノコを栽培しても仕方がありませんから、栽培して得なものになります。その中でシイタケは王様と言っても良いかもしれません。
最も特徴がありますが、世界においては決して広まっていないところもあります。英語においてはそのままシイタケとして表現されています。日本での表現のまま使われているので、元々は存在しなかったきのこになります。自然界においてはクヌギやシイ、コナラなどの木に発生するとして知られています。適温としては10度から25度となっています。
あまり寒すぎる環境も良くないですし、暑すぎる環境も良くないとされています。色の特徴としては傘の部分は茶色っぽい色をしています。木の色が茶色っぽいのでその色と非常によく似た色をしているといえるかもしれません。傘の裏の部分や軸に関しては白っぽい色をしています。傘の表部分、軸の部分などは特に特機なども無くすべすべしています。
硬さとしては適度な柔らかさがあります。似ているものとしてはマツタケなどもよく似た形を指さします。エリンギもキノコを大きくした形です。一方でしめじなどになるとかなり大きさが小さくなるタイプになります。えのき茸に関しては大きさよりも一つ一つが非常に細い状態で生えてくるのが特徴になります。
-

-
ウラムラサキの育て方
ウラムラサキの歴史に関しては、ミャンマーやタイが原産地となっています。現在でもこれらの地域が生息地となっています。ミャン...
-

-
ヨウシュコバンノキの育て方
日光を浴びる事で、成長を促進させないと、葉っぱの白い斑が消えてしまう事があります。白い斑は新芽の間の事なので、しっかりと...
-

-
センニンソウの育て方
センニンソウの特徴は、扁桃腺治療などに用いられる薬草としての役割も多いのですが、仙人の由来ともなった、仙人のヒゲのような...
-

-
ドイツアザミの育て方
この花はキク科アザミ属に属します。ドイツとありますが日本原産です。生息地も日本となるでしょう。多年草で、耐寒性があり耐暑...
-

-
オクラの育て方について
夏になれば栄養満点のオクラの栽培方法のコツです。オクラは北海道など一部の地域を除きかなり育てやすい野菜の一つです。スーパ...
-

-
宿根アスターの育て方
アスターは、キク科の中でも約500種類の品種を有する大きな属です。宿根アスター属は、中国北部の冷涼な乾燥地帯を生息地とす...
-

-
モミジバアサガオの育て方
モミジバアサガオは和名をモミジヒルガオといい、日本で古くから親しまれてきたアサガオの仲間です。日本へ伝来したのは今から1...
-

-
ヒメジョオンの育て方
ヒメジョオンは、北アメリカが原産の植物で、明治維新で日本が揺れているころに、入ってきて、以来日本中に広がり、色んな家の庭...
-

-
ユスラウメの育て方
ユスラウメの特徴としては真っ赤な赤い実をつけることです。見た目はさくらんぼにそっくりです。漢字で充てられるのは梅桃、山桜...
-

-
リクニス・ビスカリアの育て方
リクニス・ビスカリアの歴史はそれほど解明されていません。実際語源はどこから来ているのかははっきりしていませんが、属名のリ...




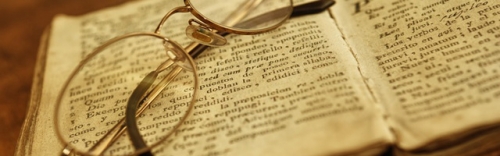





きのこ類の特徴として、シイタケに関してはハラタケ目、キシメジ科、ハラタケ科と呼ばれる種類に属します。それぞれのキノコについては何らかの種類に属するようになっています。ただキノコを栽培しても仕方がありませんから、栽培して得なものになります。その中でシイタケは王様と言っても良いかもしれません。