ツリガネニンジン、シャジンの仲間の育て方

育てる環境について
砂地や山野に自生するシャジンの仲間であるツリガネニンジンは、高山型であるのも特徴であり、育て方としては漢方薬のシャジンの仲間にあたるだけあり、丈夫で露地栽培も行いやすい多年草植物です。生育環境としては日向または半日陰が最適であり、花期となる8月から10月は木漏れ日の当たる場所へ移動させて管理することで長期間花の観賞を楽しむことが可能です。
さらに食用として利用できる新葉を収穫する3月からの春時期には、葉がしおれないためにも涼しく日当たりの良い環境が適しており、できるだけ西日や直射日光は避けた場所で管理します。生息地は山野ですが、直射日光や炎天下の気温には弱いため、7月から9月の夏時期の戸外では約50%の遮光が必要であり、遮光シートなどを利用して環境を整えます。
シャジンの仲間は夏時期には下葉から枯れてしまいやすく、その原因の多くは暑さ負けをはじめ、水不足・肥料不足・強光・通風不良が考えられます。高山型であるため、暖地においては遮光対策は必須となる他、水不足に陥らないための土壌環境としては保水性の高い土壌を選ぶことも必要です。シャジンの仲間であるため寒さには強いのが特徴であり、
雪の下は極端に気温が下がっておらず、低温の中で一定期間を越すことによって発芽を促進させることに繋がるため、戸外栽培が比較的ラクにできる多年草植物でもあります。寒波が押し寄せる地帯においては、支柱を立てることや雪避けまた霜避けなどを行うことが生育を良くする手であり、氷点下となる環境下においては軒下などに移動させて管理する方法が適しています。
種付けや水やり、肥料について
シャジンの仲間であるツリガネニンジンは、タネから育てることもできる他、ビギナー向けには苗も提供されています。タネが入っている実は早めに摘み取ることが重要で、茶色に変色した段階で摘み取り、乾燥させた後に揉んでタネを取り出しますが、実が変色したまま放置することで種子が自然と溢れ落ちてしまい、
種付けができなくなるために早い段階で摘み取るのが最適です。使用する用土としては、山野草専用となる園芸用のものを利用する他、硬質鹿沼土に軽石砂を一対一の割合で混ぜ合わせた土に植えるのも適しており、植え替え時期には生育が旺盛であるため1月から4月、または10月から12月などが適期で、特に早春に行うと根付きが良くなります。
種蒔き後は日陰管理で発芽した後、仮植えして定植させます。鉢植えでは駄温鉢が適しており、根の大きさに合わせて鉢も大きくしていきます。葉が枯れる原因となる肥料不足に陥らせないためにも堆肥また腐葉土を加えた用土で育て、肥料は株が成長する時期をはじめ、花が咲き終わった後に緩効性化成肥料をはじめ、
土壌によっては油カスや骨粉などを与えることで翌年の花付きなどを促すことが可能です。暖地においては固形肥料では根腐れしやすいため、液体肥料に変えるのも適しています。水やりは、鉢植えの場合には鉢土の表面が乾いてからたっぷりと与えますが、暖地では初夏からの水切れや乾燥を防ぐ目的で表土に水苔を張ることも育て方の基本です。
増やし方や害虫について
シャジンの仲間であるツリガネニンジンは増やし方も様々に提案されており、実生は取播き、または根茎を切り分ける株分け、さらに茎挿しからの挿し芽で増やす方法があり、それぞれに生育の難易度が異なる特徴も持ち合わせています。例えば、タネから増やす取播きでは、採種して直ぐに蒔く栽培方法と乾燥させて保存した後、
タネ蒔き適期となる早春の3月に蒔いて増やす方法があります。さらに挿し芽で増やす場合には、やや固くなった茎を利用しますが、固さが出る5月下旬頃に茎をカットし、切り口から出てくる乳液を洗い流して砂床に挿して増やします。その他、株分けによっても増やすことは可能で、株は老化してくるために3年に一度程度で行うのが適しており、
2月頃に刃物または株を割り、その切り口に殺菌剤を塗布して適期に植え付けを行います。ツリガネニンジンは食用としての利点があるため、自ずと害虫による食害を受けるために害虫予防や対策は育てる上で必要なことの1つです。ツリガネニンジンはヨトウムシやナメクジなどが発生しやすく、ナメクジは箸などを使い駆除します。
その他、ネコブセンチュウやネコナカイガラムシなども発生しますし、また害虫だけではなく夏時期にはうどんこ病が発生しやすいのもツリガネニンジンの特徴で、病害虫対策となる薬剤は必要です。食用目的で栽培する場合には、黒酢や木酢をはじめ、牛乳や防虫対策に効果的な植物を連植えすることも適しています。
ツリガネニンジンの仲間の歴史
シャジンの仲間であるツリガネニンジンはキキョウ科に分類され、和名では釣鐘人参と表されています。日本や朝鮮半島を原産としており、学名はAdenophoratriphyllaの多年草の植物です。日本での栽培歴史も古く、生息地は日本全土の山野や丘陵であり、この植物の名前の由来としては花冠が寺に吊るされている梵鐘となる吊り鐘型をしており、
その根は朝鮮ニンジンに似ていることから付けられています。日本での歴史の中にははやし歌が存在しており、その歌は春先のツリガネニンジンの若芽は美味であり、人に食べさせるにも惜しくなる気持ちを歌に表しています。はやり歌に出てくるトトキは古い呼び名であり、この歌同様に食用として食卓にのぼっていた歴史も現在、色濃く残されています。
ニンジンに似た根には有効成分であるフラボノイド・トリフィロール・イヌリンなどが含まれており、去痰・鎮咳作用があるために慢性化した咳止めまた痰切り目的で栽培されていた歴史が残されています。さらにシャジンの仲間であり、強心作用や皮膚に寄生する真菌を抑制する作用があることから、煎じた薬草としても利用されており、
生薬などの漢方の1つとして栽培が盛んに行われていました。さらにはやし歌同様に、春に芽生えする柔らかな若苗を摘み、和え物やお浸し、さらに太い根茎は刻んで粕漬けにする地域もあり、古くから観賞用としてではなく、食用また薬草として普及が進み現在に至ります。
ツリガネニンジンの仲間の特徴
キキョウ科に分類される植物は、温帯にかけて約60属2000種の品種が存在しており、ツリガネニンジン属は50種ほどであり、日本には10種類程度が自生しているのが特徴の多年草植物です。上記で挙げた通りに根は朝鮮ニンジンに似ており、真っ直ぐ地中深く伸びるのが特徴で、その深さは70cmにも伸び、色は淡い黄色をしています。
茎部分は全体に毛がびっしり生え、分枝することは無く、茎を切ると乳液が出るのも特徴の1つです。根生葉は長柄があり花期には枯れ落ち、茎生葉は柄が無く3枚から4枚輪生し、対生・互生することがあるのも特徴で、その形は長楕円形や卵形などまでがあり、葉縁はノコギリ歯状で長さは4cm程度から生育度合いで8cm程度です。
ツリガネという名前の通り、花冠の形は鐘状で茎の上部から5段程度に分かれて下向きに輪生します。花は9月から10月頃が見頃で、花色は淡い青紫色または白色をしており、花冠の先は浅く裂けてやや広がり、雌しべは花びらから外へ突き出ている形状です。香りはキキョウ科に分類されていることからもほのかに香り、
春の新芽となる葉は食用としても食べることが可能で、苦味があるものの香りが良く、和え物として調理されます。さらに根の部分は乾燥させて薬草としての利用価値があるのも特徴で、春時期に新芽を収穫し、初夏から秋口に花を観賞し、冬に根を収穫するなど、季節によって収穫栽培できる多年草植物でもあります。
-

-
ヘンリーヅタの育て方
特徴として、まずブドウ科、ツタ属であることです。つまりはぶどうの仲間で実もぶどうに似たものをつけます。しかし残念ながら食...
-

-
ナスの育て方
インドが原産の植物といわれ、中国でも古くから伝わる植物でもあります。栽培の歴史は数千年を超え、農業に関する世界最大の古典...
-

-
エキノプスの育て方
エキノプスはキク科ヒゴタイ属の多年草植物の総称で、この名前の由来はギリシア語で「ハリネズミ」を意味する「エキノス」と「~...
-

-
ツニアの育て方
この花の特徴はラン科です。園芸分類としてもランになります。見た目もランらしい鮮やかで豪華な花になっています。多年草で、草...
-

-
バラ(バレリーナ)の育て方
バレリーナの特徴としてはまずはつる性で伸びていくタイプになります。自立してどんどん増えるタイプではありません。ガーデニン...
-

-
ニシキギの育て方
ニシキギは和名で錦木と書きます。その名前の由来は秋の紅葉が錦に例えられたことでした。モミジやスズランノキと共に世界三大紅...
-

-
オンファロデスの育て方
オンファロデスは、ムラサキ科、ルリソウ属(ヤマルリソウ属)です。オンファロデスは、北アフリカやアジア、ヨーロッパなどが原...
-

-
カッコウアザミ(アゲラータム)の育て方
アゲラータムは別名カッコウアザミという和名を持っています。アザミに花はとても似ていて、その関係からカッコウアザミという名...
-

-
ミルクブッシュの育て方
種類は、トウダイグサ科、トウダイグサ属になります。ユーフォルビア属に該当することもあります。園芸として用いるときの分類と...
-

-
クリスマスローズの育て方
クリスマスローズは別名ヘレボラスと呼ばれ、その歴史は古く、人々の生活の中に根付き利用されてきました。古代ギリシャ時代の医...




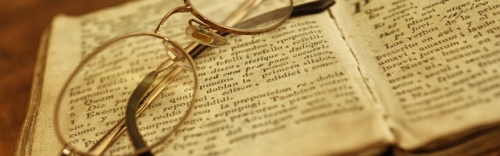





シャジンの仲間であるツリガネニンジンはキキョウ科に分類され、和名では釣鐘人参と表されています。日本や朝鮮半島を原産としており、学名はAdenophoratriphyllaの多年草の植物です。日本での栽培歴史も古く、生息地は日本全土の山野や丘陵であり、この植物の名前の由来としては花冠が寺に吊るされている梵鐘となる吊り鐘型をしており、その根は朝鮮ニンジンに似ていることから付けられています。