タアサイの育て方

タアサイの育てる環境について
タアサイには幾つかの品種が在りますが、中でも育てやすい品種と言うのは、緑菜二号、タアサイと言った種類になります。尚、連作を嫌う事からも同じ場所での作付けは控える必要があります。種まきを行う2週間前に苦土石灰を入れて耕しておき、1週間前には肥料を入れて耕して準備を進めます。
因みに、種まき以外にも苗を植える方法もありますが、苗はホームセンター、園芸ショップ、通販サイトなどで購入が可能です。植え付けを行うのは春植えは4月から5月で、収穫時期は5月下旬~7月上旬、秋植えは9月から10月で収穫時期は10月中旬~2月上旬となります。
秋植えの場合は長い期間収穫が出来る事や害虫の被害が少ないと言うメリットが有りますが、春植えと秋植えでは形が異なるので植える時には株間を考えて植えることが大切で、春植えは株間を広くし(20~30cm)、秋植えは株間を狭く(10cm)にすると言った工夫が必要です。
これは夏の太陽により株が大きくなるため、20~30cmの株間が必要であり、冬場は比較的株が小さくなるので株間は10cmが良いとされているのです。但し、甘味については春植えよりも秋植えの方が強くなるのが特徴で、
寒い時期に一生懸命成長しようとする中で糖分を蓄え、その結果甘いタアサイを栽培数r事が出来ると言う事なのです。尚、生育適温は5度から30度で、地植えの場合では、水はけが良く、日当たりが良い場所を選ぶ事が大切です。
タアサイの種付けや水やり、肥料について
タアサイの発芽に適している温度は18度から25度、生育適温は5度から30度となります。定温に強い事からも作付けは春と秋の2度行う事が出来ますが、連作を嫌う事からも同じ場所で春と秋の2度行う事は出来ません。そのため、春はプランターで栽培を行い、秋は地植えと言う方法もお勧めです。
また、寒い時期ほど甘さを増す事や、害虫の被害が少ないなどからも、初心者は秋植えがお勧めですし、大きな株に育つと言う利点も有ります。種まきによる栽培と苗による栽培何れも可能ですが、どちらの場合も2週間前から畑の準備をしておく必要があり、
苦土石灰や堆肥を入れて良く耕し、1週間前には化成肥料などを利用して耕して土を作っておきます。植え付ける時には植える時期に応じて株間や種をまく間隔に注意が必要です。間引きは株を大きくする目的や甘味を高めるなどの目的からも必要となる作業で、
間引きは2度行って最終的に1株を残すようにします。1度目の間引きは種をまいてから本葉が出た時点で、育ちが悪い株を間引きます。2度目の間引きは、本葉が3枚になった時点で行い、これについても育ちが悪い株を間引きます。
尚、種まきをする場合は直接畑に行うのではなく、ポットを利用して種を3~4粒入れて苗を作りますが、種をまいた後は、軽く土をかぶせてあげてから水をあげます。この場合も間引きは大切で、最終的には1つの株を残し、本葉が4~5枚になった時に間引きを行うのがコツです。
タアサイの増やし方や害虫について
タアサイは春植えと秋植えでは増やし方のポイントや害虫に対する防除が異なります。春植えの場合は条間を15㎝、株間を10㎝、秋植えの場合は条間を25㎝、株間を20~30cmにして植え付けます。追肥は、最後の間引きを行う段階でもある、本葉が3枚になった時に1回目、本葉が5枚になった時に2回目の追肥を施してあげます。
収穫時期は、春植えの場合は種まきをしてから40日~50日後、秋植えの場合は種まきをしてから50日から65日後になります。尚、春まきは達性とよばれるもので、とう立ちする可能性が有り、背丈が15cm~20cmになった段階で収穫をしておきます。
一方、秋まきはとう立ちはしないのですが、株を大きくすると葉が硬くなるため、背丈が20cm~25cmになった段階で収穫をしておきます。また、増やし方のポイントとしては下葉をかきとるように収穫をすれば、収穫期間を長くすることが出来ます。
尚、春まきの場合は害虫の被害に遭いやすいため、寒冷紗等を利用して防除する必要が有りますが、秋まきの場合は害虫の被害が少ないため、初心者の人にも簡単に栽培することが出来ます。但し、秋まきの場合は、葉の部分が地面に大きく開いて育つ性質が在ります。
株間は十分確保して植え付けを行っておく必要が有り、春まきと比べると秋まきの方がスペースを多く必要となります。尚、アブラムシや青虫など色々な害虫の害を受けることになりますのでその都度防除が必要です。
タアサイの歴史
中国が原産となるタアサイの歴史は中国の長江付近となる華中で、栄の時代となる960年から1279年に体菜より派生したと言われています。中華料理でもお馴染みのタアサイは、江戸後期に日本に伝来されていると言われており、ブランド白菜でもある長崎白菜はこの伝来により派生した野菜だと言います。
現在のタアサイが本格的に使われるようになったのは昭和9年(1934年)頃であり、当初は如月菜(キサラギナ)と呼ばれていたのですが、戦中の混乱、見た目が変わっているなどの理由からも、普及はそれほどしなかったと言います。
その後、中国野菜のブームなどにより国内でも人気が高まり、生産も増加し生息地も増えていると言います。因みに、タアサイは漬け菜に含まれる野菜であり、小松菜や野沢菜と同一だと言いますが、漬け菜類を分類する場合には、タアサイ群と言った分類の方法が在ります。
先ほど説明を行った長崎白菜はタアサイ群に含まれる事も有るとしています。近年健康ブームや農薬などの利用による健康被害からも、家庭菜園などで野菜を作る人も増えていますが、タアサイは初心者でも簡単に栽培出来る事や、プランターなどでも栽培が出来るため、
マンションのベランダなどを利用して栽培をする人も多いと言います。古い時代の中ではこのような自家栽培を行うと言う事は少なく、栽培を行う大半は農家などの専門職を持つ人々です。現代は色々な野菜を個人で作り楽しめるというメリットも有るのです。
タアサイの特徴
タアサイは中国が原産地であり、アブラナ科アブラナ属に属する中国野菜です。また、別名が如月菜(キサラギナ)や黒白菜(クロハクサイ)、縮み雪菜(チヂミユキナ)とも呼ばれており、中華料理などでおなじみの食材です。
旬としては2月頃になりますが、漬け菜にした場合は鮮度が命であり、日持ちがしないため、なるべく早めに食べることが大切です。尚、湿らせた新聞紙に包んでからポリ袋に入れて冷蔵庫に入れておけばある程度は保存が出来ます。
濃い緑色の葉が鮮やかなタアサイですが、この色には色々な栄養成分が含まれており、βカロチンを初め、ビタミンEやカルシウム、カリウムなどの栄養素がたっぷりと含まれています。また、これらの栄養素は油を使って炒めてあげることで栄養を壊す事無く身体の中に吸収してあげることが出来ますし、
油と一緒に食べることで吸収も高まり、健康効果を期待する事も出来ます。因みに、タアサイの旬は2月頃と言われていますが、寒さ強い野菜で有る事や、暑さにも強い事からも1年に2度の植え付けが出来る野菜でもあり、植え付け時期としては4月から5月頃と、8月から10月頃の2度になります。
尚、初心者の人の場合は8月から10月頃の秋植えを利用すれば、害虫の被害も少ないですし、寒い時期には甘みが増す事からもお勧めですし、秋植えについては収穫時期が春植えよりも長くなるためお得と言ったメリットが有るなど、春植えよりも秋植えの方が育て方も簡単です。
野菜の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:漬け菜類の育て方
タイトル:タマネギの育て方
-

-
ホオズキの育て方
ホオズキは、ナス科ホオズキ属の植物です。葉の脇に花径1~2センチ程度の白い五弁花を下向きにつけるのが特徴です。同じナス科...
-

-
サッコウフジの育て方
サッコウフジは、マメ科のナツフジ属に属している花になります。学名がMillettiareticulataになりますので、...
-

-
アブチロンの育て方
アブチロンはアオイ科の属の一つで、学名はAbutilonです。別名としてウキツリボクやショウジョウカ、チロリアンランプと...
-

-
センブリの育て方
センブリはリンドウ科センブリ属の二年草です。漢字で「千振」と書き、その学名は、Swertiajaponicaとなっていま...
-

-
初心者でも簡単な観葉植物について
最近は趣味として、ガーデニングなどを楽しんでいる方がどんどん増えています。自宅の庭に色とりどりの花を咲かせたり、ベランダ...
-

-
ヤブミョウガの仲間の育て方
ヤブミョウガはツユクサ科の花です。したがって、ヤブミョウガの仲間はミョウガではなくツユクサです。ちなみに、ミョウガは歴史...
-

-
じゃがいもの品種と育て方
じゃがいもは、寒さに強い植物です。人気は男爵やメークイン、キタアカリです。男爵は粉質が強いので、じゃがバター・ポテトフラ...
-

-
アボカドの育て方・楽しみ方
栄養価も高く、ねっとりとした口当たりが人気のアボカド。森のバターとしてもよく知られています。美容効果もあり、女性にとって...
-

-
バラ(シュラブ・ローズ)の育て方
バラの歴史はとても古く、恐竜が世界を支配していたころから始まります。さらに初めに文字として誕生したのは古代メソポタミア文...
-

-
セアノサスの育て方
セアノサスはカナダ南部や北アメリカにあるメキシコ北部が原産となっています。花の付き方が似ているという理由から、別名をカリ...




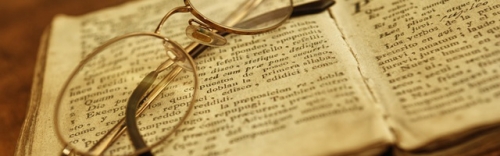





中国が原産となるタアサイの歴史は中国の長江付近となる華中で、栄の時代となる960年から1279年に体菜より派生したと言われています。中華料理でもお馴染みのタアサイは、江戸後期に日本に伝来されていると言われており、ブランド白菜でもある長崎白菜はこの伝来により派生した野菜だと言います。