アセビの育て方

アセビの育てる環境について
アセビは園芸品種としては育てやすい部類に入る品種です。環境に対する適応能力も高く、少々日当たりの悪いところでも丈夫に生育します。たとえ園芸初心者でも大きく育て方を間違えさえしなければ、立派に育てることができるでしょう。
もちろん花つきをよくするためには、ある程度日当たりの良いところで育てるほうがいいのは言うまでもありません。ただしこの品種は強烈な暑さにはあまり強いほうではありません。また乾燥も苦手ですので、西日のさしこむような場所には植えるのを避けたほうが無難です。
また水はけの悪い土地や粘土質の土地などに植えてしまうと、根の生育が妨げられることになり、期待通りに成長しない可能性があります。水はけが良く、かつ適度に湿り気のある土壌に植えるのが最も良いのですが、条件的にそのような土壌に植えることができない場合は、
あらかじめ植える予定の土壌に堆肥や腐葉土を混ぜ込んでおき、少しでも土壌が改善されるようにしておきます。鉢植えの場合は、赤玉土、鹿沼土、腐葉土を同じ割合で混ぜた土を使用します。また上記に挙げたように、極端に日当たりの良い場所に置いておくと、
乾燥や暑さで木が弱ってしまう恐れがありますので、できることなら一日中日光のあたり続ける場所に置くことは避けて置きましょう。もっとも環境適応能力が高い品種であることには違いありませんので、育てる環境についてはそれほど神経質にならなくても大丈夫です。
アセビの種付けや水やり、肥料について
アセビの植え付けの時期は2月から3月にかけておこないます。春の芽出し前におこなうのがいいのですが、9月から10月の秋ごろに植え付けをおこなっても問題ありません。鉢植えのものを植え替える場合も、春におこなうといいでしょう。
アセビを生垣に用いる人もいますが、このような場合は生育した後のことを考えて、1.5メートルから2メートル程度は空けて植えるようにします。また乾燥を防ぎ、花つきを良くするためにも、水切れは避けなければいけません。
特に生育期の水切れは生育そのものを止めてしまうことになりかねず、次の年に出てくる蕾の数が減少してしまう可能性があります。また花穂が伸びる頃に乾燥してしまうと、蕾が枯れ落ちてしまうこともありますので注意が必要です。もっとも露地に植えた場合は、
一度根付いてしまうと少々のことでは乾燥にも負けることはありません。鉢植えの場合に水切れに注意が必要なのです。ただし過度の水やりは樹勢が弱まるきっかけにもなりますので、根鉢付近が乾燥してきてから水を与えるようにするのがコツです。肥料は1月から3月にかけて株もとに施肥します。
肥料として用いるのは油粕や化成肥料などです。春に肥料を与えるのは、花穂ができる秋にむけて十分に栄養をとりこませるためです。積雪地帯ではこの施肥は雪解け後におこなうようにします。また葉の色を良くするために、秋に追肥をおこなう場合もありますが、この際はあまり多くの肥料を与えてはいけません。春に与えた肥料の3分の1程度で十分です。
アセビの増やし方や害虫について
アセビは挿し木によって増やすことができます。5月から6月頃に、その年に伸びた枝を10センチメートルほど切って水揚げをします。水揚げはおよそ1、2時間で十分です。その後で下の部分の葉を取り除き、3、4枚残した上の部分の葉も半分に切っておきます。
あとはこれを鹿沼土の用土に挿し、半日陰で保管して根の定着を待つのです。アセビは病気には強い植物ですが、害虫には注意が必要です。殺虫剤の原料となることで知られるこの樹木にも、被害を及ぼす虫は存在するのです。アセビに群がる害虫としてはグンバイムシやハマキムシが代表的です。
グンバイムシは体長3ミリメートルほどの小さな虫で、羽が生えており、葉に群がって栄養を奪います。グンバイムシの被害にあった葉は色が抜けて白くかすれたような状態になります。特に春先に被害が多く、乾燥が続けばグンバイムシが発生する可能性が高くなりますので注意が必要です。
もしグンバイムシを確認した場合は、薬剤を散布して早めに駆除することが大切です。ハマキムシは3センチメートルほどで、幼虫の時に葉を食したり、自らが出す糸で葉を丸めたり、数枚をくっつけて寝床にすることで被害を起こします。
袋状に丸まった葉や数枚の葉がくっついている場合は、このハマキムシの幼虫の被害にあっている可能性があり、またその中にハマキムシの幼虫が潜んでいることも考えられますので、葉をハマキムシの幼虫ごと取り除いて駆除します。
アセビの歴史
アセビは日本や中国が原産で、古くから日本人の生活になじんでいた植物です。その証拠に枕草子や古今集のなかでその名がみられるほか、日本最古の歌集である万葉集にも、大伴家持や大来皇女らによってアセビをモチーフにした歌が詠まれています。
万葉集にはアセビを詠んだ歌が10首ほどあるとされていますので、このことからもアセビが当時から日本人の暮らしに溶け込んでいた植物であることをうかがい知ることができます。そもそもアセビは日本の東北以南が生息地で、山地には樹高が5、6メートルにもなるものが自生していることもあります。
しかし、庭木として用いられる場合は高くても3メートル程度ですので、低木の部類に入ります。樹形も美しく、春にはスズランのような花をたくさん咲かせることから、現代でも人気の高い庭木です。また盆栽としても広く人気を集めています。
しかし、江戸時代頃のアセビは庭木としての役割だけでなく、殺虫剤の原料としても知られていました。アセビを漢字では馬酔木と書きますが、これは馬がこの植物を食すと中毒症状を起こし、まるで酔っ払っているような状態になることからこの漢字があてられたとされています。
江戸時代後期の本草学者、小野蘭山の著書「本草網目啓蒙」にはアセビを煎じた液体を冷やし、菜園にやってくる虫を駆除するための殺虫剤として使用することが記されており、このことからも当時の人はアセビが持つ有毒成分を上手く利用していたことがわかります。
アセビの特徴
アセビは常緑性の低木です。山地に自生しているものの中には、高さ5メートル以上になるものがあるとされていますが、庭木として利用される場合はせいぜい2,3メートルの高さになります。濃い緑の葉とスズランのような白い花が特徴で、春の満開時には木が覆われるほどたくさんの花を咲かせます。
さらに新芽もつやのある赤い色をしており、花に負けない美しさがあります。アセビは園芸品種として広く栽培されていますが、現在では品種改良が進み、オーソドックスな白い花を咲かせる品種だけでなく、赤やピンクの花を咲かせる品種も登場しています。また日本が原産地です。
同じ仲間は世界各地に広く存在しており、外国産の品種の栽培もおこなわれています。たとえば濃い赤色の新芽が特徴的なヒマラヤ原産のヒマラヤアセビや、白い花を咲かせるアメリカアセビが代表的です。また同じ日本国内でも、沖縄のリュウキュウアセビはまた一味違います。
奄美諸島や沖縄が原産のこの品種は、他の品種の花とは異なり、下に垂れることなく上向きに伸びて行くのが特徴です。この品種と日本原産の品種を掛け合わせたものがスプリングベルという名で栽培されていますが、これは花がつぼみの状態の時は濃いピンク色なのに、
開花すれば淡いピンク色になるのが特徴で、春にぴったりな品種として人気を集めています。さらに忘れてはいけない特徴は、木全体に有毒成分が含まれているということです。古くは殺虫剤としても使用されていましたが、摂取すると呼吸困難や痙攣、おう吐、下痢などの症状が現れます。
庭木の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:シキミの育て方
タイトル:カルーナの育て方
-

-
クチナシの育て方
クチナシの原産地は日本、中国、台湾、インドシナ、ヒマラヤとされており、暖地の山中に自生し、広く分布しています。主な生息地...
-

-
春の風物詩 チューリップの育て方について
桜の花に次いで春の風物詩となる植物がチューリップです。独特のふっくらとした形が特に女性に人気があります。卒業式や入学式な...
-

-
サポナリアの育て方
サポナリアの科名は、ナデシコ科で属名は、シャボンソウ属(サポナリア属)となります。また、和名は、シャボンソウでその他の名...
-

-
ケショウボクの育て方
ケショウボクはダレシャンピアという名前で流通していることも多い、トウダイグサ科ダレカンピア属の常緑低木です。メキシコから...
-

-
アキザキスノーフレークの育て方
オーストリア、ハンガリーなどの南ヨーロッパ西部を原産国とするアキザキスノーフレークは、この名の通り、秋に咲くスノーフレー...
-

-
バラ(ブッシュ・ローズ)の育て方
ブッシュローズは低木として育つものを差します。ヨーロッパにももともとあったそうですが、現在園芸品種として出回っているもの...
-

-
ミズバショウの育て方
ミズバショウの大きな特徴としては白い花びらに真ん中にがくのようなものがある状態があります。多くの人はこの白い部分が花びら...
-

-
メロンの育て方
園芸分野では実を食用とする野菜、「果菜」とされています。青果市場での取り扱いや、栄養学上の分類では果物や果実に分類されて...
-

-
オヤマリンドウの育て方
オヤマリンドウの特徴は名前の由来にもなっておりますように、ある程度標高の高い亜高山や高山に咲くことが大きな特徴です。そし...
-

-
ワイヤープランツの育て方
ワイヤープランツは観葉植物にもなって家の中でも外でも万能の植物です。単体でも可愛くて吊るして飾っておくとどんどん垂れてき...




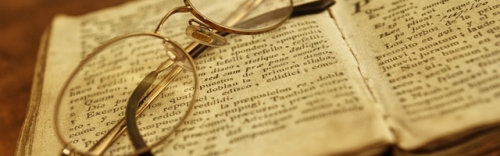





アセビは日本や中国が原産で、古くから日本人の生活になじんでいた植物です。その証拠に枕草子や古今集のなかでその名がみられるほか、日本最古の歌集である万葉集にも、大伴家持や大来皇女らによってアセビをモチーフにした歌が詠まれています。