アルケミラ・モリスの育て方

アルケミラ・モリスの育てる環境について
アルケミラ・モリスは多年草で、原産地はヨーロッパ東部〜アジアで、耐寒性は強く、耐暑性は普通で高温多湿に弱いため暖地では育ちが悪くなります。半日陰でも育ち、日向の場合は夏は遮光した方します。育て方は難しくはありませんが、注意するポイントがいくつかあるため、
それらを守れば長く楽しむことができます。春に芽吹いて、春から初夏に花を咲かせます。上手に夏超しをさせると寒さにあたって秋に紅葉して、冬には枯れて地上部はなくなりますが、根は生きていて、春にはまた芽を出します。高温多湿に弱いため、夏は風通しが悪いと腐って枯れてしまいます。
この夏の時期に枯れたら根まで腐ってしまいます。蒸れを防止するために梅雨前にアルケミラ・モリスを約10cm程度に短くカットします。夏を超すことができれば秋にはまた出てできます。冬は寒さで地上部が枯れ、春に成長して芽を出します。
春に新芽が出た時に邪魔になってしまう冬に枯れた枝は掃除をする必要があります。地域差もありますが、アルケミラ・モリスの夏超しは難しいです。腐葉土を与えると黄金虫がつき、半日陰に移動しても夏超しができるとは限りません。
非常に成長が早く、春から初夏までどんどん株が成長して大きくなるため、この時期まで楽しむことが大切です。霜が降りなくなってから、春に植えつけをします。霜にあたると枯れてしまいます。店頭などでは早めにアルケミラ・モリスを販売するため、
植えつけの時期を見定める必要があります。日光を好みますが、高温多湿に弱く半日陰でも育てることが可能なため、夏に暑い地域なら半日陰で育て、鉢植えなら夏は風通しの良い半日陰か日陰へ移動します。
鉢植えの場合、適した用土は山野草用培養土で、夏超しも容易になります。自分で配合する場合は、山砂などを主体にして腐葉土を2割混ぜた用土を使用します。草花用培養土やピートモスの多い用土で植えると夏に株が弱りやすくなります。
種付けや水やり、肥料について
水はけのよい土を好み、耐寒性はとても強いです。水やりは土が乾いてから水を与えます。高温多湿に弱いので水のやり過ぎには注意が必要です。庭に植えた場合は、土の水もちの程度にもよりますが、殆ど降雨だけで十分に育ちます。
乾燥させると株が弱まってしまいます。庭植えでは、根がしっかり張った場合は殆ど水やりは必要ありませんが、晴天が続いて土の中まで乾燥する時はたっぷりと水を与えます。鉢植えの場合は、表土が乾き始めたらたっぷりと水を与えます。太平洋側では冬の間の乾燥にも注意が必要になります。
植えつけ時に腐葉土などをよく混ぜて、元肥として化学肥料などを少量与えます。庭植えでは、特に肥料などは必要ありませんが、早く大株にしたい場合は、秋と早春に株のまわりに化成肥料をまいておきます。鉢植えでは、10月から11月と3月から4月に、それぞれ置き肥なら2回、液体肥料なら4〜5回与えます。
アルケミラ・モリスの株元に腐葉土や砂利を敷き詰めることで株の温度が上がることを防ぐ効果が期待できます。砂利は水はけがよくなりますが、日当りが良いと暑くなる場合もあるため、温度管理への注意が必要です。
植えつけ時期は、ポット苗は9月〜11月、3月〜5月です。株分けした苗は11月〜3月頃の植えつけ時期が適期です。植える場所に腐葉土などをよく混ぜて水はけを良くし根が深く張れるようにします。深植えにならないように芽の位置は地表面と同じ高さに植えます。暖地での栽培は、落葉樹の下など明るい半日陰に植えます。
増やし方や害虫について
春に咲いた花には種ができ、これがはじけて遠くに飛んで行き、広範囲にこぼれ種が落ちてアルケミラ・モリスを増やすことが可能ではありますが、株分けや種をまいて増やします。株分けの時期は、秋か早春に行ないます。芽の位置を確認して、根茎を分けます。
根茎の古い部分は次第に枯れていくため、切り詰めても問題はありません。種をまいて増やす方法は、種まきは4月から5月が適期で、秋も種をまくことができ、冷涼地では夏でも種まきが可能です。生育のよいものは2年目から開花します。
種とりに必要な花を残して、花がらを切り取ることも大切な作業です。開花後も長く残る萼をしばらく観賞することは可能ですが、雨で倒れたり色あせありするため、早めに切り取ることで見栄えもよくなり葉を秋まで長く観賞することができます。
株の成長に伴って太い根茎が横に伸びて少しずつ周囲に広がってきたタイミングで植え替えします。庭植えは3年ごとを目安に株分けして植え直します。鉢植えは、根詰まりすると生育や花つきが悪くなるため、毎年か1年おきに根をほぐして株分けして植えつけます。
アルケミラ・モリスの病気は根腐れすることです。水はけが悪いことと、高温期に根腐れを起こしやすくなります。水はけを良くして高温期に株元が高温にならないよう注意する必要があります。アルケミラ・モリスは害虫はつきにく植物でもありますが、注意が必要な害虫は毛虫類や黄金虫などです。毛虫類は葉や蕾を食害するため、見つけ出したら防除します。
アルケミラ・モリスの歴史
アルケミラ・モリスは、ハゴロモグサ属でバラ科の植物です。アラビア語のAlkemelych、錬金術に由来しています。アルケミラはハーブの一種でもあり、不思議な力を表しています。アルケミラ・モリスの葉の上に溜まる雫には魔法が宿っていると信じられており、
錬金術に用いた道具の中性の賢者の石を作るのに用いられたり、葉にたまった雫を飲むと流産を防ぐとも言われていました。アルケミラ・モリスの歴史は比較的新しく、古代ギリシャやローマ時代には、その名前が上がることはありませんでした。
中世に入り、中世ドイツの修道院長ヒルデガルト・フォン・ビンゲンにより喉の化膿に良く効くという記載があり、時がたつにつれて傷や胃腸の不調に適していると脚光を集めたハーブでもあります。中世以来、アルケミラ・モリスの葉が縁取りのあるマントに似ているため、
神聖視されるようになり、16世紀に植物家がレディースマントル(聖母マリアのマント)と名付けました。アルケミラ・モリス(レディースマントル)は葉を乾燥させて、ハーブティーや抽出した液を美容液代わりに用いると肌を引き締める効果が期待できますが、
日本で販売されいるアルケミラ・モリスは近緑種で、薬用に使用するアルケミラ・ウルガリスなどの種類ではないため、ハーブティーなどには使用できません。アルケミラ・モリスは園芸用で、薬効の効果なありませんが、愛らしい小さい花と優雅な葉が特徴的な植物なのです。
アルケミラ・モリスの特徴
ヨーロッパ北部からアジア北部が原産で、熱帯アフリカ、インド、スリランカ、インドネシアなど高山地帯に約250種類が分布しています。宿根草で野原や林などが生息地です。葉は丸形で、表面は細かい毛に覆われています。花は2〜3mmの小さな花が細かく枝分かれした集散花序につきます。
色は緑色か黄緑色です。耐寒性、耐霜性で、ハーブとしても利用されます。ハーブとしても使用されるアルケミラ・モリスは、月経不順や更年期の症状などあらゆる婦人病に良い効果が期待でき、葉を利用したハーブティーとして飲まれています。
優れた収斂効果もあり、下痢や胃腸炎も和らげます。うがい薬として使用すると喉の痛み、歯肉の出血を改善する効果が期待できます。タンニンを含み止血や消毒作用に優れるため傷薬としても用いられます。日本では北海道や本州の南北アルプスの高山地帯の草原にみられます。
高さは約30cm程度で、葉は丸形で複数に浅く裂けています。夏に約3mmの黄緑色の小花を密集してさかせます。アルケミラ・モリスは、葉の形から聖母マリアのマントを思わせることからレディースマントルとも呼ばれ、黄緑色の小花がふんわりと群れて咲いて繊細でソフトな印象を受けます。
草姿のバランスがよく、柔らかな葉が茂り、全体的に明るい雰囲気になります。葉は細かい毛に覆われて水をはじくため、朝露などが水玉になって葉の表面に残ることがあります。アルケミラ属には200種類以上あり、花壇や鉢で利用されるのは主にモリス種のアルケミラ・モリスです。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:オミナエシの育て方
-

-
ミニゴボウの育て方
ミニゴボウにかぎらず、野菜の中で形の小さい種類のものは昔からあったのですが、あまり受け入れられてきませんでした。育ちが悪...
-

-
パッションフルーツの育て方
パッションフルーツは和名をクダモノトケイソウという、アメリカ大陸の亜熱帯地域を原産とする果物です。かつてはブラジル、パラ...
-

-
ヒノキの仲間の育て方
ヒノキは原産として日本と台湾にのみ分布する樹木です。アメリカにおいては似ているものとしてアメリカヒノキがあり日本にも輸入...
-

-
ヘレボルス・フェチダスの育て方
特徴としてはキンポウゲ科、クリスマスローズ属、ヘルボルス族に該当するとされています。この花の特徴としてあるのは有茎種であ...
-

-
ファセリアの育て方
ファセリアはハゼリソウ科の植物で双子葉植物として分類されていて280種ほどが世界中で栽培されていて、南北アメリカ大陸を生...
-

-
きゅうりの育て方を学びましょう。
今回はきゅうりの育て方について説明していきます。ウリ科であるきゅうりは水分を多く含み、それでいて水はけの良い土壌を好みま...
-

-
サルスベリの育て方
サルスベリは、木登り上手のサルですら、すべって登ることができないほど、樹皮がツルツルとなめらかなことからつけられた名前ら...
-

-
より落ち着いた雰囲気にするために 植物の育て方
観葉植物を部屋に飾っていると、なんとなく落ち着いた雰囲気になりますよね。私も以前、低い棚の上に飾っていましたが、飾ってい...
-

-
モミジの育て方
モミジは日本人に古くから愛されてきた植物です。色づいたこの植物を見に行くことを紅葉狩りといい、秋の風物詩として古くからた...
-

-
トベラの育て方
”トベラ”は日本や朝鮮半島、中国を原産とする植物です。名前の由来は、昔、節分の日に悪除けの為にトベラの枝を扉にはさんだこ...




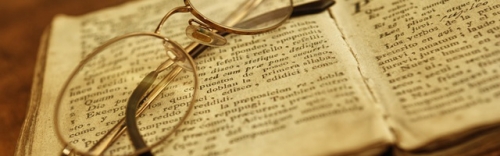





アルケミラ・モリスは、ハゴロモグサ属でバラ科の植物です。アラビア語のAlkemelych、錬金術に由来しています。アルケミラはハーブの一種でもあり、不思議な力を表しています。