ベレバリアの育て方

育てる環境について
栽培をしていこうとするとき、育て方としてはどのような環境をキープするようにすればいいのかがあります。こちらの花については乾燥した、日当たりの良い所を好むとされています。ですからまずは日当たりについてはしっかりと考慮する必要があるでしょう。基本的には1日日当たりがあるようなところで問題はありませんが、
きちんと育てていこうとするのであれば日当たりについては少し考慮をしたほうがいいとされています。午前中はいい日差しになるので直射日光が当たるようなところでも問題ありません。しかし西日などになるとあまりよい環境とは言えなくなります。そのことから午後において適している日当たりとしては明るい日陰にするようにします。
このようなところであれば西日に関しては避ける事ができますから、それ程暑くならないメリットがあります。嫌な日差しを受けることがあります。住宅の庭などであれば、庭が建物の東側にあるなら建物に隠れるように植えるようにすると東からの日差しは受けてにしからの日差しを受けなくても済むようになります。
その他植物同士の置き場の兼ね合いなどによって日差しの調整をすることはできます。1日日差しが必要なタイプがあるならそれを中心的に置くようにし、その東側に西日をあまり好まない植物を入れるようにします。植物同士で日陰を作ったりすることができます。あまり植物が近くなると風通しに影響することがあるので間隔は必要です。
種付けや水やり、肥料について
どのような用土を用意すると良いかですが、生息地としては乾燥した暖かいところになります。そのような土地に合うような土の配合が良さそうです。まずは水はけを考慮するようにします。よく育てようとするのであれば肥沃な土地も必要になります。よくある配合の一つになりますが、赤玉土を7割ほどにします。
この時の赤玉土としては小粒のタイプにします。それに腐葉土を3割いれたようなタイプにします。この植物においては酸性を好まないとされています。庭植えの場合は他の植物や土の影響をうけることがあるため、土に石灰をいれておくことで酸性にならないようにすることが可能になります。
水やりの頻度としてはそれなりに与えるような考え方になります。土の表面を見ながら、乾いた時が水やりのタイミングとされています。少しずつ与えるより、乾いてきたと感じた時にたっぷり与える方法にしていきます。花が咲くのは夏で、そのあとはどんどん枯れていきます。不安に感じてこの後水を与えようとするかもしれませんがその必要はありません。
これは自然の流れで、枯れることによって休眠状態に入ることができます。この時には水やりをしません。しっかりと休眠させる必要があります。肥料については、植え付けをするときにゆっくり聞くタイプのものを置くようにします。粒状タイプが適当とされています。最初に混ぜ込んでおくと土も良い状態にすることができます。化成肥料を利用することもあります。
増やし方や害虫について
増やし方としては球根を分球することによって行うことができます。花は春に咲き、6月になってくると徐々に葉が黄色く枯れれるようになります。この時に球根を掘り上げるようにします。葉が全て枯れて休眠の状態になってから掘り起こすことがありますが、その時には元の球根しか無いことがあります。
分球は元の球根に複数の球根がつくことによって行えますが、くっついた状態でないと行いにくいです。休眠状態までになると、外れてしまっていてわからなくなっている事があり、うまく分球することができません。そのために時期を待ったほうが良いとされています。
分球をするために掘りあげた球根に関しては、日陰の風通しの良い所で陰干しをします。最初は葉がついていることもありますが、葉が枯れればそれを取り除いて貯蔵するようにします。小さい子球を取り外すのは秋口に植える直前ぐらいです。かかりやすい病気としては白絹病が会います。これは土の中にいる菌が影響する病気とされています。
これが出てくるようになると株を枯らしてしまいます。近くに別の株があるときはそちらにうつる可能性があるので病気にかかったものを掘り起こすようにしないといけないかもしれません。植え替えについて適度に行うのが育てる上での大事な点とされています。球根が増えて窮屈になることがあります。増やすつもりがなくても植え替えを行うなりして増えた球根を離す必要があります。切るタイミングを間違えないようにします。
ベレバリアの歴史
歴史が修正されることはよくあります。年号が変更されたり、ある人の肖像がと言われていたものが全く別人のものであること、そもそもその人自体の存在が怪しくなるようなことがあります。ですから歴史の教科書はかなり中身が変わります。これはしかたがないことで、わかった時点からどんどん修正されていくことになります。
これは生物などの分類などにおいてもあります。元々はある種類として分類されていて、その後に別の種類に分類され直されることがあります。研究などによってその仲間でない、もしくは同じ種類の花でないとされるのでしょう。ベレバリアと呼ばれる花については元々はムスカリパラドクサムと呼ばれることがありました。
見た目が非常に似ていることからそのように呼ばれるようですが、いろいろな研究によって別の仲間として扱われるようになってきています。原産地としてはイラン、イラク、トルコ、コーカサス地方とされています。西アジアの辺りで、東南アジアなどと比べるとかなり気候としては乾燥している地域になってくるでしょう。
日本への渡来に関しては明治の初期辺りには来ていたようです。一方で江戸時代にはすでに伝えられていたとの話もあります。この頃といいますとまだヨーロッパなどとの関連は少ないですが、オランダの船が来ることがありました。その時にはいろいろな珍しいものがやってきているので、その時に一緒に来ていたのではないかと言われることがあります。
ベレバリアの特徴
特徴としてはヒアシンス科となっています。ムスカリに関してはキジカクシ目、キジカクシ科、ツルボ亜科、ヒアシンス連となっていますからこちらと同じような種類になるともされています。球根で成長させることからユリの仲間とすることもあります。形態としては多年草として育てることが出来るようになっています。
草の丈はそれ程大きくなるわけでなく、高い状態でも20センチから30センチぐらいとされています。花の開花については4月くらいになりますから、春をメインに花をつけていく花ということが出来るでしょう。ムスカリと呼ばれる花と比較されることが多いのが特徴になっています。花ぶりとしては全体的にやや大きめになっています。
葉っぱに関しては幅がひろいタイプです。花の茎が太くなっているので、安定感があるような花になっています。風が少し吹いたからといって簡単に揺れたりすることはなさそうです。分類上はムスカリとは別になっていますが、花屋さんなどでは同様に扱われることもある花になります。どうしても区別して好みの方を選ぶのであれば
花屋さんに確かめないといけないかもしれません。花の穂については4センチほどになります。下向きの小さな花がぎっしりとつくようにして咲く花になります。花の色は非常に濃い青色になっています。花びらの縁と内側に関しては鮮やかな緑色、黄色になっています。それが非常に対照的で、目立つようになっていることがあります。
-

-
サルビア(一年性)の育て方
サルビアの正式名称はサルビア・スプレンデンスであり、ブラジルが原産です。生息地として、日本国内でもよく見られる花です。多...
-

-
セロジネの育て方
セロジネはラン科の植物でほとんどの品種が白っぽい花を穂のような形につけていきます。古くから栽培されている品種で、原産地は...
-

-
オミナエシの育て方
オミナエシは多年草で無病息災を願って食べる秋の七草の一つです。原産や生息地は日本を始めとした東アジア一帯です。草丈は20...
-

-
クサノオウの育て方
クサノオウは古くから日本に生息している山野草です。聞き慣れない植物ですが、黄色い花を咲かせるヤマブキソウに似ています。ク...
-

-
ブラックベリーの育て方
ブラックベリーの始まりは古代ギリシャ時代までさかのぼることができるほど古いです。このブラックベリーは人々から野生種として...
-

-
ハーブで人気のバジルの育て方
近年、ハーブは私達の生活に身近な植物になってきています。例えば、アロマテラピーなど香りで癒しを生活に取り入れたり、食事に...
-

-
ツリガネニンジン、シャジンの仲間の育て方
シャジンの仲間であるツリガネニンジンはキキョウ科に分類され、和名では釣鐘人参と表されています。日本や朝鮮半島を原産として...
-

-
ヤマアジサイの育て方
ヤマアジサイは、アジサイ科、アジサイ属(ハイドランジア属)になります。また、その他の名前は、サワアジサイと幅れたりします...
-

-
シクノチェスの育て方
シクノチェスはラン科の植物で独特の花を咲かせることから世界中で人気となっている品種で、15000種以上の品種があるとされ...
-

-
ヤマジノホトトギスの育て方
ヤマジノホトトギスはユリ科の植物です。そのため、ユリのように花被片があり、ヤマジノホトトギスの場合は6つの花被片がありま...




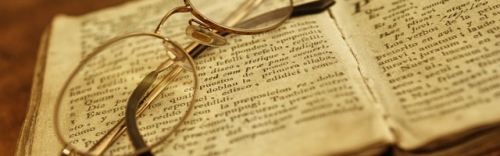





特徴としてはヒアシンス科となっています。ムスカリに関してはキジカクシ目、キジカクシ科、ツルボ亜科、ヒアシンス連となっていますからこちらと同じような種類になるともされています。