ベロニカの育て方

育てる環境について
栽培をするにあたっては育て方が必要になります。環境はどのような所が良いかです。日本において自生しているところとしては岐阜県であったり滋賀県にある山の山頂部とされています。高原植物の一つとして生息しているようです。となるとあまり暑さには強くない種類のように感じられます。
これらの地域に関しては確かに標高が高いところになりますが、必ずしもこういったところでないと育たないわけではありません。耐寒性、耐暑性ともにそれなりに高いとされています。種類によっては暑さに弱いタイプもあるようですが、一般的にはどのような環境にも対応できるようになっています。
生息地においては日本で自生している高原のほか、海岸においても見られるようになっているので、育てようとするときはその地にあった種類を選ぶようにすればよいでしょう。環境対応に優れているとされるので、ある程度どういったところでも育てることは出来るでしょうが、一応はどこが育てやすいなどの情報は確認するようにします。
種などで売られている時には書かれているでしょうし、苗などであれば販売員などに聞くことによって情報を得ることができます。日当たりに当てることが必要になりますから、庭などでは日当たりのいいところに置いたり植えたりするように考えておきましょう。土質としては肥沃なところだと育ちやすいですが必ず肥沃でないといけないわけではなく、高山などにおいてあまり栄養分の少ないところでも育ちます。
種付けや水やり、肥料について
種類によって異なるでしょうが、適応している土をそれぞれで用意する必要があります。鉢植えをする場合のいては、赤玉土、腐葉土を合わせた配合土で育てるようにします。今まで配合をしたことが無かったり経験が無いなら無理にそれを使う必要はなく、草花培養土を利用できます。
一般的にホームセンター等で販売されている草花を育てるときに使うための土になります。苦石石灰を少し混ぜておくことで土の状態を良くすることができるので、それも試すようにしてみましょう。植え付けに関しては3月から4月の春と9月から11月の秋に行うことができます。植え付けをしてから根付くまでに少しかかりますが、
この時には乾燥させないようにしなければいけません。乾燥させると栄養分が行き渡りにくくなってあまり育たなくなってしまいます。育てようとするときは花つきのものを購入することがあります。この時においては開花後大きめの植木鉢を用意してそちらに植えるようにします。庭に植え付ける方法でも問題ありません。
水やりをすることについては、庭植えではあまり必要ないとされています。あくまでも根が張った状態のことです。根が張っていない場合にはしっかりと水をやる必要があります。鉢植えでは水切れをしないように管理をします。水切れをしてしまうと葉が枯れたり、せっかくの花がつかない場合があります。乾いたと感じてきたら水を与えるようにします。蕾から開花までは多めに水を与えます。
増やし方や害虫について
増やし方は複数の方法で行うことができます。まずは株分けで簡単に行うことができます。植え付けや植替えの時に株を分けることで増やせます。十分に大きくなった株を利用するようにしなければいけません。気軽に出来るものとしてはさし芽があります。行う時期はある程度決まっています。6月頃、9月から10月頃とされています。
花芽でない若い芽を使います。それを1節ずつに切り分け、それぞれを差し込んで根付きを待つようにします。植え替えの時期でなくても簡単に行えるので、気がついた時にできそうです。種まきで増やす場合には春と夏に行います。4月から5月、9月から10月にかけて通い時期になります。
まいてから芽が出てきて葉が4枚から6枚ぐらい出てきた時に植木鉢に植え替えるようにします。面白いのは親株と違う花が咲くことがあることです。色を合わせたいときは困りますが、いろいろな色を見たいときには楽しみが増えそうです。病気には灰色かび病があります。日当たり、風通しが悪い状態にしていると起きますが、
これに気をつけていればそれ程簡単になるわけではありません。管理に気をつけるようにしておきます。害虫で気をつけるのはアブラムシぐらいとされています。この花における駆除も必要ですが、他の花についていることもあります。多くの花に春先になるとつきやすくなりますから、庭において出だした時は薬を使うなどして対応しなければいけません。数が出ると困ります。
ベロニカの歴史
動物の体の一部に似ていることからそのまま名前が付けられるものがあります。カメノテと呼ばれるものがあります。料理などで出されることもありますが確かに亀の手のように見えます。実際は貝のようです。ですから特に問題は無いでしょう。カメノテのようにリアルに似ているものもありますが、
なんとなくこれに似ているからと付けられるものもあります。ベロニカと呼ばれる植物があります。この植物の和名は非常に面白いです。ルリトラノオと名付けられています。一見何のことかと考えがちですが、ルリとトラノオが別々の意味を持つとするとすぐに分かるでしょう。
瑠璃色で虎のしっぽに似ているからこのように名付けられたようです。この花の原産としては正確なところはわかっていないこともあるようです。世界中に広く分布しているためですが、一応は北半球をメインに生息地としているとされています。ヨーロッパ、北アジアを中心とした原産とする見方もあります。
日本にもあったのかどうかはわかりませんが、一応歴史の上では明治時代の間に渡来したとされています。それ以前から咲いているものもあったかもしれませんが、伝えられたものが広がっているとされています。非常にきれいな色をしている花として知られていますが、それだけに品種改良も進められていて基本の色以外の色もどんどん出来てきているようです。そちらを好んでほしいとしている人もいますから、これからもいろいろな色が出てくるかもしれません。
ベロニカの特徴
特徴として何の種類かですが、シソ類、シソ目、オオバコ科となっています。ルリトラノオ属に該当するともなっています。多年草として知られていますが、一年草の種類もあるとされています。草丈に関しては、短いものだと5センチ程度のものがあります。長くなると1メートルぐらいの大きな草丈まで成長することがあります。
花が咲く時期としては4月から11月ぐらいです。一つの花がずっと咲き続けるのではなく、春咲き、夏咲き、秋咲きがあるとされます。それぞれが順に咲いていって、その期間咲いているように示されているようです。花の色としては、和名のルリからもわかるように青色がメインになります。自生しているのもほとんどが青色になるでしょう。
しかし今は品種改良が進んでいて、別の色で楽しめるようになっています。青色から少し変化した紫、かなり印象が変わるピンク、きれいな白色の花もつけることがあります。花に関しては遠くから見ると長い花のように見えますが、これは小さい花が集まった状態です。肉眼で見ようとするとかなり難しいかもしれませんが、
拡大写真などであればそれぞれの花について見ることができます。それを見ると4枚から5枚の花びらをつけた小さな花がたくさんついていることがわかります。したの方から徐々に咲いていくので、下のほうが膨らんで先のほうが細くなっている状態になっています。先の方が蕾の状態だと細く見えるのでより動物のしっぽのように見えます。
-

-
つい捨てちゃう、アボカドの育て方
最近では、サラダやグラタン、パスタなどに使われることもなりスーパーでもよく見かけるようになったアボカド。「森のバター」や...
-

-
フィットニアの育て方
フィットニアはキツネノマゴ科フィットニア属の植物です。南米、ペルー・コロンビアのアンデス山脈が原産の熱帯性の多年草の観葉...
-

-
アプテニアの育て方
この花については、ナデシコ目、ハマミズナ科となっています。多肉植物です。葉っぱを見ると肉厚なのがわかります。またツヤのあ...
-

-
ヒメヒオウギの育て方
現在の日本国内で「ヒメヒオウギ」と呼ばれる植物は、正式名称を「ヒメヒオウギズイセン」と言います。漢字では姫の檜の扇と書き...
-

-
センテッドゼラニウムの育て方
センテッドゼラニウムはフロウソウ科のテンジクアオイ属の植物です。ニオイゼラニウムという別名で呼ばれることがあるように、香...
-

-
サクラの育て方
原産地はヒマラヤの近郊ではないかといわれています。現在サクラの生息地はヨーロッパや西シベリア、日本、中国、米国、カナダな...
-

-
チングルマの育て方
チングルマは高山に咲く高山植物の一つです。白い花弁の中心には、黄色い色をした無数の雌蕊や雄蕊を持つ花で、登山をしていると...
-

-
ラグラスの育て方
ラグラスは、ふさふさした穂がかわいらしく、野兎のしっぽの意味を持つ名前で、イネ科の植物です。原産地は地中海沿岸で、秋まき...
-

-
ピーマンの栽培や育て方、トウモロコシの種まきと育て方
トウガラシのなかの一つで甘味料のある緑果をピーマンと呼んでいます。ピーマンの種まき時期は5月中旬頃でナスと同じ時期です。...
-

-
イングリッシュ ラベンダーの育て方
イングリッシュ ラベンダーは、シソ科のラベンダー属、半耐寒性の小低木の植物です。ハーブの女王としてゆるぎない地位を確立し...




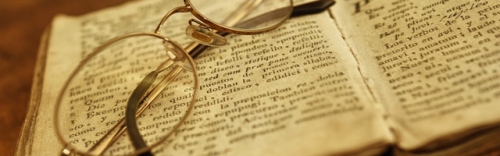





特徴として何の種類かですが、シソ類、シソ目、オオバコ科となっています。ルリトラノオ属に該当するともなっています。多年草として知られていますが、一年草の種類もあるとされています。草丈に関しては、短いものだと5センチ程度のものがあります。和名は、ルリトラノオ、その他の名前はスピードウェルと呼ばれています。