マツの仲間の育て方

育てる環境について
マツの仲間の天然分布は葉樹としては最も広い範囲をカバーしています。具体的には赤道直下のインドネシアから、北はロシアやカナダの北極圏に至る範囲が生息地となっています。その生命力は強く亜熱帯や熱帯に分布する種であっても、マイナス10度の低温・組織の凍結に堪えて生存する場合もあります。
わが国の代表的赤松、黒松、琉球松の3種のうち、赤松は本州で最も多く分布しており、乾燥した痩せ地でも良く育ちます。黒松は、防風や防潮、飛砂防備等のような防災に関する機能が期待される海岸林や、全国の名勝地における景観・風致林で主として利用されることが多いです。
琉球松は、鹿児島県の奄美大島から沖縄諸島の西表島にかけて分布しおり、これも防風林、防潮林などとして利用されることが多いです。このように過酷な環境でも育つ上、防災機能を果たし、建材や燃料としても有用であったことから、松は人から愛され続けてきました。全国各地にある名園・名所等には、
「○○の松」と名前をつけられた松の仲間が沢山あるのは、そのひとつの証左であると言えるでしょう。その中には、芸術的な形をしたものも多く、京都善峰寺の遊竜の松のように幹から左右に26メートルも枝を広げたものもあります。また東日本大震災で有名になった奇跡の一本松があります。
岩手県陸前高田市気仙町にあったこの松自体は、今では枯れてなくなってしまいましたが、その跡地には現在松の木のモミュメントが立てられています。これもある意味、松が日本人の心に深く根付いていることを表しているものと言えるでしょう。
種付けや水やり、肥料について
マツの仲間の育て方として栽培を種付けから行う場合には、秋に種を最終しておき、乾燥させないように保存しておいて、次の年の3月中旬から撒いて翌年に鉢上げするようにします。その際土は、赤玉小粒7,桐生砂小粒3の用土を用いるか、挿し芽・種まき用の土を使うとよいでしょう。庭植え、鉢植えをするときは2月から4月中旬が適期です。
移植をする場合にもこの時期に行えますが、植えつけて年数のたつ株は事前に根回しを施しておくことが必要になってきます。庭植えや鉢植えでも植えつけてから2年未満の株については、基本的に土の表面が乾いたらたっぷり水を与えるようにします。庭植えで、植えつけて2年以上たつ株については、特に水やりの必要はありません。
また基本的に肥料を施さなくても育ちますが、2月から3月に寒肥として、緩効性化成肥料の粒状肥料を1m2当たり150グラムを目安にして、株の周りの土の上にばら撒いて施しておくと葉色が濃くなってきます。病気や害虫による原因がないにも関わらず葉が黄化する場合、肥料不足が考えられます。
このような場合、寒肥を施すことで葉が緑色に戻ります。お手入れとしては、黒松は5月から6月に、伸び始めた新芽を間引いて切り戻す「ミドリ摘み」を行います。また10月から翌年3月に古葉と新葉をむしり取る「もみあげ作業」を行います。赤松については葉のないところからの芽吹きが弱いので、ミドリ摘み、もみあげ作業を行います。
増やし方や害虫について
マツは2~3月に、2年生苗の台木にして昨年に伸びた若い枝を割りつぎすることで増やせます。病害虫による被害を受けやすいので、その対策については常に気を配るようにしましょう。日本全体的に、松はマツ材線虫病により甚大な被害を受け続けている状況となっています。
防風林や防砂林といった場所の他にも、著名な景勝地の松が被害を受けており、かつては日本の白砂青松百選に選定された松原が衰退しまう等、大変深刻な状況となっています。病気としてはすす病にも注意して下さい。これはカイガラムシやアブラムシが発生し、その排泄物が堆積した結果、カビが発生する病気です。
葉が黒くすすに覆われたようになり、光合成も妨げてしまいます。害虫は、マツ材線虫病が代表的ですが、これが発生すると急激に増殖し樹液の流れをせき止め、2~4か月で葉が茶色く枯れ始めます。カイガラムシは樹液を吸うため樹勢が弱ります。幼虫の段階であれば、薬剤の散布が有効ですので、普段からの観察が大切になってきます。
アブラムシ類は何種類か発生することがありますが、冬に入る前に剪定して古い葉を落としておいて、風通しを改善することで寒さに当て、樹上で越冬できないようにすることで対処できます。マツカレハは、松の樹皮のすき間や落ち葉の下で越冬した幼虫が、春に葉を食べてしまいます。
ハダニは針状になった口を葉に刺し吸汁するため、その痕が白くなり葉が黄変します。これに対する予防策としては古い葉を取り除き、適度に風雨にさらすようにすることで対処します。薬剤も有効ですが、繁殖力や薬剤抵抗性が付きやすいことから、2種類以上を交互に使うと良いでしょう。
マツの仲間の歴史
日本における人間とマツの仲間との関わり合いの歴史は非常に古くから存在しています。用途の多い樹木であり、水湿に強い性質から、船材や基礎杭などに使われました。また樹脂を豊富に含んでいるため、燃えると高温を発生するということもあり、マツ葉も含め、燃料としても非常に優秀な存在でした。
古代から窯業がさかんだった大阪市の泉北丘陵では、木炭が大量に見つかっています。その際に窯に行われた調査で、当初使われていた木炭がカシなど広葉樹で占められていたのに対し、6世紀になる頃からアカマツが増え始め、7世紀になる頃には、そのほとんど全部がアカマツになっていたということがわかっています。
推定によると窯の周辺の照葉樹林が荒廃して、次第にマツ林に代わったと考えられています。痩せ地に強いマツの仲間は、土壌が荒れしまって、他の植物が中々成長できないようなところでも育つことができます。そうしたことから、人間の生活が急激に拡大し始めた飛鳥・奈良の時代には、おそらく燃料としての森林利用も増加したということなのでしょう。
それ以降の数百年の間にマツが増えて、日本人にとって親しみ深いものになったことは、8世紀に編纂された万葉集でわかります。「白波の浜松が枝の手向けぐさ幾代までにか年の経ぬらむ」「石室戸に立てる松の木汝を見れば昔の人を相見るごとし」等、非常に多くの松の木に関する歌が詠まれています。そこにはマツの仲間と人との関わり合いが、色とりどりに表現されています。
マツの仲間の特徴
マツの仲間の特徴としては、環境や種類によって様々に異なってくるものの、マツ属に含まれるものは、基本的に木本であり、草本が含まれていません。樹高は10メートル未満のものから、大きいものでは40~50メートルに達する種類もあります。アメリカでは、樹高80メートルを超える個体も確認されています。
樹木の樹形は環境に左右されることが多く、一定ではありません。苗木のうちは綺麗なクリスマスツリー状の円錐形のものも、大きくなるにつれて広葉樹の様な樹形になるものも多いです。マツの仲間のうち代表的なものには、黒松、赤松等があります。アメリカ原産の米松というものもあって、建材として多く輸入されています。
松は木目がハッキリとしているため、とても高級感があるため、視覚だけでも無垢の素晴らしさを感じ取れる事が出来る建材として人気があります。枝は同じ高さから四方八方に輪生します。幹として上に伸びる枝の軸と呼ばれるところや、横にのびる枝には、その先端に数個の冬芽を付けます。この芽が、夏から秋にかけて膨らんでよく目立つようになります。
マツの葉は4種類に分けることができ、それぞれ子葉、初生葉、鱗片葉、針葉となっています。普段、目にすることが出来るのは尋常葉(針葉)と鱗片葉です。この松葉には豊富な栄養成分が含まれており、漢方薬等に利用されています。24種類のアミノ酸が含まれており、他にも不飽和脂肪酸やビタミンA・C,フラボノイドといった、健康に有効な成分が含まれています。
-

-
植物の上手な育て方は土にある
花・ハーブ・野菜などの様々な植物の育て方や栽培方法は種類によって様々で、土・肥料・水やり・置場所などによって育ち方にも影...
-

-
レティクラツム・オウァリウムの育て方
この花についてはキツネノマゴ科、プセウデランテムム属となります。園芸上の分類としては熱帯植物です。また暖かいところに生息...
-

-
パンクラチウムの育て方
パンクラチウムはヒガンバナ科パンクラチウム属の植物です。原産はスリランカで、地中海沿岸に生息地が分布しています。17世紀...
-

-
アレナリアの育て方
アレナリアという花があります。この花は白くてかわいらしい花となっていますが、歴史があります。この名前で一般的に広く流通し...
-

-
初心者からはじめるミニ盆栽の育て方
少し前に流行ったミニ盆栽。若者にもひそかに人気があります。盆栽はなんといっても風格があります。3000円くらいから1万円...
-

-
ハナイカダの育て方
ハナイカダはミズキ科の植物です。とても形がユニークですので一度見ると忘れないのではないでしょうか。葉っぱだけだと普通の植...
-

-
ガーベラの育て方
ガーベラの歴史は比較的新しく、原産地は南アフリカで、元々自生していたキクの一種をイギリス人の植物採集家ジェイムソンらが本...
-

-
オクラの育て方
アオイ科に属する野菜で、原産地は、マントヒヒの生息地で知られるアフリカ北東部です。エジプトでは紀元前から栽培されていまし...
-

-
サキシフラガ(高山性)の育て方
サキシフラガは、ユキノシタ科ユキノシタ属に分類される高山性の植物です。また、流通名はホシツヅリ、別名をカブシア、ジェンキ...
-

-
ヘチマの育て方
熱帯アジアを生息地とするインド原産の植物です。日本には中国を通して江戸時代に伝わったと言われています。ヘチマは元々、果実...




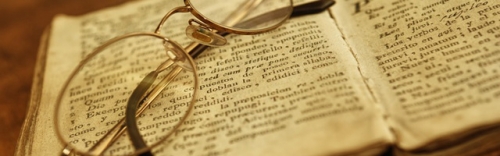





マツの仲間の特徴としては、環境や種類によって様々に異なってくるものの、マツ属に含まれるものは、基本的に木本であり、草本が含まれていません。樹高は10メートル未満のものから、大きいものでは40~50メートルに達する種類もあります。