ガザニア・リゲンスの育て方

育てる環境について
ガザニア・リンゲスの育て方について書いていきます。育て方のポイントは置き場所です。高温多湿を嫌いますので、日当たりの良い場所に置いてあげることが重要です。具体的には一戸建ての家であれば、普通に屋外に置くのも良いですし、マンションやアパート住まいであれば、ベランダの日なたが適しています。
しかし、真夏の時期になると注意が必要です。真夏は非常に高温になりますので、高温に弱いガザニア・リンゲスは日当たりの良いところに置いていると、弱ってしまいます。場合によっては枯れて死んでしまうこともあります。そのため、真夏になると、高温を避けるために日陰の風通しのよいところに一時的に移動させる必要があります。
ただし、ずっとそのまま日陰においていると、つぼみがついても開花しないことがあります。また、冬の時期になると、耐寒性は強くないので、室内飼育をお勧めします。ただし、室内で育成するときであっても、霜に注意することが重要です。そのような霜対策をすれば冬越しは容易です。室内の日差しが入りやすい場所に安置しておくとベターです。
ずっと一戸建てで庭植えで育成する場合していても、植木鉢に移さないといけません。育成環境としては、置き場所に注意しておけば問題はありませんが、肥料にこだわりたい人は、株元に腐葉土を敷き詰めれば良いです。あとは、枯れた花を放置しておくとタネが生まれて本体の栄養を搾取してしまうこともあります。したがって、花が枯れたあとの管理が大切です。
種付けや水やり、肥料について
ガザニア・リンゲスの栽培方法としては、種付け、水やり、肥料の3点から書いていきます。まずは、水やりについて書いていきます。ガザニア・リンゲスは乾燥状態を好み、湿気を含んだ用土を嫌います。そのため、水のやりすぎには注意する必要があります。水を与えることで成長を促す効果があるのはもちろんですが、植物によってはそれが有害になることもあります。
このガザニア・リンゲスはまさにその典型例です。したがって、春、夏、秋のいわゆる生育期間については、土の表面が乾燥してきたときのみ、水を少し与えてあげるだけで十分です。冬になると生育がほぼストップするので、乾燥状態になってもすぐに水をあげる必要はありません。2日か3日ほど間隔をあけて水をあげるのがベストです。
次に、肥料について書いていきます。そもそも用土は水はけの良い土を用意してあげてください。その用土と肥料を混ぜてミックスした肥料を使ってあげるとベストです。肥料は腐葉土を使うと良いです。腐葉土だけでも十分ですが、赤玉土を少し混ぜると、より生育に効果的になります。
水はけがあまりよくないようであれば、パーライトを全体の1割程度入れてあげると、水はけが良くなります。生育期間については肥料を月に3回は与えるようにしないといけません。どんどん吸収して花がたくさん咲くので、液体肥料を使うと良いです。種付けについては、株分けをすることで増やすことが一般的なやり方です。
増やし方や害虫について
ガザニア・リンゲスの増やし方と害虫について書いていきます。まずは増やし方について書きます。株分けで増やすことが一般的です。これは行う時期が重要です。植え替えと同時に行うのが一般的ですので、春頃がお勧めです。具体的には3月、4月、5月が適しています。1株につき3芽くらい付くのが理想的です。株分け以外でいうと、さし芽が重要です。
さし芽の時期については、秋頃の9月、10月頃に行う方が良いです。やり方は簡単です。芽の先端部分から少し切り取った茎を使用します。これら以外では種播きで増やすことができます。種まきの時期としては、年間で2回あります。春の4月頃と秋の9月頃の2回です。春に種播きをすると霜よけをする必要がありません。
その一方、秋に種播きをすると苗の状態にもかかわらず冬を迎えてしまいます。そのため、室内で生育する必要があります。したがって、お勧めの時期としては春頃です。ただし、種播きには注意が必要です。ガザニア・リンゲスの種は、嫌光性という性質を持っています。日光に当たってしまうと発芽しなくなります。
そのため、種を播いたあとは、きちんと用土をかけることが大切です。約1週間程度で発芽します。そのあと鉢に移し変えてあげて苗を育てます。そうして十分成長したら庭や植木鉢に植えるとベターです。また、害虫対策もしっかりとしないといけません。たとえば、害虫の代表例としてアブラムシが挙げられます。アブラムシは葉についてそこから植物の液を吸います。発見したら早急に殺虫剤で除去します。
ガザニア・リゲンスの歴史
ガザニア・リゲンスはもともとはアフリカに自生していた植物です。つまり、原産地は南アフリカであって、日本原産の植物ではありません。もともと南アフリカを中心に自生していてその種類は40種類以上あります。南アフリカの植物をヨーロッパに持ち込んで、そこで品種改良しました。いわゆる園芸品種です。
そうした園芸品種が大正時代に日本に渡来しました。このとき渡来して今でも園芸品種として人気のあるものは、ガザニア・リゲンスの他にもガザニア・パボニアやガザニア・リネアリスといった品種があります。また、このガザニア・リゲンスのガザニアという名前はラテン語学者の名前に由来します。
15世紀頃の古代ギリシャの哲学者の著作を主にラテン語に翻訳したラテン語学者のセオドルス・ガザの名前に因んでいます。ガザニア・リゲンスは草丈は15センチから40センチ程度あり、開花時期が5月から10月と非常に幅広いです。さらに、花の色はオレンジがかった色あいをしています。こうした外観が日本人にも受け入れられてきました。
毎年花を咲かせる多年草であるため、年中開花を楽しむことができます。そのため、四季を通して楽しむことができるという利点があり、日本人にも広く親しまれてきました。現在においては、多年草というよりも、一年草として栽培されることの方が多くなりました。このような園芸品種は、時代に応じて栽培方法も変わりますし、楽しみ方も変わります。
ガザニア・リゲンスの特徴
ガザニア・リゲンスの特徴について言及していきます。まずは花言葉から書きます。花言葉は「あなたを誇りに思う」です。植物の分類上は、キク科の多年草です。草丈についてはピンからキリまであります。小さいものであれば15センチ程度ですが、大きいものであれば30センチ程度です。葉については、表も白色であり、裏も白色でどちらも毛が生えています。
葉は全体的に毛が覆われていますので、実際に手で触ったらザラザラしています。大きさは10センチから15センチ程度です。開花時期については、5月から10月頃まで咲きます。原産地については、南アフリカであり、日本原産ではありません。日本への渡来時期については、大正時代です。花の色については、オレンジがかった色合いです。
開花するのは晴れた日中にしか咲きません。基本的には午後までしか咲かないです。日があまり射さない日は、たとえば曇りの場合や大雨が降っているときは、花を閉じます。もちろん、夜間も同様に花弁を閉じます。種類については、豊富にあり16種類程度あり、花の色も豊富にあります。これは園芸品種だから可能になります。
根茎については短く横に這っています。ほとんど上には伸びません。丈夫さについては、高温が苦手です。また、湿気も苦手です。そのため、風通しのよいところを生息地として好みます。種子については、取り扱いに注意が必要です。放置しておくと栄養が取られてしまうからです。
-

-
アカザカズラの育て方
夏になると、近年は省エネが叫ばれ、電力の節約のためにさまざまな工夫がなされます。つる性の草のカーテンもそのひとつだと言え...
-

-
クラウンベッチの育て方
クラウンベッチはヨーロッパが原産であり、ツルの性質を持つ、マメ目マメ科の多年草です。また、日本におけるクラウンベッチの歴...
-

-
シカクマメの育て方
シカクマメは日本でも食されるようになってきましたが、どちらかというと熱帯を原産とする植物です。元々の生息地は東南アジアや...
-

-
アネモネ(モナーク)の育て方
耐寒性も強いため、初心者でもあっても育てやすいのも特徴の花です。開花期が長いというのも、特徴の一つになります。原産地はヨ...
-

-
パキスタキスの育て方
キツネノマゴ科に分類される低木です。樹高は0.5mから1m程度ですが、放置すると2mほどになることもあります。熱帯性なの...
-

-
カリフラワーの育て方
カリフラワーはブロッコリーが突然変異で白くなったもので、原産地は地中海沿岸です。ブロッコリーと同様野生のカンランから派生...
-

-
キングサリの育て方
キングサリの科名は、マメ科 / 属名は、キングサリ属です。キングサリは、ヨーロッパでは古くから知られた植物でした。古代ロ...
-

-
ベニバナの育て方
ベニバナに関しては見ると何の種類か想像しやすい花かも知れません。見た目には小さい菊のように見えます。実際にキクの仲間にな...
-

-
アメリカハナミズキの育て方
アメリカハナミズキの歴史について言及していきます。まず、このアメリカハナミズキは原産地が、その名前からわかるとおり、アメ...
-

-
レイランドヒノキの育て方
この木の種類としてはヒノキ科になります。園芸上の分類としては、庭木、花を楽しむ木、コニファーとしての利用があります。木の...




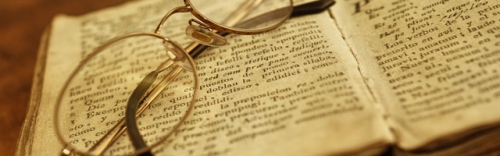





ガザニア・リゲンスの特徴について言及していきます。まずは花言葉から書きます。花言葉は「あなたを誇りに思う」です。植物の分類上は、キク科の多年草です。草丈についてはピンからキリまであります。小さいものであれば15センチ程度ですが、大きいものであれば30センチ程度です。