ヒヨドリジョウゴの育て方

育てる環境について
道を歩いていたり、山を散策していると家で栽培してずっと眺めていたくなるような可愛い植物や珍しい植物をたくさん目にします。実際に切って持って帰って栽培を試みたけれど枯らしてしまったという苦い経験をしたことのある人もいるかもしれません。自然界にはたくさんの野草があるにも関わらず、
これらを家庭で栽培しようとした時にインターネットなどで育て方を検索したところ、意外と情報が少ないことに却って驚かされます。自分で栽培方法を試行錯誤してみたり、ホームセンターや植物園などで専門家にアドバイスを仰ぐなど努力している人もいるでしょう。ヒヨドリジョウゴは元々野生で日本各地に生息している植物なので、
丈夫な植物であることはわかります。他の繊細な植物や野菜のように温度変化や水やりに関してとても気を遣う必要は無いと言えます。つまり、初めての栽培でも成功する確率は高いです。生息はしているものの数が少なくなかなか発見するのが難しい場所もありますが、繁殖しすぎて雑草と同様に駆られて処分されることも珍しくありません。
もし近所に生息している場所を知っているならば、その環境に近い環境を作ってあげるのが一番わかりやすい育て方でしょう。蔓植物なので、葉が周辺にある物に絡みついてどんどん繁殖します。家庭で育てる場合には、何か葉が絡み付くための物を用意してあげ、少し広い場所を用意してあげると良いでしょう。丈夫な植物でも日光や温度、水などに関して極端な無理を強いると期待通りの結果は得られないことがあります。
種付けや水やり、肥料について
道端や山で生息していたヒヨドリジョウゴに魅了されて育てるために実を持ち帰ったことのある人もいるでしょう。持ち帰った時は実だけで育つかどうか半信半疑になりますが、持ち帰った実からもきちんと育てることができます。自然界においても自然の摂理できちんと繁殖しています。自然界では、鳥が実を啄みます。
そして鳥に啄まれた実は鳥の胃の中で消化され、種だけが残り、排泄物として排泄されてまた芽をだすような原理になっています。人間が持ち帰った場合もやはり自然の原理を人間の手で施してやらなければなりません。種だけを取り除きます。持ち帰った実は、水分や果肉が含まれている状態なので、水で洗い流すなどして種を取り出しましょう。
実が赤く成熟しているということはその中の種も成熟している証拠です。取り出したらそのまま蒔いても大丈夫です。実ができるのが秋ぐらいなので種を蒔く時期は大体秋から冬になるでしょう。順調に生育していれば、春には芽吹くはずです。植える土壌の栄養状態を見て肥料を決めましょう。山の土壌はよく肥えている場合が多いです。
家庭栽培用の土に肥料を多くやりすぎた場合、栄養過多となって花や実の付き方に影響を及ぼす恐れがあります。また、水やりに関しても与え過ぎも少なすぎも良くありません。特に花が咲いている時の水やりは花を傷めてしまう場合があるので注意しましょう。できるだけ日に当たる場所で育てるようにし、しばらく様子を見てみましょう。
増やし方や害虫について
ヒヨドリジョウゴの繁殖力はとても凄まじいものがあります。家庭で栽培に成功した場合、嬉しい気持ちや可愛いという感情もあるかもしれませんが、近くにある植物にまで成長が及んでいた場合は隣の植物が押し潰されそうに見えたり、肩幅を狭そうにして佇んでいる姿を見え、可哀そうにさえも感じてきます。
放置していただけでも育つ速さや量は目を見張るものがあります。少し減らそうとして、新しい枝を切ることもできます。その枝を水につけてしばらく様子を見ていると、根が出てきます。その枝を別の場所に植えても良いですし、誰かにプレゼントするのも良いかもしれません。他の植物では病気や虫が気になりますが、
ヒヨドリジョウゴに関しては上記でも述べたとおり非常に丈夫な植物です。害虫や病気の被害に関しても耳にすることはほとんどありません。有毒性植物の中には殺虫剤としてその毒を利用している例もあるようです。それほど強い毒を持っているため、害虫も迂闊に有毒性の植物には近づけないのかもしれません。
一方で、あまり害虫に神経質になり過ぎたら受粉のために一役買っている昆虫がいなくなってしまっては困ります。生育過程に置いて花は咲いたけれど実が付かなかったという人は、色々な原因が考えられますが、その原因の一つとして、受粉に役立つような昆虫がいなかったために受粉できなかったという場合も考えられます。育てやすいので、どこでも誰でも楽しむことができるでしょう。
ヒヨドリジョウゴの歴史
綺麗なバラには棘があるように、見た目はどんなに綺麗な花を咲かせていたり可愛い実を付けていても、有毒の植物も存在します。時々山菜を獲りに山に出かけた人が間違えて有毒の植物を口にして中毒症状を引き起こしたというニュースを見たことのある人もいるでしょう。ヒヨドリジョウゴも見た目に騙されやすい植物だと言えます。
花や実は可愛いですが、毒を含んでいるので気を付けなければなりません。今ほど科学技術や医療が発達していない時代では、道や山に生えている植物を食べ物や薬草に使えないか試行錯誤していました。現代人から見れば、昔の人の知恵や工夫に驚くばかりです。有毒の植物も使い方によっては薬になることを発見し、生活に役立てていました。
日本では万葉集にもヒヨドリジョウゴと考えられる表現があるという意見もありますが、不確かな情報のようです。しかし、少なくとも江戸時代には記録が確認されています。また、江戸時代より以前は異なる名称で呼ばれていたこともわかっています。この植物の原産は東アジアなので、生息地は日本だけではありません。
東洋医学の発展していた中国では古くから医療に用いられていたようです。今では病院に行けば原因は機械等で検査をすればすぐにわかりますが、昔は医者に行かずにそれぞれの症状を和らげるとされる薬草などを選んで服用して済ませる人もたくさんいました。民間療法です。ヒヨドリジョウゴは乾燥させて、解熱をはじめ癌など重い病にまで使うようです。
ヒヨドリジョウゴの特徴
ヒヨドリジョウゴの特徴は外観と有毒性が挙げられます。外観に関して、白い毛が生えています。現物を見た人や写真を見た人の中には、茄子の花に似ていると感じた人もいるかもしれません。この植物は、夏の終わりから秋かけて花を咲かせますが、なす科ナス属に属しているため、茄子の花に似ていると感じるのはごく自然なことです。
また、花の咲き方はとても面白いです。普通の誰もが想像するような植物の花が咲くのとは異なり、花弁が後ろ側に反って中央にある雄蕊と雌蕊だけが残されたような格好になります。他の植物と同様に花が枯れると実を付けます。始めは緑色をしていますが、熟してくると真っ赤になります。
同じ成長過程で育つ野菜や果物はたくさんあるので熟した実はとても美味しそうに見えてしまいます。しかし、ヒヨドリジョウゴのもう一つの特徴である毒を含んでいるので口にするのは危険です。最悪の場合、命を落としかねないような重篤な症状を引き起こすほど強い毒を持っています。毒はこの植物全体に含まれていますが、
特に果実に含まれる毒は強いようです。この毒が引き起こす症状としては、頭痛や吐き気などから運動神経の麻痺や呼吸器系の麻痺など色々あります。適切に処方すれば良い薬にもなりますが、無知の人が取り扱うのはお勧めできません。また、似たような植物もありますが、花の咲き方や毛の様子などヒヨドリジョウゴならではの特徴を知っていれば見分けることができるでしょう。
-

-
シザンサスの育て方
シザンサスはチリが原産の植物です。もとの生息地では一年草、あるいは二年草の草本として生育します。日本にもたらされてからは...
-

-
ヘレボルス・アーグチフォリウスの育て方
特徴としては花の種類として何に該当するかです。まずはキンポウゲ科になります。そしてクリスマスローズ属になっています。属性...
-

-
キンロバイの育て方
キンロバイの科名は、バラ科 / 属名は、キジムシロ属(キンロバイ属 Pentaphylloides)です。キンロバイは漢...
-

-
グロキシニアの育て方
グロキシニアの科名は、イワタバコ科 / 属名は、シンニンギア属となり、和名は、オオイワギリソウ(大岩桐草)といいます。グ...
-

-
グンネラの育て方
グンネラの科名は、グンネラ科 / 属名は、グンネラ属で、和名は、オニブキ(鬼蕗)となります。グンネラ属グンネラは南半球に...
-

-
ドイツアザミの育て方
この花はキク科アザミ属に属します。ドイツとありますが日本原産です。生息地も日本となるでしょう。多年草で、耐寒性があり耐暑...
-

-
レンゲツツジの育て方
この花の特徴は、ビワモドキ亜綱、ツツジ目、ツツジ科、ツツジ属になります。見た目を見てもツツジに非常に近い植物であることが...
-

-
トレニアの育て方
トレニアはインドシナ半島原産の植物で、東南アジア・アフリカなどの熱帯の地域を生息地として約40種が分布しています。属名t...
-

-
ソラマメの育て方
世界で最も古い農作物の一つといわれています。生息地といえば例えば、チグリス・ユーフラテス川の流域では新石器時代から栽培さ...
-

-
ケラトスティグマの育て方
中国西部を原産としているケラトスティグマは明治時代に日本に渡ってきたとされています。ケラトスティグマの科名は、イソマツ科...




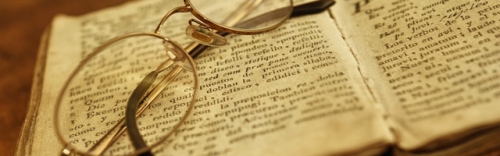





ヒヨドリジョウゴの特徴は外観と有毒性が挙げられます。外観に関して、白い毛が生えています。現物を見た人や写真を見た人の中には、茄子の花に似ていると感じた人もいるかもしれません。この植物は、夏の終わりから秋かけて花を咲かせますが、なす科ナス属に属しているため、茄子の花に似ていると感じるのはごく自然なことです。