レナンキュラスの育て方

育てる環境について
レナンキュラスはヨーロッパが原産であるため、比較的耐寒性があるために露地栽培を可能とする球根植物です。育て方として、花を付ける植物は霜に当たることで生育に影響が出るために霜避け作業または霜が当たらない場所で管理します。球根植物であることから翌年も栽培可能ですが、掘り上げた球根の管理環境としては乾燥させた後に涼しい暗所に貯蔵することにあり、
根腐れを起こす高温多湿な環境下を苦手とするため涼しい暗所が適しています。冬に開花株を手に入れた場合には、昼間は北風が当らない日向に出し、朝や夕方以降は霜が当たらない軒下などの場所で管理することで丈夫に生育しますし、暖かくなる時期にはレナンキュラスも草丈を伸ばし、葉も茂ってくるために蒸れないように風通しの良い環境下で育てます。
茎が細い場合には支柱を立てて茎が折れない工夫も必要です。さらに育て方として露地植えを行う場合には土壌環境も重要であり、酸性の土壌を苦手とする球根植物であるために有機石灰また苦土石灰を予め土に混ぜ、レナンキュラスに適した土壌を作ることも必要です。さらに球根の根腐れを起こしやすいのが水はけの悪さにもあるため、
湿り気のある土壌は適しておらず、さらに枯れた葉や傷んだ花はカビが生えやすく、病気にかかりやすいために株もとは常に清潔に保つことも重要視したい育て方です。高温多湿を苦手とするため、直射日光や雨や霜、さらに北風などの自然の天候には注意して栽培を行います。
種付けや水やり、肥料について
球根植物ですがレナンキュラスの場合には種子から栽培することも可能です。球根は市販されているもの、掘り上げて貯蔵していた球根を使って植え付けを行いますが、乾燥したまま植え付けてしまうことで吸水の割合が一気に高くなり根腐れを起こしやすく、植え付け前には吸水処理が必須となり、軽く湿らせたバーミキュライトに球根を埋めた後、冷蔵庫で1週間程度ゆっくり吸水させます。
球根の植え付けは10月が適期であり、苗の状態では3月が適期です。使用する用土は露地植えでも鉢植えでも、元肥に緩効性化成肥料を与えるのが適していますが、その他にも花植物用の培養土にバーミキュライトを混ぜた用土も適していますし、酸性土壌を苦手とするため、石灰で中和させることも土壌の性質の関係では必要となります。
露地植え付けでは株と株は20cm程度離して植え、5号鉢には3球ほど植えるのが適しています。水やりでは表面の土が乾いていから与えるのが一般的で、開花中も同様ですが、6月頃から葉が黄色く変色し、全ての葉が黄色に変わった後は水やりは完全にストップさせて管理します。肥料についてですが、
不足してしまうと茎が細くなり葉が変色するため、生育中は固形肥料を1ヶ月に1回または液体肥料を1週間に1回程度与えます。水やり同様、休眠期に入る時期には葉が枯れはじめるため、葉の色みを目安に肥料をストップさせますが、この行為は土に肥料が残ったままでは根腐れを起こすためです。
増やし方や害虫について
育てる上で大きくなった球根を分球することで増やすことが可能で、分球の適期は5月から6月となります。葉が枯れた後に掘り上げて葉や土を取り除き、球根を洗浄して分球させ、陰干しを行います。増やす場合に気をつけたいのがウイルス病の株を分球してしまうケースです。生育時期にモザイク状の色の葉を発見した場合、
その株は病気を発症しているため、分球させずに処分します。さらに分ける場合には球根の付け根に短毛が生えており、レナンキュラスの発芽はこの部分から出るために、分ける際は芽部を付けて分けます。乾燥している球根はバーミキュライトに植えて冷蔵庫で給水させますが、1週間程度のゆっくりした給水が必要ですが、
早急に植え付けたい場合には2日程度の給水でも発芽を促すことは可能です。さらにレナンキュラスはタネからも増やすことができ、発芽温度が20度を越えてしまうと発芽しないため、栽培の難易度が非常に高く、分球が適しています。さらに育てる際には病害虫にも気を配る必要があり、灰色カビ病は株もとを清潔に保つことで予防でき、
害虫にはアブラムシまたハモグリバエが発生します。それぞれ発生する時期が異なり、アブラムシは5月から10月、ハモグリバエは3月から5月まで発生し、蕾や葉につき吸汁し、葉の変色や枯れ、またウイルスなどの病気に侵されやすいため、薬剤を散布して駆除する他、幼虫が葉を移動するため、見つけ次第潰して駆除する方法が適しています。
レナンキュラスの歴史
レナンキュラスはキンポウゲ科・キンポウゲ属に分類され、Ranunculusasiaticsの学名を持ち、ヨーロッパを原産地とし、和名にハナキンポウゲと言う名を持っています。耐寒性のある多年草であるレナンキュラスの由来となるのがラテン語のカエルを意味するラナから来ており、葉っぱの形がカエルの足に似ていることからその名が付けられています。
栽培されるようになった歴史は古く、ヨーロッパに十字軍が球根を持ち込み、改良された後18世紀頃から盛んに栽培されはじめています。18世紀頃にはターバン系となる八重咲き種が栽培されており、その他ペルシア系は現在栽培されている園芸種の原種と言われています。20世紀以降には日本にも普及され、生息地も世界に広がり、
日本で改良されたレナンキュラスも存在しており、ビクトリアストレインは大輪で花色もバリエーション豊富で近年の園芸種の中で人気の高い品種です。鉢植えでの栽培に向いており、色柄も多種多様に揃う中でも幾重に重なる花弁は古くから変わらず、観賞用としてまた切り花として栽培されています。主な生息地としては、
ヨーロッパ南東部から中近東にかけての地中海性の地域であり、その大輪の花はクラフトとしても利用される以外にも有名な絵画にも取り上げられるなど見応えのある植物として古くから人気の高い品種であり、キンポウゲ属は約500種もあり、現在では香りや花形の改良が進められています。
レナンキュラスの特徴
中近東からヨーロッパにかけてが原産地である多種多様な品種を揃えるレナンキュラスの最大の特徴は、花色と花型です。花色には白をはじめ、赤・黄・ピンク・オレンジなどから、近年ではフラワーアレンジメント向けとなる品種改良された紫・緑などの花色も普及していますし、さらに花弁では紙のように薄い花弁が幾重にも重なる八重咲や一重のもの、
花弁が丸まるカール咲きなどの品種もあります。花の色が豊富であるのは他の球根植物には見られない魅力であり、一番花だけでなく蕾が次々に膨らむため、長い期間楽しめる植物です。さらに球根植物でありその特徴となるのが、1個の球根から花茎が5本から20本近く立ち上がった後に数輪の花が付く点で、大輪種であれば直径は15cm程度にもなる大きさも特徴的ですし、もちろん、蕾自体も大きくて円錐に似た形です。
葉は品種によって3つに裂け、裂片も羽状に切れ込みが入っている葉や、上記でも挙げた通りにカエルの足に似ている葉形などがあります。夏から葉などが枯れ、球根だけが残るのですがその根は太く、肥大した塊根であり、球根のてっぺんは発芽のための短毛で被われています。
さらにレナンキュラスの球根は6月頃に一旦掘り上げて乾燥させた状態で保管また市販されており、植え付けの特徴としては水を給水させて球根をもどすことにあります。乾燥状態のまま植え付けを行うことで、根腐れを起こすリスクを水でもどす作業で減らすことが可能であり、育てる上での特徴と言えます。
-

-
ハクサンイチゲの育て方
花の高さは約15センチから30センチで、上記でも述べたように大群落をつくります。その姿は絨毯を敷き詰めたようで圧巻です。...
-

-
トリテレイアの育て方
トリテレイアは、ユリ科に属する球根性の多年生植物で、かつてはブローディアとも呼ばれていました。多年生植物というのは、個体...
-

-
ネモフィラの育て方
北アメリカで10数種類以上分布し、花が咲いた後に枯れる一年草です。草丈はあまり高くなることはないのですが、細かく枝分かれ...
-

-
レモン類の育て方
レモンと言えば黄色くて酸っぱいフルーツです。レモン類には、ライムやシトロンなどがあります。ミカン科、ミカン属になっており...
-

-
キワーノの育て方
キワーノはウリ科でつる性の植物です。名前については企業の商標登録によってつけられたものですのでこれが正式な名称ではないよ...
-

-
セッコクの育て方
セッコクは単子葉植物ラン科の植物で日本の中部以南に分布しています。主な生息地は岩の上や大木で、土壌に根を下ろさず、他の木...
-

-
レンズマメの育て方
レンズマメは、マメ科ヒラマメ属の一年草、およびその種子です。和名は、ヒラマメ(扁豆)で、学名はLensculinaris...
-

-
トリフォリウムの育て方
トリフォリウムは分類上はシロツメクサやクローバーの仲間であり北半球だけで300種類ほどが分布しています。日本においてはシ...
-

-
ひまわりの育て方
ひまわりはきく科に属し、日輪草(ニチリンソウ)や日車(ヒグルマ)と言う別名を持ちこれは、ひまわりが日輪のように見えること...
-

-
ラケナリアの育て方
特徴としてはまずは分類があります。キジカクシ科とされることがあります。その他ユリ科、ヒアシンス科とされることもあります。...




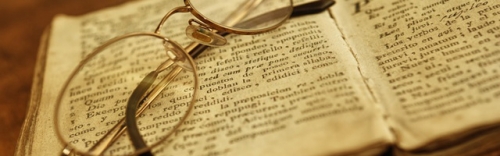





レナンキュラスはキンポウゲ科・キンポウゲ属に分類され、Ranunculusasiaticsの学名を持ち、ヨーロッパを原産地とし、和名にハナキンポウゲと言う名を持っています。耐寒性のある多年草であるレナンキュラスの由来となるのがラテン語のカエルを意味するラナから来ており、葉っぱの形がカエルの足に似ていることからその名が付けられています。