マツの育て方

種付けや水やり、肥料について
マツは盆栽として育てる方も大変多くいらっしゃいますが、庭などへ種付けされる方もいらっしゃいます。植え付けをおこなう場合は日光があたる場所を選びましょう。どちらかというと土壌がやせていても育てやすい植物ですが、日陰では弱ってしまったり葉の色が悪くなってしまう可能性があります。
ですので、日当りや水はけのよい土壌で育てるようにしてください。植え付けをおこなうのに適しているシーズンは2月頃から4月頃だとされています。土を掘る場合には、根鉢の2倍の深さが必要になります。十分に水を注いで根の部分と土を馴染ませていきましょう。
マツの育て方として大切なポイントとして水やりがありますが、鉢植えの場合でも庭植えの場合でも植え付けをおこなってから2年くらいまでは土の表面が乾いてしまわないように注意が必要です。土の表面が乾いてきたと感じたら十分に水をあげるようにしてあげてください。
植え付けをおこなってから2年以上経っている株に対しては、特に頻繁に水やりをする必要はありません。庭植えをおこなった場合の肥料は、1月頃に株元の周辺に埋めるようにしておきます。鉢植えをした場合の肥料のやり方は、固形の有機質肥料などを株元に追肥していきます。
病気や害虫について
マツを育てていく時に注意したい病気がすす病です。枝葉などが黒っぽくなってしまう病気なのですが、これはカイガラムシやアブラムシなどの排泄物などが体積することによってカビが発生していることが原因です。すす病になっている枝葉は光合成をすることができませんし美しくありません。
ですので、殺虫剤などを使用して対処しましょう。害虫に多いのは、マツノマダラカミキリやカイガラムシ、マツカレハ、マツヤドリハダニなどが挙げられます。マツノザイセンチュウを媒介することによってマツを枯らしてしまいます。幹などに卵があるのを放置していると5月中旬頃には成虫になって、
6月頃から9月頃には若い枝を食害してしまいます。カイガラムシは樹液を吸うため樹勢が失われて弱ってしまいます。アブラムシが発生してしまった場合には、枯れてしまった枝などを取り除くなどの対処をしましょう。マツカレハなども食害しますので害虫駆除が必要です。
マツの剪定と樹形の調整について
マツは一般的に春頃になると緑摘みがおこなわれ、秋頃にはもみ上げと呼ばれている作業がおこなわれます。実際にはこまめにお手入れをすることが難しいという方も多いですので、年に一度おこなうのであれば秋頃がおすすめされています。冬におこなうとダメージを与えてしまいますので冬になる前におこなうようにしてください。
マツの剪定作業中に付着してしまう松脂は洗濯をしても落とすことが難しいため、作業をおこなう際の服装は前もって汚れても問題ない作業着を準備しておきましょう。庭に植えられている大きなマツの場合は、職人さんにお任せされている方が多いです。
剪定をおこなわない場合に樹形を整えるために緑摘みをおこないます。葉がまだ出ていない4月頃から5月頃に折って取り除いていくことがおすすめです。このシーズンに取り除いても夏頃になると成長してきますがそれほど長くはなりません。
もみあげという作業は、夏に伸びてしまっている枝を減らしていくのが目的です。10月頃から翌年の3月上旬に古い葉や多過ぎる新しい葉をむしり取っていきます。枝を整理してすっきりさせて下枝の方にも日光があたるようにしてあげましょう。
ふやし方について
マツのふやし方としては、秋頃に種を採取して乾燥させないように保存しておきます。2月から3月頃に保存しておいた種をまいてふやす方法が一般家庭などでは主流となっています。種まきは重ならないように間隔をおいてまいていき、種が隠れる程度に土を被せていきます。土の表面が乾燥してしまわないように水やりをおこなって育てていけば春頃には発芽します。
盆栽の育て方
趣味の一つとして盆栽として栽培されていらっしゃる方も多いですが、育てる場合には日当りのよい場所が好ましいです。盆栽というのは、草木などを鉢に植えて姿全体を鑑賞するもので、肥料や剪定、針金掛けなどの手間ひまをかけて作っていきます。
針金というのは休眠中におこなわれているのですが、太い幹などを曲げたいというような時におこなわれています。2月くらいから始めて針金は半年から1年ほどかけっぱなしにしておきます。枝ぶりや葉姿、幹の肌などを鑑賞します。
盆栽には樹齢100年から300年以上のものなどもあります。半日陰でも問題はありませんが、基本的に室外の風通しのよいところに置くようにしてください。冬のシーズンには霜が心配ですので日当りに注意するようにしましょう。水やりの頻度は、春頃や秋頃の比較的涼しいシーズンは1日に1回ほどで大丈夫です。
真夏は乾きやすいですので1日に2回ほど水やりをすることがおすすめです。逆に冬は毎日水やりをする必要はなく3日に1回くらいで問題ないとされています。4月頃から9月頃の間に1度有機性の肥料を置いておきましょう。害虫に関しても春から秋頃にかけて4回ほど専用の殺虫剤を散布しておくことがおすすめです。
マツの歴史
マツ属はマツ科の属の一つで、原産はインドネシアから北側はロシアやカナダなどが挙げられます。大部分が生息地として北半球にありますが、近年ではオーストラリアやニュージーランドなどでもラジアータパインと呼ばれている種類が生息しています。
マツは化石の研究によって古い時代からあったとされています。日本国内でも庭木や庭園などで多く見られますが種類は大変多く、葉に模様が入っている品種なども改良されて植えられています。美しい景観を作り出すために、街路樹として用いられることもあります。
これらは2葉ですが3葉にはアメリカ大陸を中心として分布しているテーダマツやダイオウマツなどが知られています。5葉にはヒメコマツやチョウセンゴヨウなどがあります。日本国内には3葉のものは自生していませんが、化石の研究によってオオミツバマツという種類が分布していたことが確認されています。
第二次世界大戦中などには松脂を採取して松根油を採取することで航空機の燃料などに利用しようとしていました。松の実は食用として利用されています。松脂を上流した成分は粘着剤や生薬、香料などさまざまな用途として利用されてきたとされています。
マツの特徴
マツの樹高は10メートルから40メートルほどまで大きくなる種類まであります。アカマツやクロマツなどのような温帯地域に生息している種類は、一般的に春先から初夏にかけて枝が一節ずつ伸びていくとされています。夏頃になると成長が止まるような種類があります。
特に亜熱帯地域に分布しているような種類は1年間に多節成長するものがあります。アカマツは大きいものは高さが50メートルほどにまでなり、樹皮が赤褐色や黄色みの赤褐色です。葉は2枚ずつついて針状で細長いという特徴があります。樹脂道が3個から9個ほどあり下表皮に接して存在しています。
開花は4月頃で雄花は新枝の下部に多数つけるのですが、形は円筒状で緑っぽい黄色です。雌花の場合は新枝に2、3個付いて色は紅紫色です。成熟していくと淡黄褐色になります。クロマツは、日本や韓国の海岸辺りに自生し、樹高は40メートルほどに成長するケースもあります。
アカマツと比較してみると樹皮が黒っぽくて雄松とも呼ばれています。塩害に強いという特徴を持っていることから、街路樹や防潮林として利用されたり浜などに植えられていることがあります。また盆栽用としても利用されています。
庭木の育て方や色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も参考になります♪
タイトル:トウヒの仲間の育て方
タイトル:ナツツバキの育て方
タイトル:ハナモモの育て方
-

-
初心者でもできる、へちまの育て方
へちま水や、へちまたわし等、小学校の時にだいたいの方はへちまの栽培をしたことがあると思います。最近は夏の日除け、室温対策...
-

-
ほうれん草の育て方
中央アジアから西アジアの地域を原産地とするほうれん草が、初めて栽培されたのはアジア地方だと言われています。中世紀末にはア...
-

-
シモバシラの育て方
学名はKeiskeaJaponicaであり、シソ科シモバシラ属に分類される宿根草がシモバシラと呼ばれる山野草であり、別名...
-

-
ライスフラワーの育て方
ライスフラワーの特徴として、種類としてはキク科、ヘリクリサム属になります。常緑低木です。草丈としては30センチぐらいから...
-

-
ヌスビトハギの育て方
ヌスビトハギの仲間はいろいろ実在していて、種類ごとに持っている特質などに違いが見られ、また亜種も実在しています。例に出し...
-

-
バニラ(Vanilla planifolia)の育て方
バニラは古くから香料として用いられていました。現在でもアイスクリームの香料などに用いられていますが、その歴史は非常に古い...
-

-
ウツボグサの育て方
中国北部〜朝鮮半島、日本列島が原産のシソ科の植物です。紫色の小さな花がポツポツと咲くのが特徴です。漢方医学では「夏枯草」...
-

-
ウェストリンギアの育て方
シソ科・ウエストリンギア属に分類され、別名にオーストラリアンローズマリーの名前を持つ低木がウェストリンギアです。別名にあ...
-

-
ヒメシャラの育て方
ヒメシャラはナツツバキ属のうちのひとつです。日本ではナツツバキをシャラノキ(沙羅樹)と呼んでおり、似ていますがそれより小...
-

-
トマトの育て方について
自宅の庭に花が咲く植物を植えてキレイなフラワーガーデンを作るというのも一つの方法ですが、日常的に使う野菜を栽培することが...






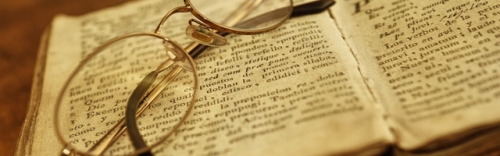





マツ属はマツ科の属の一つで、原産はインドネシアから北側はロシアやカナダなどが挙げられます。大部分が生息地として北半球にありますが、近年ではオーストラリアやニュージーランドなどでもラジアータパインと呼ばれている種類が生息しています。