トケイソウの仲間の育て方

トケイソウの仲間の育てる環境について
トケイソウの仲間は熱帯地方が原産なので、好む環境も高温でやや乾燥した場所が基本となります。ただし種類が多いため、育て方に微妙な違いがあります。どの種もだいたい暑さには強く、真夏の西日を浴びても大丈夫です。一年を通じて、日当たりが良い場所を好みます。
日陰ではまったく育たないということはありませんが、日照時間が不足していると、つるが間延びして弱くなります。また花の数や色形が劣ることもあります。少なくとも春から秋にかけては、できれば毎日5時間以上、直射日光に当ててやりたいところです。
ただし鉢植えにしているなら、花が咲いているときは部屋の中に置いても構いません。寒さに対しては、種によって耐性がかなり異なります。真っ白な花が美しいコンスタンスエリオット、派手な赤紫のまだら模様を特徴とするレッドインカなどは、寒さに強い種として知られています。
これらは屋外で冬越しが可能で、マイナス15度でも枯れないとされています。庭に植えてある場合は、冬には日当たりもあまり必要としません。しかし一般的なトケイソウの仲間は、霜が降りると枯れることが多いため、冬場は室内やベランダに置いて、
零度を下回らないように注意します。シックな紫色のライラックレディ、青紫の園芸品種ベロッティーなどがこれに該当します。近年では地球温暖化のせいもあって、戸外で冬越しさせている例も見かけますが、鉢植えは屋内に入れたほうが安全でしょう。
種付けや水やり、肥料について
植え付けをするなら、水はけの良い土が第一の条件になります。ずっと土が湿ったままだと、根腐れを起こしてしまいます。一般的には赤玉土7に対して腐葉土3の割合で混ぜた土を使用します。肥えた土が好ましいものの、水はけが良ければ他の条件はあまり気にする必要はありません。
トケイソウの仲間は園芸店などでは苗の形で販売されていることが多いですが、種から育てることもできます。種まきの時期は4~6月、または9~10月です。おおむね20度~30度が発芽の適温とされています。入手した種は冷暗所に保管し、できるだけ早めに蒔くことをお勧めします。
春から秋にかけては生育期となるため、土が乾燥したら十分な水を与えます。特に鉢植えにしている場合は、水切れを起こしやすくなります。水切れはつぼみが落ちる原因になります。ただし水の与えすぎにも注意しなければなりません。土の表面が乾燥してから水やりをするのがコツです。
晩秋から冬にかけては、トケイソウの根はほとんど活動しなくなります。ですから水やりも控えめにして、土を乾燥気味に保つ必要があります。庭にしっかりと根付いているなら、冬は特に水を与えなくてよいぐらいです。
肥料は春から秋の生育期に、緩効性の固形肥料を、2か月に1回程度を目安として与えます。または液体肥料を1か月に2~3回ほど与えても構いません。この場合は剪定のタイミングと合わせると良いでしょう。冬季は肥料を与えません。
増やし方や害虫について
トケイソウの仲間は挿し木で増やすこともできます。新しく元気なつるを2~3節の長さに切り、土に挿してたっぷりと水を与えます。時期は初夏が適当です。つるの成長が早いことは、トケイソウの仲間の特徴です。放っておくと絡み合って見苦しくなり、
また花つきが悪くなることもあるため、適当な時期に剪定が必要です。基本的には3月~4月ごろ、つるの切り戻しを行ないます。支柱に絡みついた部分をほどき、枯れ葉や巻きひげなどを整理してから、地上から1mほどのところで切ってしまいます。
このとき節のすぐ上で切ると、新しいつるが生えやすく、それだけ花の数も増えます。ただし短く切りすぎると、新芽が出ないこともあるため注意してください。そのほか春から夏の気温の高い時期なら、いつでも剪定して構いません。
しかし花芽はつるの先端に付くので、つるを切ると花が咲かなくなることもあります。切り戻した後は、つるを支柱などに誘引します。つるはすぐに伸びるので、勝手な場所へ伸びていかないよう、何度も誘引する必要があります。トケイソウの仲間は病気や害虫には強いほうですが、
枝や葉が混みあうと、害虫の被害が拡大する可能性があります。初夏から夏にはハダニが発生し、新芽にはアブラムシやカイガラムシが付くこともあります。これらへの対策としては、殺虫殺菌剤を使用するとともに、適切に剪定を行ない枯れ葉などを取り除いて、風通しよく清潔に保つことが大切です。
トケイソウの仲間の歴史
トケイソウの仲間は中央アメリカから南アメリカにかけてが原産地とされています。生息地は熱帯地域が中心で、現在では世界中に数百種類が分布しています。英語ではパッションフラワーと呼び、果物のパッションフルーツもトケイソウの仲間です。
このパッションは「情熱」の意味ではなく、イエス・キリストの「受難」を意味します。ヨーロッパに紹介されたのは16世紀のことです。南米へ布教に出かけたイエズス会の宣教師が、この花を現地で発見し、「キリストの受難の花」と名づけました。
一説によれば、雌しべや雄しべを十字架と釘、副花冠をイバラの冠、花びらとがくを10人の使徒などに喩え、キリストの磔刑に見立てたものとされています。そして、この花をキリスト教の布教に利用しました。日本には18世紀前半の享保年間に初めて持ち込まれました。
それはパッシフローラ・カエルレアという種で、10cmほどの赤や青の花弁と紫色の副花冠を持ちます。また現在でも日本語でトケイソウといえば、この種を指すのが一般的になっています。トケイソウの名前は、花の形が文字どおり時計に似ているためで、
花弁と副花冠を文字盤に、先端が3つに分かれた雌しべを針になぞらえています。花の色や形が個性的で美しいため、今では世界中で園芸植物として栽培されています。またパッションフルーツをはじめ、オオナガミクダモノトケイソウやブラジルトケイソウなど、食用として栽培される品種もあります。
トケイソウの仲間の特徴
トケイソウの仲間は観賞用や食用として盛んに栽培され、掛け合わされてきた結果、きわめて多種多様な色や形のものが存在します。それらは大まかに、パッシフローラ・デカロバ・デイダミオイデス・アストロフェアの4亜属に分類されます。パッシフローラは属名にもなっています。
パッシフローラとデカロバはつる性植物で、一般にトケイソウといえば、この2亜属を指します。ある種のトケイソウの仲間は、がくが花びら状になっており、色違いの2種類の花びらがあるように見えます。また花びらの内側に副花冠を持っているのが特徴です。
トケイソウの副花冠は花弁と同様バリエーションに富み、長いヒゲ状になっていたり筒状になっていたりします。色も花弁と違っていたりするので、さらに花の面白さが際立っています。トケイソウの仲間は巻きひげで支柱に絡みつき、つるを伸ばしていく性質があります。
旺盛な生育力を持っているため、壁一面に這わせて緑のカーテンを作るのにも利用されます。花だけでなく葉の形にも多様な種類があり、好みのものを選ぶことができます。ただし形よく仕上げるには、こまめな剪定作業が大切になります。
生食用のパッションフルーツは、正式にはクダモノトケイソウと呼ばれます。甘酸っぱい味に特徴があり、トロピカルジュースなどにも好んで用いられます。また乱れた神経を鎮め、痛みを緩和する作用があるとされ、精神不安や更年期障害に効くハーブとして用いられることもあります。
緑のカーテンの育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:ヘデラの育て方
-

-
カラミンサ・ネペタの育て方
カラミンサ・ネペタはレッサー・キャットミント、レッサー・カラミントなどとも呼ばれる南ヨーロッパ原産のシソ科の芳香性多年草...
-

-
モモ(桃)の育て方
桃はよく庭などに園芸用やガーデニングとして植えられていたりしますし、商業用としても栽培されている植物ですので、とても馴染...
-

-
ガーデンシクラメンの育て方
シクラメンの原産はトルコからイスラエルのあたりです。現在でも原種の生息地となっていて、受粉後に花がらせん状になることから...
-

-
ジャカランダの育て方
ジャカランダは世界三大花木の一つとして知られており、日本では数多くあるジャカランダの品種の内の一部が栽培されています。日...
-

-
アカンサスの育て方
アカンサスはキツネノマゴ科アカンサス属またはハアザミ属の植物で、別名をギザギザの葉がアザミの葉に似ていることから和名を葉...
-

-
ゴメザの育て方
ブラジル原産のラン科の植物です。属名がなんども変えられた歴史を持っています。最初はSigmatostalix(シグマトス...
-

-
植物や果物を育ててみませんか
仕事や行事などで毎日が忙しく、たまに休みがあったとしてもやりたい趣味活動がなかなかないという人も最近ではよく見かけること...
-

-
フェイジョアの育て方
フェイジョアは1890年にフランス人の植物学者であるエドアールアンドレによってヨーロッパにもたらされた果樹です。元々は原...
-

-
カロライナジャスミンの育て方
カロライナジャスミンは、北アメリカの南部から、グアテマラが原産の、つるで伸びていく植物です。ジャスミンといえば、ジャスミ...
-

-
ナナカマドの仲間の育て方
ナナカマドの仲間は、バラ科の落葉高木で、学名がSorbuscommixta、漢字で「七竈」と書きます。「庭七竈」は、学名...




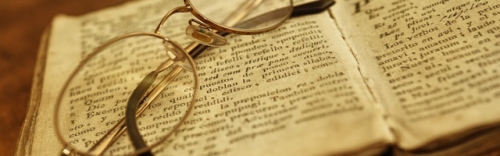





トケイソウの仲間は中央アメリカから南アメリカにかけてが原産地とされています。生息地は熱帯地域が中心で、現在では世界中に数百種類が分布しています。英語ではパッションフラワーと呼び、果物のパッションフルーツもトケイソウの仲間です。