イヌツゲの育て方

イヌツゲの育てる環境について
イヌツゲは耐寒性と耐暑性が備わっていますので、場所を選ばずに広い応用が利く庭木です。日本国内であれば、九州から東北まで、広い範囲で容易に栽培できます。初心者でも育て方に困ることがなく、地植えにしておけば自然の雨水だけでも充分に生育していきます。
ただし、成長が早いので、剪定しないまま放置し続けてしまうと、高木になってしまいます。高さが10メートルを越えることもありますので、庭木として植える際には、電線に触れてしまわないように配慮することも重要です。適切な剪定を定期的に行うことで、
低木として維持できるように栽培するのが理想的と言えます。どのような土壌であっても、適応力が高いのも特徴です。湿度の高い土壌であっても、乾燥しやすい土壌であっても、適応しながら成長していきます。どのような土壌なのかを考慮しながら剪定をすると、
病害虫の被害が少なくなります。もしも湿度の高い土壌であれば、風通しが良くなるように透かし剪定を行うと良いでしょう。排水性が高くて乾燥しやすい土壌であれば、刈り込み剪定を行うと良いでしょう。刈り込み剪定で仕立てると、葉が密集してきて美しく仕上がります。
強い生命力を感じさせる木なので、幹線道路沿いや自動車の排気ガスが多い地域でも、安心して栽培できます。道路沿いの敷地であれば、生垣として栽培することで、排気ガス対策にもなり、庭の空気に清潔感が備わるように感じられます。日当たりが良いのが理想的ですが、半日陰でも安心して栽培できます。
イヌツゲの種付けや水やり、肥料について
イヌツゲには黒い果実が付きますから、採取しておくと種子として利用できます。秋から冬にかけて黒い果実を種子として採取しておき、春に蒔くのが理想的です。種子は発芽しやすく、小さいうちは鉢植えや盆栽として楽しむこともできます。
水やりは、意識的に行わなくても良いので、自然の雨水に任せておくと良いでしょう。土壌が湿りがちか乾燥しがちかに関わらず、水やりを行わなくても育ちますが、肥料は適切に与えると良いでしょう。土壌そのものが肥沃で栄養が多く含まれていれば問題ないのですが、
イヌツゲは成長が早くて葉が芽吹く力が強い木ですから、地中から多くの養分を吸収しています。冬季の間に、寒肥と呼ばれる方法で、堆肥を与えておくと良いでしょう。株元に腐葉土を撒いておくのも良い方法です。化成肥料でも大丈夫ですが、化成肥料の場合は株元の地中に混ぜておくと吸収がスムーズです。
花がたくさん咲いた場合は、梅雨明け頃にも肥料をあげると良いでしょう。ただし腐葉土を夏に撒いてしまうと、虫が繁殖してしまうこともあるため、夏は化成肥料のみにしたほうが良いでしょう。鉢植えや盆栽で栽培している場合は、春先に追肥と呼ばれている方法で肥料をあげます。
イヌツゲはアルカリ性の土壌を好む性質もありますので、株元に苦土石灰を混ぜておくというのも良い方法です。苦土石灰は肥料ではないものの、イヌツゲの葉のつやが美しくなる効果が高まりますし、冬の落葉防止効果を高めることができます。常緑性ですが、栄養不足になると冬に落葉してしまうことがあるからです。
イヌツゲの増やし方や害虫について
イヌツゲは挿し木で増やすことができます。挿し木のポイントは、その年に伸びた新しい枝を利用することです。季節は夏が最適です。湿度の高い梅雨の時期でも、乾燥して高温になりやすい真夏でも大丈夫です。挿し木に利用する枝を選ぶポイントは、勢いが良いことと、しっかりと固く育っていることです。
長さを10センチメートルほどに切り、切ってから30分たっぷりと水を吸わせます。水を吸わせてから土に挿すことで、発根の成功率が高まります。発根は一ヶ月ほどで始まりますが、最初の二年間ほどは成長がゆっくりです。鉢植えとして楽しむのも良いでしょう。
イヌツゲで気をつけたいのがカイガラムシです。生命力の強い木であり、害虫や病気にも強いのですが、カイガラムシが繁殖してしまうと、すす病が発生してしまうことがあります。カイガラムシ対策は、葉の表面がべったりしてきたようになってしまったら、葉ごと除去することです。
カイガラムシの被害が大きい場合は、透かし剪定を行うと良いでょう。風通しを良くすることで、カイガラムシの繁殖予防の効果が得られるからです。ハマキムシが発生することもあります。カイガラムシもハマキムシも、初夏から梅雨の時期に発生しやすいのが特徴です。
害虫の発生は、葉にダメージを与えることで、光合成を阻害しますので、できるだけ幼虫の時期に駆除するのが理想的です。木の成長が早いので、害虫の被害に応じて枝ごと切って除去するのも良い方法です。薬剤を散布する方法もあります。
イヌツゲの歴史
イヌツゲはモチノキ科のモチノキ属の常緑性の木です。一般的には庭木に活用されていることが多いため、低木で知られていますが、放置していると高木になることもあります。原産は日本と朝鮮半島南部です。日本での生息地は、九州から本州まで広い分布となっており、
朝鮮半島南部に位置する済州島も生息地として知られています。和名は犬黄楊で、イヌツゲと読みます。和名の由来には、柘植に似ているが、建材や木材としては劣るものという意味が込められています。柘植はツゲと読み、髪を梳かす櫛の原料となる木です。
ツゲはツゲ科の植物ですから、まったく別の植物です。イヌという言葉には、劣るという意味があります。ツゲは日本の古典文学である万葉集や源氏物語にも登場する有名な木ですが、イヌツゲはツゲに似ているものの、江戸時代以降になってから園芸用として親しまれるようになりました。
さらにモチノキ科の植物ということもあり、トリモチを採取することにも長い間にわたって利用されてきました。トリモチとは、鳥を採取するときに用いるゴム状のものであり、木の枝に塗っておいて鳥が止まって付いたら離れられなくなるものですが、現在では使用が禁止されています。
狩猟禁止の鳥も捕獲してしまうことがあるからです。現在では、主に日本庭園での仕立て園芸に親しまれることが多いです。仕立てが容易であり、生育も早いことから生垣として利用されることもあります。幅広い仕立てが可能であり、職人でなくても上手に剪定することが可能です。
イヌツゲの特徴
イヌツゲは常緑性の木で、こまめに刈り込んで剪定するのに最適な木です。成長がとても早いので、生垣としても利用しやすく、刈り込めば刈り込むほど、葉が密な状態になります。葉は楕円形です。葉の縁は、丸みを帯びたノコギリ歯になっています。
枝は灰色がかった色をしており、常緑性の葉の緑色を、落ち着いた雰囲気に引き立てます。日本庭園に好まれるのも、落ち着いた雰囲気が重要なポイントになっています。イヌツゲは雌雄異株であり、雄株と雌株に分かれているのも特徴です。葉は互生なので、互い違いに並びながら育ちます。
日本では初夏から梅雨にかけての季節に、花が咲きます。花は小さく、白いですが、やや紫色もしくは黄色がかって見えます。小さな花が、たくさん咲くことで、控えめながら美しい眺めを楽しむことができます。花が咲き終わると、雌株に果実がつきます。
果実は小さな粒状の球形であり、成熟してくると秋には黒い果実になります。なお、成長が早いのは雄株のほうです。花や実を楽しむ庭木には雌株のほうを、生垣には成長が早い雄株のほうが選ばれることが多いのも特徴です。
丸く仕立てられると、とても柔らかな雰囲気を醸し出すのですが、葉は、見た目の印象よりも、やや硬めです。日本海側の積雪する地方では、地面を這うように生育するタイプも存在します。耐寒性が強く、耐暑性も強いです。
初心者でも栽培しやすい木です。春から秋にかけての長い期間にわたり剪定することが可能ですが、真夏の直射日光に新芽が焼けてしまうこともあるので、日当たりを考慮して剪定すると良いでしょう。
庭木の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:ソヨゴの育て方
タイトル:イチイの仲間の育て方
タイトル:カエデ類の育て方
-

-
メギの育て方
メギはメギ科メギ属の仲間に入るもので、垣根によく利用される背の低い植物です。メギ属はアルカロイドという成分を含んだ種類が...
-

-
ホタルブクロの育て方
ホタルブクロの特徴として、まずはキキョウ目、キキョウ科であることです。花の色としては真っ白のものがよく知られていますが、...
-

-
ベンジャミン(Ficus benjamina)の育て方
ベンジャミンの原産地はインドや東南アジアです。クワ科イチジク属に分類されている常食高木で、観葉植物として人気があります。...
-

-
グラマトフィラムの育て方
グラマトフィラムの原産は東南アジアで、暑い地域の植物です。生息地では12種の原種があります。洋蘭の一種で、熱帯からヨーロ...
-

-
コバイモの育て方
コバイモは本州中部から近畿地方の山地に多く自生している植物で、原産国としては日本であるとされているのですが、その生息地は...
-

-
ナンバンギセルの育て方
ナンバンギセルはハマウツボ科でナンバンギゼル属に属し、別名がオモイグサと呼ばれています。原産地は東アジアから東南アジア、...
-

-
オルキスの育て方
このような面白い形の植物は、ラン科に多いのですが、やはりこのオルキス・イタリカもランの一種で、オルキスとはランのことで、...
-

-
コケ類の育て方
特徴としては乾燥にも強く様々な環境の中で生きていく力が他の植物よりも強いところがあげられます。光と水だけで育成できること...
-

-
ヘミグラフィスの育て方
特徴としてはキツネノマゴ科の植物になります。和名としてはその他にはヒロはサギゴケ、イセハナビと呼ばれることがあります。葉...
-

-
バラ(ピュア)の育て方
その特徴といえば、たくさんありますが、特徴を挙げるとすれば、その香りが最大の特徴ではないかと考えられます。もし、いくら花...




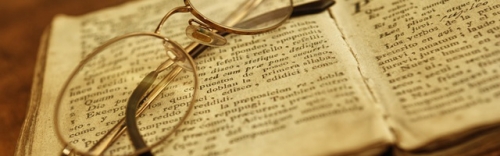





イヌツゲはモチノキ科のモチノキ属の常緑性の木です。一般的には庭木に活用されていることが多いため、低木で知られていますが、放置していると高木になることもあります。原産は日本と朝鮮半島南部です。