モロヘイヤの育て方

育てる環境について
また盛んに食べられているエジプトでは、この植物専用の包丁まであったそうです。日本ではさすがに新しい野菜で、1980年代から知られるようになり、ビタミンやミネラルが豊富で、アフリカ原産でもわかるように栽培しても非常に強い野菜なので、日本の気候でも、育てることができるということでも人気が出てきています。
家庭菜園やガーデニングでも試してみると良い植物ではないかということになります。この植物の食べるところは若葉、茎で、旬はアフリカの植物ですので、やはり日本でも夏ということになります。植物自体の背の高さも50センチぐらいですので、観葉植物ということでも、ちょうど良い大きさではないかという感じです。葉は長い楕円形で、先が尖っています。
日本の植物ではホウレンソウなどの葉を食べる野菜に似ています。日本で作られている料理のレシピでは、やはりスープ系が多くて、細かく刻んで酢の物にするとか、納豆と絡めて食べるとか、蕎麦やカレーなどに入れて食べるとかで、細かく刻んで食べる方法が中心のようで、それもアフリカなどに古くからある食べ方に学んでいるのでしょう。
この方法だと確かにたくさん食べることができます。またスーパーなどでも、ホウレンソウのような感じで、モロヘイヤとして販売されていますし、育て方ということでも、簡単なのでプランターや鉢植えでも育てられます。また食べられるので、その点でも人気があるということになります。
種付けや水やり、肥料について
またこの植物は臭みも癖もあまりないのですが、オクラなど同じで刻むと粘り気が出てきます。ですから納豆やオクラなどと混ぜて食べる人も多いようです。納豆もそうですが、粘り気がある植物は、非常に栄養価が高い野菜が多いようですので、モロヘイヤも健康管理に利用すると、非常に高い効果を発揮するということになります。
またこの植物は便秘の解消や肌荒れなどの肌のトラブルにも効果がありますので、女性にも非常に良い植物ということが言えます。その他の効果では、滋養強壮や疲労回復、抗がん作用などもあり、その点でも健康を回復するための野菜にもなるということでしょう。エジプトの王様まで治したということですから、病気に利用してみるのも良いということになります。
また家庭菜園での栽培での注意点としては、種子や種子のさやや発芽間もない若葉などには、毒性の強いストロファンチジン様物質という物質があるので、特に果実がついたものは食べないようにするのが無難です。販売されているモロヘイヤと同じような部分を食べるという方法もあります。具体的な育て方では、種まきは4月から6月初旬ぐらいで、収穫も6月から11月頃までできます。
肥料は収穫期と同じ期間です。やはりアフリカ周辺の気候を好むようで、理想的な発芽温度は発芽温度は25~28℃ということですが、20度ぐらいからでも5日間ぐらいで発芽するようです。また種まきもできます。ですが苗を植えるほうが早く収穫ができますし、非常に強い植物なので、初心者でも苗を植えることは簡単にできます。
増やし方や害虫について
種まきから育てる場合には、種を水で一晩ふやかせて蒔きますが、肥料は刺激が強すぎるようですので、化成肥料は入れないようにします。また薄く土をかぶせて、湿り気を与えておきます。また温度が低すぎると発芽しません。暖かい地域の植物だからでしょう。また発芽しますが、その後も温度が下がらないような環境で育てます。
そのように水分と温度管理が大切な植物ということになります。温かい環境が好きということでしょう。また環境としては、日当たりが良くて、水はけの良い土地が好きなようです。また土壌は、微アルカリ性土壌を好むそうで、強い酸性に弱いらしいので、石灰などを加えて、よく耕してから植え付けるのが良いということでした。
畝のサイズは50~70cmぐらいで、高さ10cmほどにします。また株間は30cm位で定植するというのが大体の基準になります。露地栽培でも低温が問題になりますので、暖かい地域の植物ということを忘れないようにします。肥料は半月に1度、野菜用化成肥料や鶏糞、油粕等を与えると、すくすく育っていきます。
また成長するようになった時には、水と肥料を欠かさないようにすることもポイントです。また収穫は、葉が3,4枚ついた状態で収穫をしていきます。また害虫はあまりないようですが、コガネムシやハマキムシ、ヒメシロモンドクガの幼虫などがいますので、その都度駆除しますが、風通しの悪いところなどでは、カビが生えたりする場合もあります。その点も注意が必要です。
モロヘイヤの歴史
今の日本人は栄養過多で、人類の歴史が常に飢餓線上にあった状況とはまったく違う日常生活になっています。そうなると飢餓に慣れた身体が急に栄養過多になってしまったので、身体も今までの、とにかく生きるために栄養を蓄えようとする状態から、その変化に対応できていないのだろうということですが、そのような中で、健康管理という面からも、
体に良い食べ物を如何に適量に摂取するかということが重要になってきます。量と質で解決しないといけないということですが、最近は健康に良い野菜なども目立ってきているように感じます。その中で良く話題になるのが、モロヘイヤという野菜です。加工されて健康食品になったり、色々な飲み物や食べ物に取り入れられて売られたりしています。
そして野菜の王様とも言われているようで、非常に健康に良い野菜ということのようです。それで家庭菜園などでも、モロヘイヤを育ててみようという人たちも増えるわけですが、この植物は歴史的にも古くから利用されていたということがわかっています。シナノキ科の一年生草本で、
元々の名前はシマツナソで漢字では縞綱麻と書くそうですが、色々な呼び方があり、タイワンツナソ、ナガミツナソ、ジュートなどと呼ばれてもいます。ツナソという言葉が共通しています。その中でモロヘイヤが一般化していますが、元々はエジプト語の方言だそうで、ペルシャ語でもあるということでした。いちばん親しみやすく覚えやすいからでしょう。
モロヘイヤの特徴
原産地と生息地は北アフリカで、利用されているのは今では、東南アジアやエジプトや地中海沿岸、アフリカなどですが、おもにアフリカ周辺で、昔から一般的な野菜であり、生命力も強いので栽培に向いていたということもあるのでしょう。その点でも日本人が食べても、安全な食材ということになります。
体験者が大勢、古くからいるということでもありますし、新しい食材でもないので、色々なことが健康的にわかっているということもあるからです。またアフリカなどをイメージしてもらえばわかりますが、高温で乾燥している土地でも育つ強い野菜ということがわかります。
またエジプトやアラビア半島では、古くから常食とされてきた野菜で、その歴史は5000年も遡ると言われています。それだけ健康に良いということがわかって、食べられてきたということで、日本人には、あまり馴染みはないのですが、健康管理でも利用すべき植物ということができます。また古代のエジプトの王様が、このモロヘイヤを食べて回復した話や、有名な3大美女のひとりのクレオパトラも好んで食べていたそうです。
そうなると美容と健康にも効果があるということになります。また食べ方としては、細かく刻んでスープに入れて飲んでいたそうで、日本の味噌汁の具のような感じで日常的に食べられていたということがわかります。日本でもスープや味噌汁に入れて食べると、効果が発揮できるのではないかと考えられます。加熱すると野菜はたくさん食べられるので、その効果もあったのでしょう。
-

-
トキワマンサクの育て方
トキワマンサクは日本をはじめ中国やインド、台湾などにも生息地があります。もともと日本に自生していた植物ではなく、原産地の...
-

-
メランポジウムの育て方
メランポジウムはメキシコや中央アメリカを原産としていて、その用途は鉢植えや寄せ植え、切り花などに用いられています。なお、...
-

-
ハイドロカルチャーの育て方
土を使わず、ハイドロボールと呼ばれる素焼きの石や、炭、砂等に植物を植えて育てる水耕栽培の植物栽培方法です。ちょっとした観...
-

-
ヤブレガサの育て方
葉っぱから見ると種類が想像しにくいですが、キク目、キク科、キク亜科となっていますからキクの仲間になります。通常は葉っぱの...
-

-
ポリキセナの育て方
この花の特徴としては、ヒアシンス科になります。種から植えるタイプではなく、球根から育てるタイプになります。多年草のタイプ...
-

-
クリアンサスの育て方
クリアンサスの特徴としては鮮やかな赤い色の花でしょう。またその他に白やピンクなどもあります。草丈はそれほど高くなく80セ...
-

-
スギ(杉)の育て方
スギが日本に登場したのは200万年前頃で、縄文時代や弥生時代には、すでに日本全国に広く分布していました。日本人が日本人に...
-

-
メコノプシスの育て方
ヒマラヤの青いケシと呼ばれる、メコノプシス・グランディスは、その名の通り、原産地がヒマラヤ山脈かチベット、ミャンマーなど...
-

-
ドラゴンフルーツの育て方
サンカクサボテンの実の事を総称してピタヤと呼びます。ピタヤはベトナムから輸出する時の商品名であり、日本に輸入される時には...
-

-
フィゲリウスの育て方
フィゲリウスはゴマノハグサ科に属している植物です。また別名をケープフクシアといいますが、花の形は他の植物と少し変わってお...




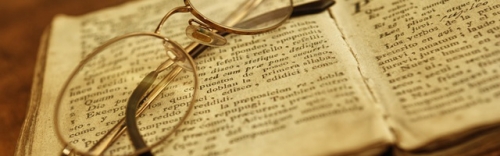





今の日本人は栄養過多で、人類の歴史が常に飢餓線上にあった状況とはまったく違う日常生活になっています。そうなると飢餓に慣れた身体が急に栄養過多になってしまったので、身体も今までの、とにかく生きるために栄養を蓄えようとする状態から、その変化に対応できていないのだろうということですが、そのような中で、健康管理という面からも、体に良い食べ物を如何に適量に摂取するかということが重要になってきます。