クラッスラの育て方

育てる環境について
クラッスラの育て方は、春頃から秋頃は日当りのよい場所で栽培して夏の気温が高くなるシーズンは半日陰や室内などへ移動することがおすすめです。冬場はとても寒いですので室内で育てていくことがよいでしょう。金のなる木は比較的耐寒性に優れている方ではありますが、
夏場の直射日光には弱いですので葉が焼けてしまわないように注意してあげましょう。また加湿にも弱い性質がありますので梅雨などのシーズンには、雨にあたってしまわないようにしておかないと根腐れをして枯れてしまうことがあります。鉢植えをして育てているような場合には、
梅雨のシーズンは軒下などに移動しておくことがおすすめされています。春から秋に成長する夏型で比較的小型の種類と、秋頃から冬頃にかけて葉が真っ赤に紅葉する火祭りという種類などがあります。葉が層に重なった奇妙な形をしているキムナッチーや暑さから
身を守るために葉の表面に微毛をもつ月光などもあります。火祭りは耐寒性、耐暑性ともに高くて寒冷地を除いて屋外でも栽培することが可能です。1年を通して日当りのよい場所に置いて強い光にあて栽培することによってしまった株になります。
月光は、蒸れや湿害に弱いですので夏場は直射日光を避けて風通しのよい場所で乾かし気味にして管理をします。鉢植えで育てていく場合には、鉢を直接地面に置いてしまうのではなくて棚の上などに置いておく方がよいでしょう。冬場は寒風いあたってしまわないようにしてください。
種付けや水やり、肥料について
クラッスラは、茎や葉に水分をたっぷりと貯えることができる植物ですので、水やりを忘れてしまっても簡単に枯れてしまう心配がなく平気で生きています。弁慶のように強いという意味から「べんけいそう」の名が与えられた種間交配などによって多数の園芸品種が作り出されています。
クラッスラは1年を通して少し乾かし気味して管理することが好ましく、冬は特に休眠に入りますので水をあまり必要としません。水を控えることによって植物の水分が減って体液が濃くなり寒さに強くなるとされています。土の表面が乾いてから4、5日くらい経ってから水やりをするくらいで大丈夫です。
肥料を施す場合には、生育するシーズンには2ヶ月に1回くらいの頻度で固形の肥料を置き肥するか、液体肥料を水やり代わりに与えてあげるとよいでしょう。真夏は特に肥料を施してあげる必要はありません。クラッスラは高温多湿に弱いですので、
鉢の中の水分が乾ききってからたっぷり水やりするようにしてください。火祭りは、秋から水やりや肥料を抑えて良く日にあててある程度の寒さにあてることできれいに紅葉します。クラッスラは、水が切れない地植えや株や暖かな室内の
鉢植えは紅葉しにくいとされています。用土には川砂を主体とした水はけの良い土が適しています。市販されている多肉植物の培養土などをそのまま利用したり、川砂と赤玉土と腐葉土を4対4対2くらいの割合で混ぜた土を利用することがおすすめです。
増やし方や害虫について
クラッスラの増やし方には、挿し木や葉ざしなどの方法が用いられています。適しているシーズンは5月頃から8月頃になります。挿し木をする場合は先端からおよそ5センチメートルから20センチメートルほどの長さに切り取りをしていきます。
切り取ったまま挿してしまうと腐ってきてしまうケースがありますので、切り取りをしたら日陰で乾かしておくようにしましょう。葉ざしをして増やしていく場合には、枝から葉を取っていって切り取り口を乾燥させてください。川砂に切り口の部分から浅く挿すことで、
およそ1ヶ月くらいで小さな芽が出てきます。小さな芽吹きからある程度生育してきたら鉢植えへと植え替えをおこなっていくようにしてください。水不足が続くと枝先の節目からも根を生やすことがあり、枝からちぎった葉1枚でも土に挿しておくと根を生やすほど
生命力が強い植物だとされています。株分けをして増やす方法を用いる場合は、群生しているタイプは2、3棟分に分けて古い葉や枯れた根を取り除いてから鉢に植えつけしていきます。古くなった下葉は、軟腐病の原因になってしまいますので早めに取り除いていきましょう。花が咲き終わったら、花茎を早めに切り取りしていきましょう。
クラッスラの病気には、葉に褐色の小さな斑点ができるさび病や黒っぽい斑点ができる黒星病、軟腐病などが発生することがあります。軟腐病は多湿や下葉の腐りが原因で発生しますので下葉は早めに取り除きます。害虫としては高温で乾燥するシーズンにカイガラムシが発生することがありますので駆除してください。
クラッスラの歴史
クラッスラはベンケイソウ科のクラッスラ属に属する南アフリカ、東アフリカ、マダガスカルなどが原産の植物です。クラッスラ属はギリシャ語で厚いという意味があり、大部分が多肉植物で葉が厚いことから名付けられています。南アフリカの原産種が多いのですが、
確認されている原種だけでもおよそ500種類ほどもあります。生息地は砂漠か草原で、日本国内には観葉植物として導入されました。クラッスラの和名は花月や星の王子、神童などが挙げられます。クラッスラの花はとても小さいため、どちらかというと葉の部分を観賞目的としていることが多いです。
可愛くて小さい花を咲かせるクラッスラの種類は大変多くあります。種間交配などによって多数の園芸品種が作り出されています。小型で群生するものや垂直に伸びて成長するものなど、草姿もさまざまなものが存在しています。鉢植えの観葉植物として広く普及している種類は
カネノナルキ「金のなる木」と呼ばれているものがあります。古くから栽培されている種類で春頃から秋頃に成長して冬には休眠に入る夏型のクラッスラだとされています。カネノナルキは、南アフリカの西ケープ州南部からクワズール・ナタール州にかけて
分布しています。日本国内には昭和元年頃に入ってきたとされます。和名には、フチベニベンケイという名前があり、園芸名には花月(かげつ)などの呼び名があります。金のなる木という流通名などで園芸ショップで販売されています。
クラッスラの特徴
クラッスラは常緑の多年草または低木で、茎が太くて直立しています。草丈は大きなもので3メートルほどにまで生育するものがあります。分枝するものやほとんどしないものなどさまざまな種類があります。葉は基本的には対生となってロゼット状の葉が幾層にも重なる仏塔型と呼ばれているタイプなどがあります。
葉は多肉質で花は通常細弁の5弁花でレッドやホワイト、ピンク、イエローなどのさまざまなものがあります。金のなる木は英語で表記するとdollar plantと言います。これは、葉が硬貨に似ているのが名前の由来だとされています。栽培業者などが5円硬貨の穴を頂芽に通して
枝が硬貨の穴を通ったまま成長するようにしたことで、効果が木になっているかのように見えることから「金のなる木」や「成金草」の園芸名で呼ばれるようになりました。金のなる木の葉は多肉質の長円形で長さがおよそ3センチメートルから4センチメートルほどになります。
明るめのグリーンで光沢があるのが特徴となっています。辺縁部は赤くて葉は低温にあうと紅葉して全体がワインレッドになりますので、特に秋頃から冬頃にかけてはとても色鮮やかになり葉に斑の入る種類などもあります。主に葉の形や株姿が楽しまれていますが、
花は小さな星のような形をしてほんのりピンクに染まった白花や淡いピンク色で茎の頂点にまとめて咲きます。小さいうちから花を咲かせる早咲きの改良品種なども登場しています。
多肉植物の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:セイロンベンケイの育て方
タイトル:グラプトペタラムの育て方
-

-
ヘリオプシスの育て方
特徴としてはこの花は1年草になります。キクイモモドキの名前の元になっているキクイモに関しては多年草ですから、その面では異...
-

-
イトラッキョウの育て方
イトラッキョウは日本原産の植物で、生息地が長崎県の平戸島に限られている貴重な植物です。準絶滅危惧種に指定されている貴重な...
-

-
コーヒーノキ(Coffea arabica)の育て方
コーヒーノキには栽培品種ごとに年代や経路が異なっていることや、栽培されている過程での突然変異等によって作られた品種が数多...
-

-
ミヤマクロユリの育て方
このミヤマクロユリは多年草になり、直立した茎の上部に細長い楕円形の葉を2~3段に輪生させており、茎の先に2~3輪の花を下...
-

-
レウイシア・コチレドンの育て方
この植物の特徴は、スベリヒユ科、レウイシア属になります。園芸上の分類としては山野草、草花となることが多くなります。花の咲...
-

-
唐辛子の育て方
中南米が原産地の唐辛子ですが、メキシコでは数千年も前から食用として利用されており栽培も盛んに行われていました。原産地でも...
-

-
ウェストリンギアの育て方
シソ科・ウエストリンギア属に分類され、別名にオーストラリアンローズマリーの名前を持つ低木がウェストリンギアです。別名にあ...
-

-
ギンヨウアカシアの育て方
ギンヨウアカシアの原産地はオーストラリアで、南半球の熱帯や亜熱帯を主な生息地としています。ハナアカシア、ミモザ、ミモザア...
-

-
ニオイスミレ(スイートバイオレット)の育て方
ニオイスミレは、別名でスイートバイオレットとも呼ばれています。スミレ科のスミレ属に属しています。耐寒性多年草で、原産地は...
-

-
ニューギニア・インパチエンスの育て方
ニューギニア・インパチエンスはツリフネソウ科の常緑多年草で、学名を「Impatiens hawkeri」と言います。イン...




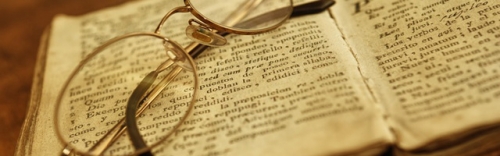





クラッスラはベンケイソウ科のクラッスラ属に属する南アフリカ、東アフリカ、マダガスカルなどが原産の植物です。クラッスラ属はギリシャ語で厚いという意味があり、大部分が多肉植物で葉が厚いことから名付けられています。