ニシキギの育て方

ニシキギの育て方
ニシキギは日当たりの良い場所もしくは明るい日陰などで育てることができます。紅葉を楽しみたい場合は日当たりが良いだけではなく、夜露や霜などにもあたりやすい場所を選択するのがベストです。土は水はけがよく、肥沃なものが良いので中粒の赤玉土2と完熟した腐葉土もしくは樹皮堆肥を1混ぜ合わせたものを使うのが良いです。
植えつけは12月から1月上旬、2月の半ば頃から3月上旬あたりの休眠期間中が良いでしょう。庭植えにする場合、2年未満のものには土の表面が乾いたらたっぷりと水を与えるようにし、鉢植えも同じくです。特に鉢植えは夏の高温期に水切れしてしまわないように気をつけます。
植えつけてから2年以上たっている庭植えのものに対しては雨水で十分なので特に水やりをする必要はありません。肥料は庭植えでしたら1月に寒肥として有機肥料を株元の周辺に与えます。鉢植えは3月に化成肥料を株元に追肥してあげるだけでいいです。
病気はほとんど心配いりませんが、注意したいのは害虫です。特にカイガラムシには気をつけたいところです。カイガラムシは樹液を吸って株を弱らせるだけではなく、カイガラムシの排泄物によって黒いすす状のカビができてしまうすす病になってしまいます。
こうなってしまうと光合成ができなくなってしまうので株は弱っていく一方です。カイガラムシの成虫は薬が効きにくいので古い歯ブラシなどを使ってこすって落としてしまいます。その時、くれぐれも葉は傷つけないように気をつけます。
6月頃から7月頃にかけてカイガラムシの幼虫が発生しやすいです。しかしこの時期ならば薬剤を使って退治することができるので、見つけたらすぐに薬剤散布をしたほうがいいです。
栽培する時のコツ
ニシキギは山野では日当たりが良い明るい場所に生えていることが多いので、栽培する場合もやはり日当たりはできれば良いほうが良いです。極端に日当たりが悪い場所ですと花付きが悪かったり、実も十分につかないのです。また秋になって紅葉する季節でも鮮やかな色合いにならない場合があります。
また植え付けは落葉期であればいつでもいいのですが、寒い地方の場合は厳寒期を避けて植え付けしたほうがいいでしょう。小さな苗を植え付ける場合はすでに成長している株よりも植え付けできる期間が長く、春に芽が出て葉が付く頃まではOKです。
庭に植える場合はあらかじめ土に堆肥や腐葉土を混ぜ込んでおきます。さらに水はけを良くするための工夫として山高に土を盛っておくのが良いです。そしてその中心には支柱をたてておきます。夏は乾燥しやすいので、そういう時は株元に腐葉土を敷いておきます。
これによって極端に土が乾いてしまうことはなくなります。剪定はほとんど必要ありませんが、伸び過ぎている枝などはカットして取り除いておきます。落葉期はいつでも剪定してもいいですし、それ以外ですと春に芽が出る直前である2月から3月頃が適しています。
ニシキギは芽吹きがとても良いので中途半端な長さでカットしてしまうとそこからたくさん芽が出てきてしまいます。これは樹形を崩すことになりますから、枝を切るのであれば枝分かれをしている部分を切るようにします。
生垣にしている場合は11月頃に全体を整える程度に刈り込みますが、この時期になるとすでに来年咲く花芽が出てきてしまっていますので、それごと刈り込むことになってしまいます。生垣では実を観賞して楽しむというよりは紅葉だけを楽しむと考えておくほうがいいです。
種付けで増やせるのか?
ニシキギは種付け、挿し木、とり木で増やすことができます。挿し木をするのであれば3月中旬から下旬が良い時期で、前年に伸びた枝を15cmほどカットして下半分を用土に埋めておきます。根も出やすいので、5年ほど育てれば株も立派になります。大きな株を欲しい時にはとり木を行ないます。
4月中旬頃に取りたい場所の枝の表皮をぐるりと一周りはがしておき、そこに湿らせたミズゴケを巻いてからビニールを巻いて乾かさないようにしておきます。3か月ほどで発根がしますから9月頃に切り離して植え付けるようにします。
種付けは秋に熟している果実を採取し、土の中に埋めてしばらくそのままにしておきます。すると周りの果肉が腐って種だけが残ります。この種を3月頃に取り出して撒けばよいです。もしくは採取した果実から種だけを取り出してビニール袋もしくは密封容器に入れて冷蔵庫で保存しておきます。
それを3月になったら清潔な土にまきます。これ以外の方法ですと根伏せという方法もあります。3月上旬頃に行います。根を掘りあげて直径が1.5cmほどある場所の根を15cmから20cmほどの長さにして水はけが良い土に5cmほどの深さで埋めておきます。
地面にじゃなければ、鉢を利用しても大丈夫です。これらの方法の中で一番簡単なのは挿し木ですが、せっかく種ができるので種まきに挑戦してみるのも良いでしょう。
ニシキギの歴史とは
ニシキギは和名で錦木と書きます。その名前の由来は秋の紅葉が錦に例えられたことでした。モミジやスズランノキと共に世界三大紅葉樹に数えられます。原産や生息地は日本や中国です。別名には枝の翼を矢に例えられてつけられたヤハズニシキギやシラミコロシ、ソバノキというものあります。
シラミコロシとつけられたのは昔、秩父地方でニシキギの実を砕いたものを頭髪油で練って毛じらみを退治したことが由来となっています。ソバノキというのは蕎麦の実に似た実をつけることから呼ばれるようになりました。また昔からニシキギはその薬効にも注目されていました。
枝についている硬いコルク状の翼部分を採取し、それを日干しにして乾燥させたものを生薬として使っていました。これは現在でも使われており、衛矛と書いてえいぼうと呼びます。月経不順にはを煎じて食間に3回に分けて服用します。またトゲ抜きにも効果的で、
衛矛を黒焼きにしたものをごはんで練ってそれをガーゼに塗って患部に直接ぬっていました。山野に自生していますので、人々の生活の中でわりと身近な存在としてあったのです。アジア全体には約170種ほどが分布しているといわれています。属名のエウオニムスは古代ギリシア語で良い評判という意味があります。
ニシキギの特徴
ニシキギはニシキギ科ニシキギ属の落葉低木で、北海道、本州、四国、九州、中国、アジア東南部などに広く自生しています。紅葉が美しいので庭木として植えられることもよくあります。樹高も1mから2mほどにしかならないので狭い場所でも植えることができるのがメリットです。
緑色をしている若い枝はコルクに似ている翼があるのが特徴です。この枝は生花にも好んで使われます。耐寒性、耐暑性共に強く、栽培も比較的しやすいので初心者の方でも挑戦しやすいです。晩秋になると橙赤色をしている種がぶらさがるようにしてなっているのも美しいです。
盆栽や生垣にもできます。花は10月から11月頃にかけて咲きます。花は葉のワキから葉より短い柄の集散花序を出してその先に数個だけ淡い緑色のものを咲かせます。葉は対につき、長い楕円形もしくは倒卵形をしています。毛はありませんが、縁は鈍い鋸歯があることも特徴です。
実は熟すと裂け、そこから仮種皮に包まれている種が1個だけ出てきます。これがはじけることで本当の種が出てきます。大きさは3、4ミリほどで肌色っぽいです。冬になると冬芽が出てきます。長卵形をしており、先はぴんととがっています。枝は最初は緑色で毛もありませんが、後にコルクのような硬さになり、4翼があらわれます。
庭木の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も参考になります♪
タイトル:サクラの育て方
タイトル:ツバキの育て方
タイトル:フジの育て方
-

-
イワヒゲの育て方
イワヒゲの生息地は日本の本州の中部より北の鉱山の地域です。かなり古くから日本にあり、栽培品種として流通しているものは日本...
-

-
そら豆の育て方
そら豆は祖先種ももともとの生息地も、まだはっきりしていません。 原産地についてはエジプト説、ペルシャ説、カスピ海南部説な...
-

-
リシマキアの育て方
リシマキアは育て方も簡単に行なうことができて、栽培しやすい植物になっています。それに原産国は北半球です。そしてサクラソウ...
-

-
サツキの育て方
日本が原産のサツキの歴史は古く5世紀から8世紀頃の万葉集にも登場します。江戸時代に多くの品種がつくられました。盆栽に仕立...
-

-
クリナムの育て方
クリナムとは世界の熱帯・亜熱帯に分布する大型球根植物です。その種類は約160種にも上り、大半の種はアフリカに分布していま...
-

-
リーフレタスの育て方
紀元前6世紀にはペルシャ王の食卓に供されたというレタスですが野菜としての歴史は非常に古く、4500年前のエジプトの壁画に...
-

-
アリッサムの育て方
アリッサムはミヤマナズナ属のアブラナ科の植物で、日本で一般的にアリッサムと呼ばれているものはニワナズナなので、かつてはミ...
-

-
ユズ(実)の育て方
ユズの実の特徴として、成長して実をつけるまでの時間の長さが挙げられます。桃栗八年とはよく聞くことですが、ゆずは16年くら...
-

-
グロリオサの育て方
グロリオサはアフリカ、熱帯アジアが生息地で5種が分布するつる性植物です。グロリオサの名前はギリシア語の栄光ある、名誉ある...
-

-
モモバギキョウの育て方
この花の特徴としては、キキョウ科、ホタルブクロ属となっています。園芸においては山野草、草花としての利用が多くなります。形...




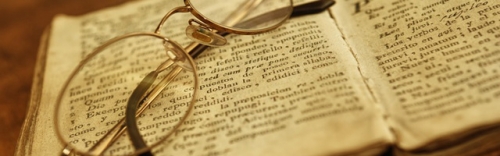





ニシキギは和名で錦木と書きます。その名前の由来は秋の紅葉が錦に例えられたことでした。モミジやスズランノキと共に世界三大紅葉樹に数えられます。原産や生息地は日本や中国です。