マンデビラの育て方について

マンデビラの育て方
マンデビラは春から秋にかけては屋外の日当たりの良い場所で育て、冬になったら10度以上の気温を保つように室内にとりこんで、窓際などの日当たりの良い場所に置いてあげるといいです。冬でも15度以上の気温を保っていれば花を咲かせることがあります。土は水はけの良いものが適しています。
鉢植えであれば小粒の赤玉土を6、腐葉土を4の割合であわせた土を使うようにするのも良いです。水は基本的には栽培していてマンデビラの土の表面が乾いた時にたっぷりと与えるようにすると覚えておくといいです。秋からは少しずつ水やりの回数を減らしていくのが育て方のコツです。冬は少し乾燥ぎみにするくらいでちょうど良いです。
肥料は春に新芽がのびてきたなと思った時に水の代わりに液体肥料を月2、3回与えるようにするといいです。固形肥料であれば2か月に1度で十分です。肥料は秋まで与えて、後は与えません。寒さには弱いですから、マンデビラはできれば鉢植えなど移動できるもので育てたほうがいいです。
わきからのびるツルで邪魔なものや長く伸び過ぎているものがあればカットしまってもOKです。これは日当たりが悪くなって株元などに日光が当たらなくなるのを防ぐためと、ツルがあまりに多いと花付きが悪くなってしまうからです。花が咲き終わった後は翌年の花付きを良くするためにツルを3、4節分ほど残して他はカットしてしまいましょう。
マンデビラの栽培の注意点
栽培する時の注意したほうが良いことは鉢植えで栽培している場合、根がよくはる植物ですから1年に1度は必ず植え替えするようにしたほうがいいということです。4月頃から5月頃にかけての時期に植え替えするのが最適です。気温が10度以上になった時に新芽がのびてきているようであれば植え替えしてもいいというサインです。
植え替えをする時は古い土は十分に落としてしまい、一回り大きな鉢に植え替えします。購入した苗を使うのであれば、芽の先端をつんでしまってワキ芽を出させるのがボリュームを出す育て方になります。鉢はあくまで一回り程度大きいものにしないと、あまりに大き過ぎてしまうと土が乾燥されることなく過湿状態になりやすくなります。
根腐れを防ぐためにも忘れないでおきたい重要なポイントです。もし庭植えをするのであれば植える前に土の中に苦土石灰を1平方メートルにつき100gほど混ぜておいて、植えつける時にも今度は完熟牛ふん堆肥か腐葉土を1平方メートルあたりで2キログラムほど、粒状肥料を1平方メートルあたり150g程度混ぜておくのが良いです。
株と株の間は20cmから30cmほどあけておくのが良いので、10号鉢でしたら2株ほど植えるのが良いでしょう。またマンデビラは少なくとも半日は日光にあたっていなければ花が咲かなくなってしまいますので、植える場所はよく考えて決めなくてはいけません。
種付けで増やすことはできる?
マンデビラの育て方を理解したら次は増やしてみることに挑戦してみましょう。マンデビラは基本的には挿し木によって増やしていきます。もちろん花が枯れた後もそのまま放置しておけば種付けはされますが、種から育てることはとても難しいので初心者の方は苗を購入するか、挿し木からチャレンジするのが良いでしょう。
種付けをしないのであれば枯れた花は落ちてしまうと病気のもとになってしまうので摘み取ってしまうほうがいいです。挿し木は茎のてっぺんから葉でいうと4枚目くらいのところでカットし、切り口から出てくる乳白色の液体をよく洗い流します。これをそのままにして挿し木してしまうと成長が妨げられることが多いからです。きれいに洗い流したら、あとは川砂か赤玉土の中に挿しておくだけです。
20日前後たつと根が出てきますから、そうなったら鉢植えなどに植え替えしてあげればよいです。気温が15度以上になった頃が良いタイミングといえます。大きな葉は半分ほどに切って蒸散を抑えるようにします。種付けさせたものは自然とこぼれ種となって増えることもありますが、自分で採取するのであれば地面に落ちないように気をつけて採取しましょう。
草丈をあまりのばしたくない場合はある程度茎がのびたらカットしてわき芽を出させてボリュームだけを出すようにしないとどんどん大きくなってしまいますので注意です。グリーンカーテンとして利用することもできます。つる性のものは放っておけば3mほどには伸びてしまいますので、これを活かしてナチュラルグリーンカーテンを作ってしまうのもオススメです。
用意するのは10cm角の編み目のネットと支柱だけです。カーテンにしたい場合は早めに摘芯をして枚数を増やしていくようにし、ネットにつるを広げるようにして誘引していくことでまんべんなくひろがって室内が見えないように目隠し代わりにもなります。夏は涼しい陰を作ってくれますからエコにもつながります。
マンデビラの歴史
マンデビラはキョウチクトウ科マンデビラ属で、原産地や生息地は北米や中南米です。チリソケイやディプラデニアという別名もあります。マンデビラという名前がつけられたのは19世紀のブエノスアイレス駐在大使だったマンデビル氏が由来だといわれています。100種類ほどの仲間がメキシコからアルゼンチンの辺りにかけて自生しているのです。
正確な情報ではマンデビラとディプラデニアというものはかなり近い種ではありますが、実は別物です。ディプラデニア属そのものは日本へは渡来していないといわれています。日本ではとても似ているということでマンデビラをディプラデニアと呼ぶようになったということがあります。最初からあった一重咲きの品種に加えて最近では品種改良が進められるようになり、八重咲き品種も多く出始めました。
花付きはとても良いですから初夏から秋頃まではきれいな花を楽しむことができます。つる性の植物なので日本へ渡来して以来、鉢植えなどだけではなく、アーチにもよく使われるようになっています。形をきれいに作ってあげることで鉢植えでも支柱を使ってきれいに飾りつけることができるようになるので挑戦している人も多いです。
マンデビラの特徴
つる性植物で、熱帯の植物のわりには寒さにも強いです。冬越しをさせても葉を落とすことがほとんどありません。もし葉がたくさん落ちるようになっていたら根詰まりか根腐れを起こしている可能性があります。赤や白、ピンク色のラッパ型の花を初夏から初秋にかけて咲かせます。葉には特徴があり、鈍い光沢があって独特のしわが入っています。
草丈は50cmから100cm以上になり、横幅は30cmから100cm以上になります。非常につるの伸びがはやく、あっという間に大きくなりますので驚く方も少なくありません。鉢植えによる販売が多かったのですが、現在では苗で販売されていることもよくあります。
トレリスやフェンスに絡めたりして楽しむことができますし、花はいかにも温かい国の花という感じが伝わるものですから、寄せ植えなどで一緒に植える花は南国系のものをもってくるとバランスがとれやすいです。苗を購入する時にはなるべく大きめのものを選ぶことで育てやすくなります。
小さな苗はなかなか思うとおりには育ってくれません。新芽や茎には栄養たっぷりの汁を吸おうとアブラムシが寄ってきてすぐに増えてしまいますので見つけたらできればその日のうちに薬剤などで退治してしまいましょう。
-

-
バラ(つるバラ)の育て方
バラの種類は、かなりたくさんありますが一般的には世界で約120種類あると言われています。記録によれば、古代ギリシアの時代...
-

-
猫が大好きな猫草の育て方
猫が大好きな植物に猫草があります。猫草はペットショップなどでは食べやすい長さに成長したものが販売されていますが、「猫草」...
-

-
自宅で植物を育てよう
部屋に植物があると生きたインテリアにもなり、その緑や花の華やかな色は日頃の疲れやストレスへの癒やしにもなります。ただ、生...
-

-
シロバナノヘビイチゴの育て方
シロバナノヘビイチゴの特徴は何と言っても、その花が白いことです。また、赤い果実を付けるのですが、どちらかと言うと普通の苺...
-

-
花の栽培を通して喜びを感じる
手作りの物を口にしたり、目の保養をする事ができたら、こんなに素晴らしい事はないと考えている人は多く、実際に実行に移す人の...
-

-
アメリカアゼナの育て方
アゼナ科アゼナ属で、従来種のアゼナよりも大きく、大型だが花や葉の姿形や生育地はほとんどが同じです。特徴はたくさんあります...
-

-
レモン類の育て方
レモンと言えば黄色くて酸っぱいフルーツです。レモン類には、ライムやシトロンなどがあります。ミカン科、ミカン属になっており...
-

-
ヒデリコの育て方
ヒデリコは高さが20~60cmの小柄な植物で、秋には種子を落として枯れてしまう1年草です。湿地や田んぼのあぜなどに生育し...
-

-
ダボエシアの育て方
ダボエシアは学名でDaboeciacantabrica’bicolor’といいますが、分類で言うとツツジ科ダボエシカ属に...
-

-
ミセバヤの育て方
特徴として、バラの種類であることがわかっています。バラ亜綱、バラ目、ベンケイソウ科、ムラサキベンケイソウ属になります。園...




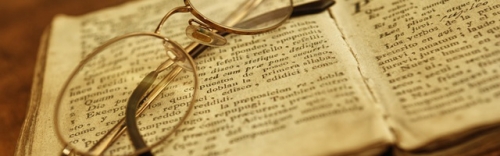





マンデビラはキョウチクトウ科マンデビラ属で、原産地や生息地は北米や中南米です。チリソケイやディプラデニアという別名もあります。マンデビラという名前がつけられたのは19世紀のブエノスアイレス駐在大使だったマンデビル氏が由来だといわれています。100種類ほどの仲間がメキシコからアルゼンチンの辺りにかけて自生しているのです。