ハツユキソウの育て方

育てる環境について
日当たりがよく暖かで、少し乾燥気味の環境が栽培に適しています。成長が早く枝の伸びもいいので、背丈を押さえて育てたい場合は先端に生える芽を摘んでわき芽を伸ばしていきます。7月までに二回ほど芽を摘んでやると草丈を抑えられ横に広がり、ボリュームのある株に育てることができます。鉢植えで育てる場合は庭の日当たりの良い居場所に移動させながら育て、
庭に直に植える場合には日光がよく当たる場所を選んで植えるといいでしょう。ハツユキソウは寒さに弱い植物ですが、露時期の冷え込む日でも基本的にはそのままで大丈夫です。庭の暖かい場所へ植え替えようと掘り起こしてしまうと、せっかく根付いていた根を傷つけ枯れてしまう恐れがあります。
条件を満たした場所で育てていても枯れてしまったという場合はほとんどが植え替え時のトラブルです。このようにハツユキソウは植え替えに繊細な植物なので、ポット株から植えるときにも根を刺激しないよう優しく植えましょう。土質にこだわらず育てられるので、鉢植えの際に選ぶ土は草花の培養土や、赤玉土と腐葉土を混ぜたもので十分育ちます。
背丈がある程度大きくなってきたら、先端の葉の様子や重さを見つつ支柱を立てる必要があるため、大きく育てたい場合はあらかじめ用意しておくとスムーズでしょう。大きくボリュームのある株に育てる場合は市中は不要になりますので、どう育てたいかをあらかじめ考え決めておくのもいいかもしれません。
種付けや水やり、肥料について
およそ25℃前後が発芽にもっとも適した気温のため、種から育てる場合は4月下旬から5月の暖かい頃を目安にしましょう。直根性で移植を嫌うので、苗を植える場合は、まだ苗が小さいうちに根が傷つかないようにそっと植え、その後は芽を摘みながら葉の枚数を増やし育てていきます。乾燥した場所を好みますが、極度に乾燥させてしまうと生育が極端に悪くなります。
土の表面が乾いたらたっぷりと水を与えましょう。肥料は植え付ける際に化成肥料を混ぜ混んでおきます。その後夏になり葉が色づいてきたら同じ肥料を少量追加します。水を豊富に与えることで大きく育ち、逆に少な目にすることで草丈も調節できます。真夏の直射日光にも負けない強さがありますので、育て方としてはしっかりと日に当て、水をやり、
植え替えをせずに芽を摘まみながら育てる、がポイントです。庭先に植えて毎年増やしていきたい方は、実がついて乾燥したら種を取り保存しておくのがおすすめです。保存して管理しておくことで、翌年に増やしたい数だけ種を撒くことが可能になります。発芽しやすいハツユキソウは自然に落ちた種でもどんどん増えていきますので、
芽が出て来たら感覚を考え間引きしておくことも大事です。毎年増えて雑草化してしまったという例も多いため、周囲の草花のバランスなども考え、種や芽はしっかりと管理して美しい庭先を保ちたいですね。夏の暑い盛りに、たくさんの白い葉が風に揺れている様はとても見事です。
増やし方や害虫について
ハツユキソウを襲う害虫は主にハダニです。ハダニとは、気温が高く乾燥した場所に生息する害虫です。葉の裏につき吸汁しますので、葉が見所のハツユキソウには天敵です。また、お互いに適した環境も同じなので、一度ハダニが発生してしまうと瞬く間に被害が広がってしまいます。
葉に小さく白色の斑点が無数にできたり、かすり傷のような模様ができるのがハダニの特徴です。また、雲のように糸をはいて移動し、数が増えると蜘蛛の巣状の網をかける習性がありますので、ハツユキソウの先端付近に巣を見つけたらまずハダニがいると疑いましょう。ハダニが発生すると葉がボロボロにされてしまうため、
薬剤でしっかりと駆除しましょう。葉の裏に密集して生息していることが多いので、薬剤を散布する際には葉の裏にもきちんと吹き付けるようにします。どうしても薬剤を使いたくないという場合は、少量発生の場合のみ葉の裏に密集するハダニをセロハンテープで取り除く方法もあります。または木酢を薄めた物やトウガラシをつけた液などを散布する方法もありますが、
これだと一時的に効果はありますがまた戻ってきてしまいますので駆除には有効ではありません。その他にもうどんこ病という病気にかかることもあります。うどんこ病は葉が白い粉を振ったようなカビにおおわれるのが特徴で、前途のトウガラシをつけた液などが殺菌作用がありとても有効です。害虫と病気の種類に分けて効果的に薬剤などを利用し育てましょう。
ハツユキソウの歴史
ハツユキソウは夏から秋にかけて鑑賞される花です。ですが花自体は小さく、主に鑑賞されるのは葉の部分です。見頃になるときれいな緑の葉の上にまるで雪が淡く積もったように見える事から、和名をハツユキソウ、英名をスノー・オン・ザ・マウンテンといいます。原産地は北アメリカのミネソタ、コロラド、テキサス州で、日本には1800年代に入ってきたといわれています。
トウダイグサ科ユーフォルビア属に分類される花で、クリスマスの時期になると葉を真っ赤に染め見る人を楽しませるポインセチアと同じ分類です。多くのハツユキソウは一年草で、春に種を植え夏、秋の鑑賞期が過ぎると、霜が降りると共にかれて消えていきます。ですが、翌年の春になると落とした種から芽が出て、翌年また咲く事も多いようです。
土質にこだわらずとも育ちやすい部類ですので、庭先に株をひとつ植えれば毎年楽しめるガーデニングに適した花だといえます。毎年種を保存して春先に植えてやれば、順調に増やしていくことも可能です。適した生息地としては、日当たりがよく暖かい場所を好みます。最近ではご家庭の庭先や、公園の花壇などでも栽培されています。
百年以上も前に日本に渡り、秋の終わりに葉をきれいに白く染めた姿は、四季の美しい日本では本当に初雪が降ったと思わせる様だったことでしょう。まだ暑さの残る季節に、白く色づいた葉がとても涼しげに見えるハツユキソウは、昔の人々にもその姿で涼を与えていたのかもしれません。
ハツユキソウの特徴
ハツユキソウは背丈がおよそ1メートル程の高さに延び、その葉先に小さな花をつけます。白く色づく葉は花の回りにある唇型の葉です。この葉がハツユキソウの特徴で、夏の開花時期と同時に徐々に覆輪状に白く縁取られていきます。茎の下の部分から生えている鮮やかな緑の葉と白のコントラストが非常に美しい植物です。
やや厚めのしっかりとした葉で、白く染まり始める前は灰緑色をしています。葉の緑を鮮やかに育てたい場合は、やはり日当たりのい居場所で日光をたくさん当てて育てます。見所が葉の色の違いにあるので、なるべく気を使いたいところですね。花の回りにだけ白い葉がついているので、白い葉自体が花のように見えます。
見頃を過ぎると小さな花が枯れ緑色の実をつけ、その実の中に種が入っています。初夏に挿し木苗が売り出されるのですが、種からも育てられます。特に種から育てた場合はハツユキソウ本来の大きめな背丈に成長することが多く、自分が求めるボリュームに合わせて株か種かを選ぶといいでしょう。背丈が高く育つのも特徴のひとつですが、
あまり高くなりすぎると風が天敵になります。夏ごろから秋にかけての見頃には台風も多く、すらりとした茎が風でなぎ倒されてしまう場合があります。鉢植えなどで育てている場合はそういった日は屋内に避難させ、庭に直に植えている場合は添え木をして支えましょう。また、先端部に葉が集中して生えるため頭が重くなりしなだれてしまう場合も添え木でそっと支えましょう。
-

-
植物の栽培によるビジネス
農業の次世代化は、これまでの従来型の農業からの改革案として、農家離れによる休耕地をいかに活用していくか、食糧難に対応させ...
-

-
センリョウの育て方
センリョウは日本や中国、台湾、朝鮮半島、インド、マレーシアなどが原産の、センリョウ科センリョウ属の常緑性の低木です。 ...
-

-
アオキの育て方
庭木として重宝されているアオキは、日本の野山に自生している常緑低木です。寒さに強く日陰でも丈夫に育つうえ、光沢のある葉や...
-

-
イタリアンパセリの育て方
パセリはヨーロッパ中南部から北アフリカにかけての地中海沿岸が原産のハーブです。学術名の「ペトロセリウム」は、生息地を砂礫...
-

-
ヨルガオの育て方
ヨルガオというものは朝顔の仲間でもあるもので、熱帯アメリカ原産であり寒さに弱いものですので、一年草として扱われているもの...
-

-
センニチコウの育て方
熱帯アメリカが生息地の原産で、日本には江戸時代に渡来しました。江戸時代の初期に渡来して、江戸時代に書かれた書物にもその名...
-

-
トケイソウの育て方
原産地は、北米、ブラジルやペルーなどの熱帯アメリカです。パラグアイでは国花とされています。現在、園芸に適した品種として知...
-

-
ニラの育て方
東アジア原産で、中国西部から東アジアにかけての地域が生息地と考えられます。中国では紀元前から栽培されており、モンゴル、イ...
-

-
おいしいほうれん草の育て方
野菜の育て方を覚えれば、誰でも美味しい野菜を誰でも育てることが出来ます。そこでほうれん草の栽培について説明します。ほうれ...
-

-
カンアオイの育て方
カンアオイは、ウマノスズクサ目ウマノスズクサ科カンアオイ属に属する植物です。日本名は「寒葵」と書かれ、関東葵と呼ばれるこ...




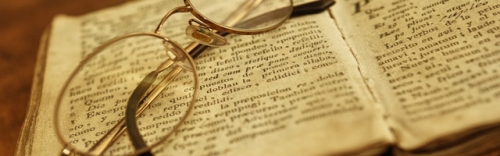





ハツユキソウは背丈がおよそ1メートル程の高さに延び、その葉先に小さな花をつけます。白く色づく葉は花の回りにある唇型の葉です。この葉がハツユキソウの特徴で、夏の開花時期と同時に徐々に覆輪状に白く縁取られていきます。茎の下の部分から生えている鮮やかな緑の葉と白のコントラストが非常に美しい植物です。